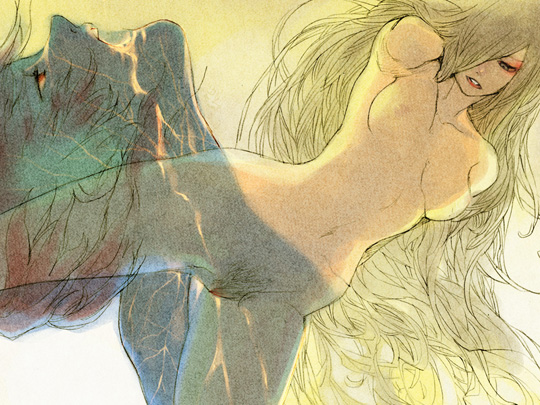
注目の大型官能小説連載 毎週木曜日更新!
ニュースタイル・平安エロティカル曼荼羅
New Style Heian Erotical Mandara [Kouchu no hitoya]
艶めかしき人外の化生に魅せられた侍が堕ちていく魔的なエクスタシーの奈落――。今昔物語の一編を題材にとり、深き闇の中で紡がれる妖と美の競演を描くニュースタイル・平安エロティカル曼荼羅。期待の新人作家・上諏訪カヤハと絵師・大往生ジダラクのカップリングで贈る会心のアブノーマル・ノベル!!季節が移り変わろうとしている。
日中はまだ陽炎に景色が揺らぎ、暑さを耐え難く思うことも多いものの、空を見上げると、空気が澄んで高くなっていた。
(屋敷で一緒に働いていた連中は、今、どうしているだろう)
日陰を選び選び歩いていた吉丸は、道端の石を蹴りながら、ふと懐かしい顔ぶれを思い出した。
残暑に喘ぐ小路には人の姿は見えず、吉丸だけが夢の中を彷徨っているかのように、陽炎の中にぽつんと立っていた。太陽はようやく西に傾きかけたところだ。四方から蝉の鳴き声が乱反射して、まるで京の空に音で蓋をしているかのようだった。
初めて強盗に入った日から、まだ二月(ふたつき)と経っていない。しかし、狐面の盗賊団の一員として貴族や豪族、豪商の屋敷に押し入ることは、この長いとはいえない間にすでに十数回を数えていた。太刀を手に家の中に斬り込んでいったこともあれば、弓矢を持って守りを固めることもある。回数を重ねるうちに、吉丸は次第に一目置かれる存在となっていった。
だが、 それが狐たちからの信頼につながったかというと、そうだとは思えない。狐や覆面たちが吉丸に友好的な態度で接してくるようなことはなかったし、彼らの顔は常に面で覆われたままだった。しかしそれは、彼らが吉丸を信頼していないというよりは、誰もが誰もに対してそうだったのかもしれなかった。彼らはいつも時間になると一人ずつどこからともなく現われて、「仕事」が終わると声を掛け合うこともなく散り散りに去っていく。吉丸もまた、そういう状況で素性を明かそうとは思わなかった。
首魁狐の正体も、いまだにわからない。会うたびにどことなく阿夜に似ているとは思うのだが、決め手になるものがまったく掴めずにいた。
吉丸はいつからか、盗品の分け前にもあずかるようになっていた。主の屋敷に戻らない以上、そうしないと飯を食ってはいけないと、彼は自分に言い聞かせた。阿夜も実戦には加わらないものの(あの首魁狐が彼女でなければ、だが)それなりに盗品は手にしていたようだから、そこを恃みにするということもできたが、盗品を実際に手にしようがしまいが罪の重さは同じだろうと、腹を括ることにした。
ところで。
吉丸は今、今夜強盗に入ると阿夜から伝えられた、ある豪族の屋敷のまわりをぐるりと回って帰ってくるところだった。内部の造りや役割分担については今夜集合した際に改めて伝えられるというが、それを待つまでもなく、明るいうちに見られるだけのものを見ておきたかった。
屋敷の周りは高い塀で囲まれていたから、中の様子はほとんどわからなかった。しかし塀の崩れから見渡せる部分はあったし、全体的な雰囲気を把握しておけるだけでも十分だった。そんな曖昧な把握がどんな時に、どんなふうに役に立つのかと訊かれたら、はっきりとは答えられない。今まで培ってきた勘が要求するだけのものだが、それを馬鹿にはできなかった。
屋敷は塀こそ金持ちめかして高かったが、規模自体はそれほどでもないようだ。家の木材は古びている。一度火の手が上がったら、あっという間に回るだろう。門の守りは必要最小限にして、できるだけ大人数で押し入り、火が回る前に一気に片を付けるのが最善の策だと考えられた。
家に戻ると、簾の内で眠っていた阿夜の隣に吉丸も横になった。夜になるまで少し眠っておこうと思った。
――昔は、 昼間眠そうにしている阿夜を不審がったものだ。
懐古するにはまだ早すぎるな、と苦笑しながら目を閉じる。長く盗賊稼業に身を置くうちに、昼夜の生活が逆転してしまったのだと、今ではわかっていた。
強盗に入る日を除いては、二人は毎晩睦み合った。笞で打たれるようなことはあれ以来なかったが、それでも、世の常の人がもし目にしたら眉を顰めるどころか、声を上げて罵りかねさえしないことを吉丸は阿夜と繰り返した。今では阿夜の体から迸るものまで、汚いとも嫌だとも思うことなく受け入れられる。というより、自ら欲している。初夏のまばゆい陽光のように輝く液体を喉を鳴らして飲んでいると、吉丸は至福に酔いしれることができた。
――神仙郷に湧く極上の酒とは、こういうもののことを言うのかもしれぬ。
顔の上に跨られ、ほのかに柔らかな茂みを舌で掻き分けて拝受する神がかった金色に感じ入るたび、失うものはあったとしても、やはり何としても阿夜の傍らに居続けたいという思いを強くする。と同時に、失ったものを惜しむ心も、その液体に洗い流されていくかのように次第に色褪せていくのであった。
その夜、吉丸は黒い水干を着込み、籠手と脛当、脛巾を着け、太刀と弓矢を携えた軽武装で家を出た。
吉丸は一度、 自分が外に出ている間にお前は何をしているのかと阿夜に訊いてみたことがある。阿夜は家で湯を沸かし、食事の支度を整えて吉丸の帰りを待っているのだと事も無げに答えた。
狐面や覆面たちと落ち合う場所が蓼中の御門であることも、最初の時と変わらなかった。しかし、味方を味方と知らせる合図はその都度変わった。それは阿夜が事前にどこからか聞いてきて、吉丸に伝える。
丑の刻を少し過ぎた頃、一党は忍ぶ足を早くも吹き始めた秋風にまぎらわせて、今夜の獲物が眠る屋敷を目指した。上空は風が強いのか、雲の動きが早い。有明近くの月はやっと東の空に昇ったばかりで、今にも吹き飛ばされてしまいそうに細かった。星も散り乱れる今夜は雲の動きで明るさがちらちらと変わったが、それを面倒と思うような狐らでもない。彼らは最初から、吉丸が睨んだ通り短時間で片を付けるつもりでいた。
「四半刻」
黒狐は御門の前で、居並ぶ狐と覆面たちに そう宣告していた。「合図は出さぬ。それを過ぎたら各々の判断で去れ。遅れた者は捨て置く」。
塀の上に乗った狐面と覆面が建物に向けて火矢を続けて放った。風を切って飛んでいった矢が当たった壁に、ちらちらと赤い火がきらめき始める。それが広がっていくのを確認して、吉丸たちは一気に切り込んだ。
母屋の遣戸を蹴破って中に乱入する。数秒もしないうちにあちこちで女の甲高い悲鳴があがった。視界の端では、早くも、侍女に囲まれていた女を引きずり出して、夜着を剥いでいる仲間の姿も見える。
吉丸はさらに廊を駆けた。後から仲間が何人か従ってきた。戸という戸を片っ端から蹴り壊して進む。逃げる者はいちいち追わないが、歯向かおうとする者には容赦はしない。太刀が脂でぬめると、相手から武器を奪った。それがまた使い物にならなくなると二本目以降は仲間から、「ちょっと、貸してくれ」と返事も聞かずにぶん取ったが、それで文句を言う者はいなかった。吉丸の後に続く者たちは、切り伏せられた死体を退けながら目ぼしい物を見つける作業にいそしんだ。そんな一連の流れはここのところ、仲間内でひとつの手法として確立されつつあった。
角を曲がると、向こうから地響きのような足音が聞こえてきた。おそらく武装した侍だろう。間も置かず煙越しに見えてきたのは、予想した通り、胴丸姿の影だった。
傍若無人に屋内を駆け回っていた吉丸の前に、侍は矛を突き出して立ちはだかった。加勢はなく、一人のようである。肩幅が広く全体的に大柄だが、よく見れば無駄なものの一切ない、研ぎ尽くされた体つきをしている。低く落とした下半身と、そこに支えられる重厚な上半身で構成された全体は、一見、柔軟性や瞬発力といったものとは無縁のようにも見えるが、筋肉の動きはあくまでもしなやかで、その巨躯からは想像できない速さの攻撃が繰り出されることが予測できた。
――今までのようにはいくまい。
吉丸は太刀を構えなおし、侍と相対した。
と、同時に、
――あれ、こいつは……?
目の前の侍に、いつか、どこかで会ったことがあるという気がした。まさにこの体つき、まさにこの構えに見覚えがあった。相手の顔は鉄の半首(はつぶり) の影になって識別ができない。だが、
「三郎か!」
こちらの喉元を狙って矛が一直線に繰り出された刹那に、吉丸はその男の名を叫んだ。言いながら、矛先をすんでのところでかわす。
「何!?」
矛をかわされた男は驚きながらも、すぐに体を反転させ、再度武器を構えた。男の驚愕を見る限り、吉丸が発したその名は正しかったのだろう。だが、動揺しながらも隙は一切できていなかった。
「俺だ」
吉丸は言いかけ、、懐かしさのあまり覆面を剥ごうとしたが、途中でその手を、はっと止めた。
俺は今、盗人だ。ここで顔を見られてどうする。
だが、その憂慮も空しく、三郎と呼ばれた侍はすぐに吉丸の正体を見破った。
「吉丸……か……?」
吉丸が相手の体つきや構えに見覚えがあったのと同様に、三郎もまた、そこから導き出したのだろうと思われた。それは、さしたる苦があることでもなかっただろう。二人は二十年以上の長きに渡って支え合ってきた友同士だったのだから。
あちこちでパチパチと家屋が燃えはぜる音と悲鳴が響き渡っていた。あたりにはむせ返るような血生臭さが充満している。しかし吉丸は突如として、そういったものの届かない白い静寂の世界に放り出された。三郎と過ごした日々の思い出が、洪水のように押し寄せてくる。
――あれは俺がまだ、坂東にいた頃だ。
あえて辿ろうとしなくても、記憶は次から次へと溢れ出してきた。
その頃はまだ吉丸も三郎も、東国の片隅で、名もない半農半士の子として暮らしていた。
(続く)

上諏訪カヤハ フェティシズムと日本史と妖怪・人外と幻想文学をこよなく愛しすぎて、
全部足さずにはいられなくなった水瓶座・A型。
好きな歴史上の人物は世阿弥。

大往生ジダラク 2010年より少しずつ活動開始した新米絵描きです。1988年生まれ。和モノ怪奇モノ大好物です、座右の銘は【いやらしければなんでもいいわ!】です、宜しくお願いいたします。
大往生ジダラク公式サイト=「大往生のジダラク生活」
10.10.07更新 |
WEBスナイパー
>
口中の獄
| |
| |
































