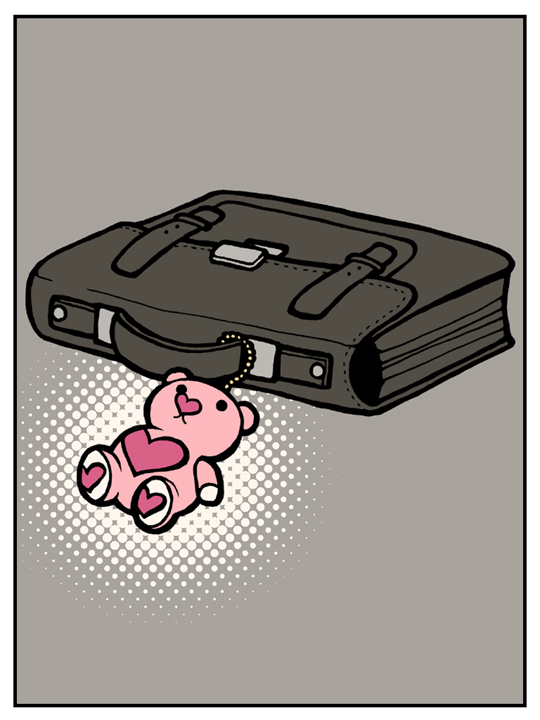
毎週土曜日更新!
Alice who wishes confinement
私の居場所はどこにあるの――女児誘拐の不穏なニュースを観ながら倒錯した欲望に駆られた女子高生が体験する、エロティックでキケンで悩み多き冒険。理想と現実の狭間で揺れ動く乙女心とアブノーマルな性の交点に生まれる現代のロリータ・ファンタジー。オナニーマエストロ遠藤遊佐の作家デビュー作品!!――ああ、忙しい……時間がない!
そんなふうに思いながら動くのは久しぶりのことだ。まゆりは朝から自室の中でバタバタと動き回っている。
四六時中“監禁したいご主人様のための掲示板”に張り付いて、微妙なさじ加減で書き込みを続けた。今の自分がタナベに監禁してもらうためにできる手は全部打ったと思う。あとは数日後に迫ったXデーを待つだけ。まさに“人事を尽くして天命を待つ”の心持ちだ。
しかし、やれることをやったからといってのんびりしてもいられなかった。本当の勝負は狙い通り監禁されてからなのだ。ただ家の中に閉じ込められているだけじゃ、登校拒否になってからの2年間と変わらなくなってしまう。
――これからの何日かで、できるだけ快適な監禁生活が送れるように準備を整えなきゃならないわ。効率的に、うまくやらなくちゃ。
そう考えると焦りが湧いてきたが、同時に気分も高揚してきた。
まゆりは他人を押しのけてまで積極的に何かをやろうというタイプではなかったが、もともとこういう作業が嫌いではない。
先を読み、最小の労力で最大の成果をあげられるように道筋をつくる。必要な物と不必要な物を見極め、絶対にはずせないポイントを探して正しい場所に配置する。もちろん予想通りに事が進まなかった場合のフォロー案もあらかじめ練っておかなくてはいけない。将棋が上達したのもそれが瞬時にできる頭の回転の速さと、しつこいくらい粘り強い性格のせいだった。
見かけによらぬ手際のよさと頭脳を買われて、小中学校の頃はよく学級委員やイベントの世話係を任されていたものだ。
あれこれと考えをめぐらせていると、知らず知らずのうちに遠足の前日のような気分になってくる。
アレとアレとアレは必要だけど、でもアレを鞄に入れると荷物が大きくなりすぎて怪しまれそうだ。よく考えなくちゃ。監禁されたことがわかってしまうようなパソコンの履歴や、エッチなURLは全部消して……ああ、それに家族にも余計な心配をかけないようにしておかないと。いつかは警察に届けを出されてしまうだろうけど、この監禁ゲームの展開が読めるまで、少なくとも一週間くらいは騒ぎを大きくしたくない。
とにかく、すべきことは山ほどあるのだ。
まゆりはまず「掲示板の件、たぶんうまく罠を仕掛けられたと思います」とメッセンジャーで藤原に報告をした。すると待ち構えていたようにすぐに応答があった。
藤原は大喜びでひとしきりはしゃいだ後、
「用意するものがあったらいつでも連絡して。スタンガンでもセクシー下着でも、今アキバで揃わないものなんてないんだからさ!」
と言ってくれた。頼もしい。スタンガンやセクシー下着は必要ないけど、彼にはいろいろと手伝ってもらいたいことがある。
必要だと思われるいくつかの物を調達してくれるよう頼み、それから藤原にやり方を教わりながらパソコンの履歴を綺麗に消した。
首尾よく監禁されてからのことも相談した。せめて一週間は捜索願いを出されたくないというまゆりに、藤原は「だったら旅行にでも行ってるってことにすればどう?」とさらりと言った。
繭玉:えー、そんなんじゃお父さんもお母さんも納得しないと思う。私ひきこもりの問題児だし。
王将少年:ひきこもりだからいいんだよ。繭さんが「気分転換に一週間旅行してくる」って言えば案外喜ぶんじゃないの? 田舎にいるから電波が悪いとかなんとか言って、時々携帯メールでもしとけば平気平気。
繭玉:監禁されてるのにメールなんて絶対無理ですよ。
王将少年:あ、大丈夫。それは僕がやっとくから。
繭玉:でも私のアドレスと違うし……。
王将少年:今は他人のアドレスになりすませちゃう便利なソフトがあるんだよ。ふふふ、任せなさいって!
そんな簡単なことでいいのだろうかと一抹の不安を覚えたもの、他にいい方法も浮かばないので自信満々の藤原に任せることにした。まあ、それくらいのリスクは負わなくちゃ安楽な新生活を手に入れることなんてできやしないだろう。それに、藤原の勝負強さには一目置いている。
翌日には、ここ数カ月開けることすらなかったクローゼットから星涼学園の冬服と紺色のダッフルコート、そして学校指定の鞄を取り出した。掲示板に出ていた女子高生だと一目でわかるよう、深夜の公園にはこの制服を来て行かなくてはならない。
藤原も、拉致されるには最初のインパクトが勝負だと言っていた。星涼学園にはほんの数カ月しか通っておらずあまりいい思い出がなかったが、うまく事を運ぶためにはこの制服が大きな武器になるのだ。
久しぶりにクローゼットから引っ張り出したので制服は少しナフタリン臭い。仕方がないので慌ててファブリーズする。入学以来ほとんど使っていないせいで鞄が新品同様なのと、ひきこもり生活で少し太ってスカートのホックが止まらなくなったのも気になったが、これはどうにもならないので目をつぶることにした。
久しぶりに制服を来て鏡の前に立ってみると、そこには入学式の写真と寸分違わない少女がいた。ほとんど外に出ないせいで肌は以前よりさらに白くなり、つややかな髪はしばらく切っていないために背中まで伸びて、まさに美少女という感じだ。
しかし、まゆりの心にはまだ不安がある。それほど悪くないと思うけど、これで本当に大丈夫なのだろうか。タナベはこんな子供っぽい女の子に欲情してくれるのだろうか。
さらに、もう一つ心配なことがあった。
それは、自分の体にはちゃんと女としての魅力が備わっているのかということである。
まゆりはこれまで、自分の全裸をしっかりと見たことがない。今どきの女子高生なら、鏡張りのラブホテルかなんかで男とまぐわう自分を見ることくらい日常茶飯事なのだろうが、彼女はもう何年も自分だけの世界で暮らしている。第三者の目を気にする必要などなかったのだから仕方がない。
もちろん、自分のアソコを鏡で見るなんてもってのほかだった。でも、思い通りに事が進めば、そう遠くない将来、自分のその部分は見知らぬ男の目に触れるのである。
まゆりは決心したように制服を脱ぎ、下着姿になった。下着はレースがほんの少しだけついた白の上下だ。藤原からしつこいほど「ロリコンを手玉にとりたいなら白の木綿じゃなきゃダメだ!」と言われていたけれど、そんな忠告をされるまでもなく元から派手な色の下着など持ってはいない。
誰にも会わず家にひきこもってはいても体は発育していく。身長や幼い顔つきは以前のままだったが、ブラジャーのサイズはDカップ、童顔に似合わずなかなかのボリュームに成長していた。ウエストは姉の富子に比べるとやや寸胴だったがそれなりのくびれはあったし、若いからかお腹も出ていない。何よりも、白くなめらかな肌は思わず触れたくなるような極上の質感だ。
食い入るように鏡の中を見つめていたまゆりは、やがて床に座りパンティをおろすと、鏡の前でおずおずと両足をM字に開いた。
――やだ、何これ……?
白い太股の中央に不恰好な毛に囲まれた部分があり、その奥で生々しいピンク色の肉がヌメヌメと濡れて光っている。まゆりはショックで思わず眉をしかめた。女の人の性器ってこんなにグロテスクなものなの? それとも私のが特別なの?
まゆりのそこは普通の女の子に比べても色素の沈着も薄く、少女のような可愛らしい佇まいだったが、彼女の目には卑猥で汚れたものに見えた。男の人は本当にこんなものを見て興奮したり、喜んで舐めたりしてるのかしら。信じられない。
もっとじっくり観察しようと鏡のすぐ前にアソコを近づけると、部屋が寒いせいだろうか、その部分はまるで呼吸でもしているかのように白く曇った。
生きてるみたい……。じっと見つめるとその不思議な生き物は物欲しげにヒクヒクと蠢いた。
「まゆりちゃーん!」
その時、部屋の外からそう呼ぶ声が聞こえた。甥っ子の勇樹だ。一気に現実に引き戻されたまゆりは大慌てでパンティを穿き、ベッドの上に放り出してあったピンクのジャージをすっぽりとかぶった。
「な、なあに?」
「プリン貰ったからおいでよ。一緒に食べよう」
部屋に入って来られてはたまらないと思い急いで居間に行くと、富子とその彼氏がいた。ダイニングテーブルの上には近所の菓子屋のプリンが入った箱が置かれており、勇樹は「どの味にしようかなあ」と箱の中を覗いている。まゆりに気づいた富子は、誇らしげに言った。
「彼が買ってきてくれたの。美味しそうでしょ? あんたの分もあるのよ」
「彼が買ってきてくれたの」が聞いて呆れる。富子の彼氏は手土産を持ってくるような気のきく人間ではない。ケチで、ちょっとした買い物を頼まれても必ず代金を請求するような男だ。このプリンを買ったお金だってどうせ富子の財布から出てるに決まっている。たぶん、この間せびっていた80万をまんまと引き出すのに成功したのだろう。
たったプリン6個でご機嫌取りができるなら安いもんだわ。心の中でそう毒づくまゆりをよそに、富子は今度は自分の前に置いてある小さな熊のぬいぐるみを自慢し始めた。
「ほら見て。これも彼からのプレゼント。可愛いでしょう?」
まゆりは小さくため息をつく。そのぬいぐるみは若い子の間では人気のあるキャラクターだけれど、スーパーのおもちゃ売り場に行けば千円ほどで買える安物だ。いや、うまくすれば200円のUFOキャッチャーでだって手に入る。
いつもだったらそう思っても波風を立てたくないから黙っているのだが、今日はなんとなくイタズラ心が湧き上がってきて、つい余計な言葉が口をついて出てしまった。数日後にはもうこんな茶番に付き合わなくてもよくなるんだと思うと、気分が解放されたのかもしれない。
「ふうん、私も欲しいなあ。千円渡すから買ってきてくれませんか?」
それを聞くと、さっさとプリンを食べ終わり、つまらなさそうにタバコを吸っていた彼氏の顔色が急に変わった。
「性格の悪い女だな、そんなふうだから学校でイジメられるんだよ! そのまま一生ひきこもってりゃいいだろ!」
「イジメられっ子」「ひきこもり」という言葉は、現実を忘れて浮かれ気分になっていたまゆりの心に突き刺さり、居間は一気に重苦しい空気に包まれた。
男は真っ赤な顔で椅子を蹴飛ばすと、針のような捨て台詞を残して居間を出て行った。彼氏と一緒になって怒るかと思った富子も、何も言わずそのまま黙り込んでしまった。
どうしてこんなふうになっちゃうんだろう。お姉ちゃんのことが嫌いなわけじゃない。ただ自分にはないバカがつくほどの無邪気さを見ていると、どうしようもなくイライラするだけなのだ。
最後の数日くらい笑って過ごしたかったのに。軽口を後悔したけれど、後の祭りだった。
次の日の夕方、藤原から届いた荷物を確認しながら幾通りもの監禁パターンをシミュレーションしていると、勇樹が部屋にやってきて、昨日男が買ってきたものと同じぬいぐるみをくれた。
「ママからプレゼント。さっき2人で夕飯の買い物に行ったとき駅前のスーパーで買ってきたの」
ぬいぐるみには、980円という値札がついたままになっている。
――お姉ちゃんらしいわ。
なんだかんだ言いながらも妹のことを心配しているのだ。
まゆりは枕元に置いた学生鞄に、そっとそのぬいぐるみを付けた。作戦決行の日はいよいよ明日に迫っていた。
(続く)
関連記事
赤裸々自慰行為宣言 遠藤遊佐のオナニー平和主義!

(C)花津ハナヨ
遠藤遊佐 AVとオナニーをこよなく愛する三十路独身女子。一昨年までは職業欄に「ニート」と記入しておりましたが、政府が定めた規定値(16歳から34歳までの無職者)から外れてしまったため、しぶしぶフリーターとなる。AV好きが昂じて最近はAV誌でレビューなどもさせていただいております。好きなものはビールと甘いものと脂身。性感帯はデカ乳首。将来の夢は長生き。
遠藤遊佐ブログ=「エヴィサン。」

ナナタ イラストレーター兼和菓子屋兼主婦。好きな和菓子は麩饅頭。嫌いな家事は掃除。
もっぱらの悩みは家が倒壊しそうなこと。
ナナタ個人サイト=「769」
10.10.09更新 |
WEBスナイパー
>
監禁志願アリス
| |
| |
































