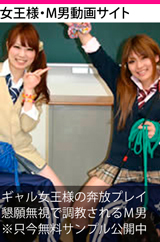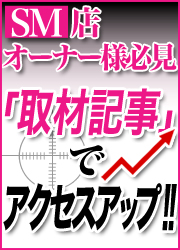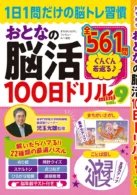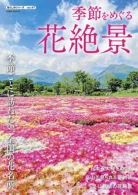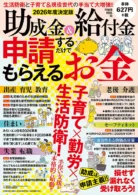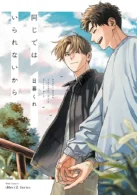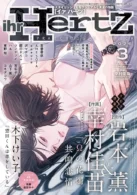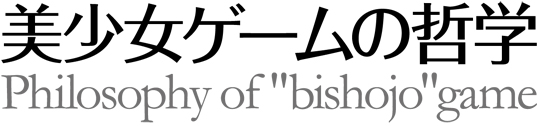
Criticism series by Murakami Yuichi;Philosophy of "bishojo" game
連載「美少女ゲームの哲学」
第六章 ノベルゲームにとって進化とは何か【5】様々なメディアミックスによってコンテンツが生まれている昨今、改めて注目されている作品たちがある。美少女ゲーム。識者によってすでに臨界点さえ指摘された、かつて可能性に満ちていた旧態のメディア作品。だがそうした認識は変わらないままなのか。傍流による結実がなければ光は当たらないのか。そもそも我々は美少女ゲームをどれほど理解しているのか――。巨大な風景の歴史と可能性をいま一度検証する、村上裕一氏の批評シリーズ連載。
『月姫』に見られたような方向性――即ち、多様な物語空間への志向性と、残酷さを背景にした二次創作への希求――は、次回作となる『Fate/stay night』(TYPE-MOON, 2004)でよりはっきりとした形で現われたと言うことができるだろう。
簡単に物語の内容を説明すると、これは、現代の日本を舞台に、魔術師たちが「聖杯」を争って戦う様子を描いた物語だ。魔術師たちは戦いのパートナーとして各々にサーヴァントと呼ばれる存在を召喚する。サーヴァントは神話に登場するような英雄たちである。魔術師は英雄とタッグを組んで、何でも願いを叶えるという聖杯を奪い合うのだ。
ではまず、この作品はどのように多様性を示しているのか。既に述べたように、この作品では、古今東西の英雄が召喚されて入り乱れる。たとえば最古の英雄と呼ばれるギルガメッシュや、神話の英雄ヘラクレスが登場する。そこまで古びていなくとも、いわゆる逸話の登場人物としてのアーサー王が出てくるし、他方で逸話どころかある種の都市伝説とでも言える佐々木小次郎のような(※102)、風説的であるがゆえに神話的であるような人物が同時に並び立つ。最終的には、即ち奈須きのこ独自の世界観において独自に育まれて英雄化したような人物が登場するに至る。ここにおいては、時間軸上の区別がないのに留まらず、お話の性質の区別すらもない。神話も歴史も――そして手製のフィクションまでもがまさにクロスオーバーしており、これは「なんでもあり」の世界の典型だと言うことができる(※104)。
このように多様性を内在した世界観はどのように成立しているか。ここには二つの水準がある。一つはむろん、オールスター的でファンディスク的な発想である。たとえば死者の世界では、死者であるという共通性によって色々な人物が同居している、という考え方がある。ということは、歴史上の人物は死者であるからみなそこにいる。彼らは、生前の歴史においては生きた時代が大きく異なるにもかかわらず、何食わぬ顔で横に並んでいる。これは北欧神話におけるヴァルハラの発想だ(※105)。いちいち列挙はしないが、こういうモチーフをそのまま描いた同人誌も多く存在していた。
こういう発想は現在の唯一性に支えられている。過去や未来には段階がある。年表や地図を使ってある種の座標指定を行なうこともできるだろう。しかし、「いま・ここ」であることはそういった相対的評価とは全く関わりがない。
作品中では、聖杯の機能と、それをめぐる陰謀という形で、現代日本を舞台にすることの理由が語られるが、そもそもその設定それ自体が「いま・ここ」の絶対的唯一性を担保するものとして用いられている。というより、現代に「なんでもあり」を持ち込む多くの作品の背景に見えない形でヴァルハラ的論理があった、と見るべきだろう。
これはもう一つの方向性の問題と深く関係している。多様性というものは、ある種の二次創作の欲望と同期している。『月姫』の場合、さつきの例に典型的であったように、非常に凄惨なエピソードが存在感を持っていた。その凄惨さゆえに、どうにかしてやりたい、どうにかできなかったのか、というような気持ちがキャラクターへの感情移入の駆動因となっていく。『Fate』は、この駆動のメカニズムがそのまま物語化されたようなところがある。
聖杯は何でも願いを叶えることができる。だから魔術師たちがこれを狙っていることは既に述べたが、実際には、彼ら彼女らによって呼び出されるサーヴァントたちもこれに漏れるものではない。
特に典型的なのはセイバーである。彼女はメインヒロイン格の登場人物であると同時に主人公のサーヴァントであり、その正体はアーサー王である。彼女は高潔な王政を敷こうと努力したのだが、その労苦が全て裏目に出てしまい、家族や国民に見放されしまうというような顛末に直面していた(※106)。従って、その苦境を打破し、国民を正しく導きたいという強い欲望があった。それは、やり直したいという強烈な後悔であると言ってよい。
選択肢を選び直したいというこの欲望は非常に美少女ゲーム的である。『YU-NO』がそうであったように、批評的な美少女ゲームは二次創作を内面化しているところがある。『Fate』は、システム面においてはそこまで込み入ったことをやっているわけではない。それどころか、本稿は『Fate』がさも多様性に満ち溢れたゲームであるかのように言っているが、その最も分かりやすい多様性であるところのマルチエンディング性に関しては、ほとんど無いと言っていい(※107)。にもかかわらず本作が多様であるというのは、モチーフの水準での多様性と、その多様性がいかなる感情に基礎づけられているか、という内在的考察に富んでいるからである。
文=村上裕一
※103 佐々木小次郎も『Fate』ではいささか特殊な役回りをしている。宮本武蔵との兼ね合いで有名を誇る彼であるが、調べてみると出自といい名前といい不確かなことが多く、『Fate』においても一種の謎の人物として取り扱われている。そのせいか、登場の仕方も普通の英雄=サーヴァントではなく、キャスターのクラスのサーヴァントが(自分がサーヴァントであるにもかかわらず)魔法の力で召還した存在として現われる。つまり、彼は『Fate』においてもかりそめの人物なのである。もっとも、元を正せばサーヴァントなどみな仮初の人物だとも言えるが……。
※104 この「なんでもあり」感は、『Fate』という作品にとって本質的である。たとえば、主人公である衛宮士郎の持つ能力がそのようなものだ。彼が戦闘において用いる能力――というより魔法――は「無限の剣製」と呼ばれている。自分が見たことのある全ての剣を内包した世界を召喚することで、それらの武器を自由自在に扱えるというものだ。実態としてはむしろ、自分のテリトリーの中に周りの人たちを引きずり込む能力だと考えたほうが分かりやすいかもしれない。これは、見た目の説明よりも遥かに強力な能力である。というのも、剣とはいったものの、いわゆる伝説の武器がひしめいており、一つ一つが強力な破壊力を秘めているからだ。しかも、見たことさえあれば、微妙に劣化するとはいえ、ほとんど同じものをコピーして所蔵することができるなど、反則的な機能を持っている。
このような能力を複数の登場人物が備えている。たとえば、実質的なボスキャラであるギルガメッシュの持つ「王の財宝」がそれだ。衛宮の能力とは異なり、彼は最古の英雄であるという謂われから、あらゆる伝説のアイテム――の起源にあたる財宝を貯蔵していることになっているのだ。またスピンオフ作品で活躍する人物だが、征服王イスカンダル(『Fate/Zero』)などは英雄たちに慕われた英雄ということで、英雄の軍団を召喚する能力を備えている。
むろん武器だけで言えば、エクスカリバーのような超有名かつ一撃必殺のアイテムが登場するため、『Fate』においては量が質に如く、というようなことが一概に言えるわけではない。だが、博物館的な能力に大きな見せ場が与えられているという事実は、本文後述のヴァルハラ的論理とあいまって重要な役割を担う。
※105 実際、作中にもおまけパートでヴァルハラ温泉という名前が存在している。また、そういうコンセプトを持ったヒット作のコンシューマゲームに『ヴァルキリープロファイル』(エニックス, 1999)がある。
※106 セイバーは特殊である。というのも、他の英霊が既に死んだ存在であるのに対し、彼女は死ぬ寸前に世界に召し上げられた状態にあるからだ。つまり、英霊といいながら彼女はまだ生きている。ゆえに、祖国を救いたいという欲望にある種の生々しさが宿っている。英霊は誰しも手に入れられなかったものに対する妄執を抱えているが、セイバーの場合はまだ死にきっていないため、単なる死者の妄執ではなく、それと同時に生者の妄執を重ねているような状態にあった。しかし冷静に考えれば、サーヴァントのマスターたる魔術師がいるというのに、どうやって聖杯を分け合うのかなど、問題がすぐに思い浮かぶのだが、そういうことはお構いなしにだ。実際、聖杯は願いを叶えるアイテムだ、という説明が実は嘘であることが後から判明する。
※107 かつて東浩紀は『美少女ゲームの臨界点』で『Fate』は事実上の一本道のストーリーであると批判したことがある。それは本作が「いま・ここ」に強く縛られているということと無縁ではない。
関連リンク
TYPE-MOON Official Web Site
http://www.typemoon.com/
村上裕一 批評家。デビュー作『ゴーストの条件』(講談社BOX)絶賛発売中!最近の仕事だと『ビジュアルノベルの星霜圏』(BLACKPAST)の責任編集、ユリイカ『総特集†魔法少女まどか☆マギカ』(青土社)に寄稿+インタビュー司会、『メガストア』2月号のタカヒロインタビューなど。もうすぐ出る仕事だと『Gian-ism
Vol.2』(エンターブレイン)で座談会に出席したり司会進行したりなど。またニコニコ動画でロングランのラジオ番組「おばけゴースト」をやっています。http://d.hatena.ne.jp/obakeghost/
WEBスナイパーでは連載「美少女ゲームの哲学」とラジオ番組「村上裕一のゴーストテラス」をやっています。よろしくね!
12.03.20更新 |
WEBスナイパー
>
美少女ゲームの哲学
|
|