法廷ドキュメント 色魔の勲章
大人気のスナイパーアーカイブ・法廷ドキュメント第五回をお届けします。
色魔の誕生
色魔――女を色情でたぶらかしもてあそぶ男。女たらし。
(広辞苑)
善知鳥安高は、第一回めの公判を翌日に控えて流石に眠れぬ夜を迎えた。
起訴の内容は恐喝である。
二ヵ月ほど前にS警察署の係官に令状逮捕された時、容疑は脅迫であった。
逮捕された時の罪名と、起訴された時の罪名が異なることになる。
これは、安高を含めた事件関係者の取調べの結果、取調べ側が当初考えていた容疑事実に変更のあったことを示すものである。
安高はまだ物心のつかない幼少時に、貰い子として善知鳥家に来た。
善知鳥家は、若夫婦が結婚して七年もたつのにまだ一人も子供に恵まれなかったため、遠縁の子供を迎え入れたのだった。
安高の生みの母親は、彼を生んで間もなく死亡した。
実の父親はまだ若く、働かねばならなかったし、安高の面倒を見てくれる祖父母も無かった。
だから、善知鳥家から、安高を養子として貰い受けたい旨の申し出があった時、ためらうことなく受け入れた。
しかし運命とは皮肉なものである。
安高が三歳となった頃、善知鳥家の若夫婦は、次々と子供に恵まれたのである。
ほぼ一年に一人の割合で、安高が小学校に入学する頃には、女の子二人、男の子一人、安高を加えれば合計四人の子供が誕生したのである。
最初の頃は、安高もそれこそ蝶よ花よと大事に育てられた。
だが、長女が生まれ、次に男の子が生まれるに及んで善知鳥家の安高に対する態度は一変した。
こうして安高にとっては冬の季節が衝撃的に訪れたわけである。
もちろん、三、四歳といった幼児期にあった安高にとって、自らの境遇が、悲惨なものとなったなどという判断は到底出来かねるものではあった。
しかしながら、客観的な境遇の変化が、安高の精神形成に多大の、いや、決定的な影響を与えたであろうことは想像するに難くないことである。
実際、子供というのは大抵、大人よりはデリケートな感受性の持ち主であり、少しのことでもその子の精神形成に大きな影響を与えるものである。
そして、いったん受容した心理的障害は、後の人格形成上、陰に日向に顔を出すことになる。
「三つ子の魂百まで」というたとえがあるが、まさにこのようなことを指しているのであろう。
安高は食事時でも、その後の団欒時でも、家族の輪の中には入れず、いつも外側から、幼い妹弟達と大人達との楽しそうな交わりを眺めているだけであった。
無言のうちに流れる拒絶の空気を安高は敏感に感じとり、その空気にあらがうだけの知力も気力もまだ幼い彼には備わってはいなかったのだ。
大人達に逆らわないこと、出来るだけ自分を押さえること、そういった態度をとることを彼は無意識のうちに身につけるようになっていった。
安高は、善知鳥家での愛情に対する飢餓感を埋め合わせるためであろうか、小学校に入学する二年ほど前から、近所の同年代の女の子、あるいは、一つ二つほど歳上の女の子達との淫靡な遊びを始めるようになった。
俗に言う「お医者さんごっこ」である。
安高に最初にその遊びを教えたのは、彼より一つ年上の女の子だった。
その女の子の家庭は、両親の放縦な性生活の結果を露骨に示すかのように子供の数が多く、その子を含めて八人を数えた。
彼女は下から三番めの子だった。
彼女の両親は、どちらも好色な性格で、そんな自らの性格を心の裡にとどめておくほどの教養も全く持たない夫婦だったから、近所の者が遊びに行った時などは、大抵、性や性交を中心にした話を始めて恬として恥じることは無かった。
「タベは、父ちゃんのさつまいもを三本も食べた」
とか、
「あの時のお××こはめったにないほど気持ちが良かった」
とか、そんな露骨な表現を平気で子供達の前でする夫婦であった。
そんな親と毎日を過ごせば、いかに純心な子供達でも、いや純心だからこそ、そういった雰囲気、淫らな環境にたちどころに染まってしまうのも無理のない話であった。
その女の子も性の何たるかを理解し得ないながら、性に対して異常と思えるほどの興味を示す子だった。
大人しい安高は、彼女にとって、格好の実験材料に思えたのだろう。
彼女は彼を誘っては、近くの山の中に入って行き、うつそうたる雑木林の木立の陰に腰を落とし、互いに下半身を曝け出し、安高に命じて、自分の幼い、未成熟の秘裂に、草の葉を丸めて押し込ませたり、安高の大人の小指ほどもない、突起物を揉んだり、相手の菊蕾に指を差し入れ、その指にしみ込んだ汚物の臭いを嗅いだりといったことを、飽きることなく繰り返したのである。
安高も、幼いながら、何か淫靡なことをしているという意識はあり、それ故に、この女の子と二人きりになることが何よりの楽しみであった。
一度、安高は親にこの快楽の現場を目撃され、家に帰ってきたところを激しく叱責されたことがあった。
それは、安高が自分より年下の女の子を雑木林に誘い出し、一歳年上の女の子に手ほどきされた遊びを、そのまま施しているところであった。
女の子は、安高の命ずるまま無言でズロースを下げ、両足を開き、安高にその恥部の全てを曝け出し、草の葉を丸めたものを受け入れていた。
丁度その頃、薪を拾いに来ていた母親に現場を目撃されたのであった。
家に帰って、親に誰とどこで何をしていたのかを問われた安高は、子供心に女の子との遊びは伏せておこうと考え、校庭で砂遊びをしてきたと答えたものである。
すると母親は色をなして怒り、あのようなことをする子は将来ろくでなしにしかなれないと断言し、あまりの叱責の厳しさ故に泣きじゃくる安高に追い打ちをかけるように、
「もっともこの家の跡取りは、お前でなくて良かったよ」
と口をすべらせた。
安高が、自分は両親の本当の子供ではないのではないかとの疑いを持つようになったのはこの頃からである。
こういった家庭の雰囲気の中に、安高は中学校を卒業するまで浸されていた。
その結果、安高の性格は表面的には大人しく、しかし人の目の届かないところでは、それまでの不満を一挙に爆発させるかのごとく荒々しい感情を剥き出しにするといった、二重人格者となっていったのである。
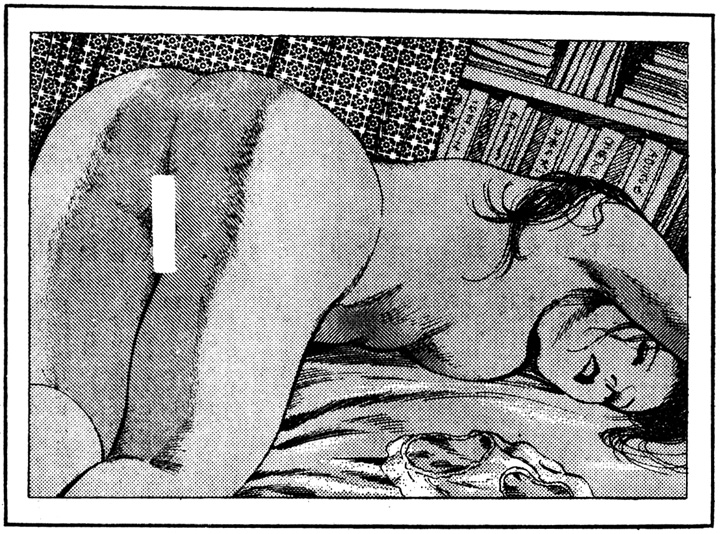
| 法廷ドキュメント 色魔の勲章 第一回 文=法野巌 イラスト=笹沼傑嗣 養子として虐げられた幼年期を過ごした男に宿った性への渇望。 |
 |
大人気のスナイパーアーカイブ・法廷ドキュメント第五回をお届けします。
色魔の誕生
色魔――女を色情でたぶらかしもてあそぶ男。女たらし。
(広辞苑)
善知鳥安高は、第一回めの公判を翌日に控えて流石に眠れぬ夜を迎えた。
起訴の内容は恐喝である。
二ヵ月ほど前にS警察署の係官に令状逮捕された時、容疑は脅迫であった。
逮捕された時の罪名と、起訴された時の罪名が異なることになる。
これは、安高を含めた事件関係者の取調べの結果、取調べ側が当初考えていた容疑事実に変更のあったことを示すものである。
安高はまだ物心のつかない幼少時に、貰い子として善知鳥家に来た。
善知鳥家は、若夫婦が結婚して七年もたつのにまだ一人も子供に恵まれなかったため、遠縁の子供を迎え入れたのだった。
安高の生みの母親は、彼を生んで間もなく死亡した。
実の父親はまだ若く、働かねばならなかったし、安高の面倒を見てくれる祖父母も無かった。
だから、善知鳥家から、安高を養子として貰い受けたい旨の申し出があった時、ためらうことなく受け入れた。
しかし運命とは皮肉なものである。
安高が三歳となった頃、善知鳥家の若夫婦は、次々と子供に恵まれたのである。
ほぼ一年に一人の割合で、安高が小学校に入学する頃には、女の子二人、男の子一人、安高を加えれば合計四人の子供が誕生したのである。
最初の頃は、安高もそれこそ蝶よ花よと大事に育てられた。
だが、長女が生まれ、次に男の子が生まれるに及んで善知鳥家の安高に対する態度は一変した。
こうして安高にとっては冬の季節が衝撃的に訪れたわけである。
もちろん、三、四歳といった幼児期にあった安高にとって、自らの境遇が、悲惨なものとなったなどという判断は到底出来かねるものではあった。
しかしながら、客観的な境遇の変化が、安高の精神形成に多大の、いや、決定的な影響を与えたであろうことは想像するに難くないことである。
実際、子供というのは大抵、大人よりはデリケートな感受性の持ち主であり、少しのことでもその子の精神形成に大きな影響を与えるものである。
そして、いったん受容した心理的障害は、後の人格形成上、陰に日向に顔を出すことになる。
「三つ子の魂百まで」というたとえがあるが、まさにこのようなことを指しているのであろう。
安高は食事時でも、その後の団欒時でも、家族の輪の中には入れず、いつも外側から、幼い妹弟達と大人達との楽しそうな交わりを眺めているだけであった。
無言のうちに流れる拒絶の空気を安高は敏感に感じとり、その空気にあらがうだけの知力も気力もまだ幼い彼には備わってはいなかったのだ。
大人達に逆らわないこと、出来るだけ自分を押さえること、そういった態度をとることを彼は無意識のうちに身につけるようになっていった。
安高は、善知鳥家での愛情に対する飢餓感を埋め合わせるためであろうか、小学校に入学する二年ほど前から、近所の同年代の女の子、あるいは、一つ二つほど歳上の女の子達との淫靡な遊びを始めるようになった。
俗に言う「お医者さんごっこ」である。
安高に最初にその遊びを教えたのは、彼より一つ年上の女の子だった。
その女の子の家庭は、両親の放縦な性生活の結果を露骨に示すかのように子供の数が多く、その子を含めて八人を数えた。
彼女は下から三番めの子だった。
彼女の両親は、どちらも好色な性格で、そんな自らの性格を心の裡にとどめておくほどの教養も全く持たない夫婦だったから、近所の者が遊びに行った時などは、大抵、性や性交を中心にした話を始めて恬として恥じることは無かった。
「タベは、父ちゃんのさつまいもを三本も食べた」
とか、
「あの時のお××こはめったにないほど気持ちが良かった」
とか、そんな露骨な表現を平気で子供達の前でする夫婦であった。
そんな親と毎日を過ごせば、いかに純心な子供達でも、いや純心だからこそ、そういった雰囲気、淫らな環境にたちどころに染まってしまうのも無理のない話であった。
その女の子も性の何たるかを理解し得ないながら、性に対して異常と思えるほどの興味を示す子だった。
大人しい安高は、彼女にとって、格好の実験材料に思えたのだろう。
彼女は彼を誘っては、近くの山の中に入って行き、うつそうたる雑木林の木立の陰に腰を落とし、互いに下半身を曝け出し、安高に命じて、自分の幼い、未成熟の秘裂に、草の葉を丸めて押し込ませたり、安高の大人の小指ほどもない、突起物を揉んだり、相手の菊蕾に指を差し入れ、その指にしみ込んだ汚物の臭いを嗅いだりといったことを、飽きることなく繰り返したのである。
安高も、幼いながら、何か淫靡なことをしているという意識はあり、それ故に、この女の子と二人きりになることが何よりの楽しみであった。
一度、安高は親にこの快楽の現場を目撃され、家に帰ってきたところを激しく叱責されたことがあった。
それは、安高が自分より年下の女の子を雑木林に誘い出し、一歳年上の女の子に手ほどきされた遊びを、そのまま施しているところであった。
女の子は、安高の命ずるまま無言でズロースを下げ、両足を開き、安高にその恥部の全てを曝け出し、草の葉を丸めたものを受け入れていた。
丁度その頃、薪を拾いに来ていた母親に現場を目撃されたのであった。
家に帰って、親に誰とどこで何をしていたのかを問われた安高は、子供心に女の子との遊びは伏せておこうと考え、校庭で砂遊びをしてきたと答えたものである。
すると母親は色をなして怒り、あのようなことをする子は将来ろくでなしにしかなれないと断言し、あまりの叱責の厳しさ故に泣きじゃくる安高に追い打ちをかけるように、
「もっともこの家の跡取りは、お前でなくて良かったよ」
と口をすべらせた。
安高が、自分は両親の本当の子供ではないのではないかとの疑いを持つようになったのはこの頃からである。
こういった家庭の雰囲気の中に、安高は中学校を卒業するまで浸されていた。
その結果、安高の性格は表面的には大人しく、しかし人の目の届かないところでは、それまでの不満を一挙に爆発させるかのごとく荒々しい感情を剥き出しにするといった、二重人格者となっていったのである。
(続く)
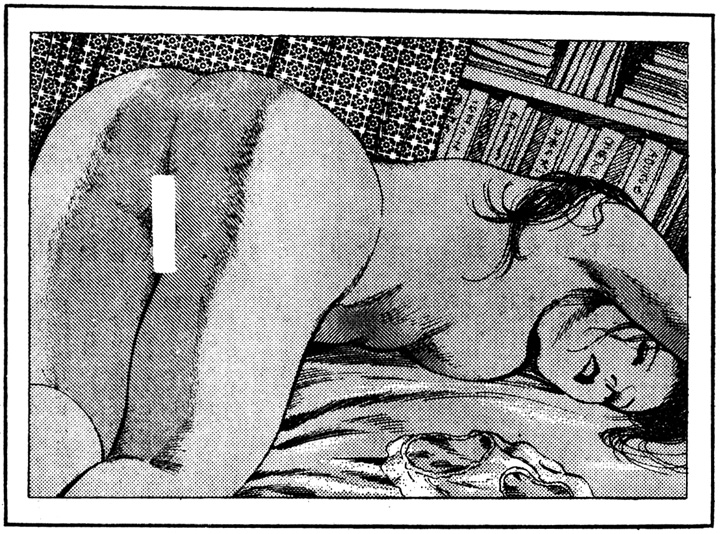
07.07.12更新 |
WEBスナイパー
>
スナイパーアーカイヴス






















