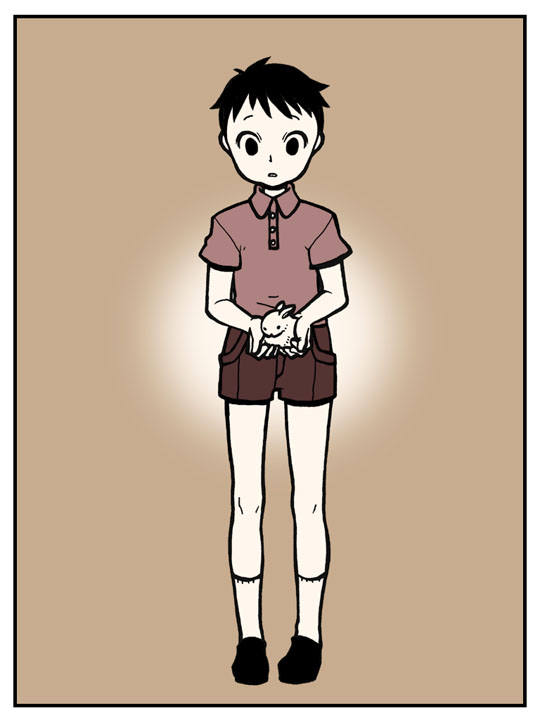
毎週土曜日更新!
Alice who wishes confinement
私の居場所はどこにあるの――女児誘拐の不穏なニュースを観ながら倒錯した欲望に駆られた女子高生が体験する、エロティックでキケンで悩み多き冒険。理想と現実の狭間で揺れ動く乙女心とアブノーマルな性の交点に生まれる現代のロリータ・ファンタジー。オナニーマエストロ遠藤遊佐の作家デビュー作品!!「もしかしたら俺は二重人格なんじゃないだろうか」
まゆりをこの一軒家に監禁しはじめてから、タナベはときどきそう思うようになった。
毎晩リビングで、美少女にエロ本のグラビアみたいなあられもない格好をさせねちねちいたぶる自分と、女子社員といえば50過ぎのおばさんばかりという女っ気のない職場で灰色の作業着に着替え黙々と仕事をする自分。相手が羞恥のあまり涙を浮かべても、ひるむことなくスカートの中に突進していける自分と、後輩社員たちが昨夜した合コンについて「お持ち帰り」だの「ヤリ逃げ」だのと盛り上がっていると、いたたまれなくなってつい席をはずしてしまう自分。どっちが本当の自分なのだろう。
これまでは、そんなふうに深く考えたことはなかった。二回り以上も年の離れた少女にしか性欲を感じない、世間でいうところの“キモいロリコンオヤジ”であることと、20年間無遅刻無欠勤の真面目で小心なサラリーマンであること。おかしなことだが、彼の中でその2つはごく自然に共存していた。たとえ、頭の中は口に出すのもはばかられるような卑猥なプレイでいっぱいだったとしても、インターネット掲示板で同好の士を相手に妄想を語るだけなら誰にも迷惑はかからない。たまに行く女子校生イメクラの女だって、ケチらず湯水のようにオプションをつけてくれるタナベのことを気前のいい上客だと喜んでいるように見える。だったらそれでいいじゃないか。そう思っていた。俺はきちんと自分の責任を果たしたうえで、ひっそりと脳内に棲む美少女とのセックスを楽しんでいる。うん、それでいいじゃないか。誰にも文句を言われる筋合いはない。
しかし、今タナベが自分の欲望を満たすためのオモチャにしているのは、まゆりという生身の少女だ。脳内ではない現実の少女を相手にしているうちに、もう一人の自分もどんどん膨らみ現実のものになっていく。最近では、会社から帰り玄関の鍵を開けた途端、自分勝手でふてぶてしいご主人様へごく自然にシフトチェンジするようになってきていた。これを二重人格と言わずしてなんと言おう。
正直、ご主人様でいるのは楽しかった。20年以上もの間、何度も繰り返し頭の中で思い描いてきた夢が現実になるのだ、楽しくないわけがない。しかも相手は理想の美少女だ。まゆりが恥ずかしい命令に困って泣きそうになるところや、唇をぎゅっと噛んで湧き上がる快感をこらえようとするところを見ていると、どこかのSM小説で見たようないやらしいセリフが次々わいてきた。柔らかく吸いつくような内腿の手触りも、まだちょっとオシッコ臭さが残る愛液の香りも、すべてが妄想よりもはるかに上だった。
タナベは生まれて初めて、自分が“主人公”になったと感じた。
しかし、それでもふと我に返る一瞬はある。これ以上ないというくらい芝居じみたセリフでいたぶったあとや、嫌がる少女をオモチャを使って何度も繰り返しイカせたあと。満足が深いほど逆に気持ちがすっと冷めていくのだ。こういうの、なんていうんだったっけ。あ、そうそう、賢者タイムだ。
――あの子は俺を、どう思っているんだろう。
そう考え出してしまったが最後、恥ずかしさに居ても立ってもいられなくなる。きっと、ひどい奴だと思っているに違いない。あんなに優しかったのに騙されたと思っているかも……。いや、それならまだいい。タナベが一番恐れるのは、すべてを見透かされているんじゃないかということだ。
最初の頃の礼儀正しく小心なタナベと、本性を隠さなくなってからの下衆で暴君なタナベ。彼女は他の誰も知らない両方の顔を知っているのである。
「ふん、カッコつけてたって、本性は妄想癖のある気の小さいロリコンじゃないの。エラそうにご主人様ぶっちゃって、バカみたい」
あの可愛い奴隷が、心の中でそんなふうに考えているとしたら……。考えただけで泣きたくなってしまう。
タナベはふと、小学生の頃、夜店で買ったミニウサギを飼っていたのを思い出した。
両親には内緒で、お年玉の残りを使って購入した。確か数千円だったと思う。
小学校高学年のタナベは、少し内気でプロ野球と少年チャンピオンが好きな一般的な少年だったが、2歳年上の従姉妹に連れられて行った縁日の夜店で、どういうわけかそのウサギから目が離せなくなってしまった。それまで、動物を飼いたいなんて思ったことは一度もなかったのに。ウサギは手のひらに乗るほどの大きさで、生温かくふわふわしていて、驚くほど頼りなかった。
タナベは“うさこ”と名付けたそのウサギを、親にも従姉妹にもクラスの友達にも内緒で近所の廃屋の二階に小さなケージを置いて飼っていた。なぜなら、最初に“うさこ”に目をつけたのは従姉妹のほうだったのだけれど、動物好きでいろんな生き物を飼いたがるくせにすぐに死なせてしまう彼女は、両親にそれを買ってもらえなかったからだ。
「あのウサギ、そんなに可愛くなかったよ」「あんなに小さいんだもん、きっとすぐ死んじゃうよ」そう言って慰めた手前、自分の家で飼うのは気が引けた。
それに、内気で目立たないタナベがそこでミニウサギなんて素晴らしいものを飼っていると知ったら、クラスの子たちはきっとおもしろがって押しかけてくるだろう。両親や従姉妹にバレるのは時間の問題だ。
タナベは、図書館で『かわいいウサギの飼い方』という本を借り、細心の注意を払ってうさこを飼った。しかし、半年ほどでうさこはあっけなく死んでしまった。その年は例年にない猛暑だったから、そのせいかもしれない。
タナベは涙が枯れるほど泣いた後、一人でうさこを廃屋の庭に埋めた。それから大学に進学して家を出るまで、あの廃屋のあった場所には一度も行っていない。
なぜ今、そんなことを思い出すんだろう。
きっと、自分が敷いてやった布団の上で安心しきって眠っているまゆりを見たせいだ。愛らしい寝顔は、誰にも内緒でミニウサギを飼っていたときと同じ高揚感と、同時にうしろめたさも感じさせる。
うさこが死んだとき、タナベ少年は「これでよかったんだろうか」という気持ちに苛まれた。
あの半年間、ミニウサギは確かに自分の生活のすべてだった。親に叱られても学校で嫌なことがあっても、廃屋でふわふわした温かい生き物が待っていると思うだけで世界はバラ色になった。
しかし、うさこは幸せだっただろうかとも思うのだ。あのときタナベにペットショップで買われなかったら。もっと広い場所で大勢の人に可愛がられていたら。きっと寂しい思いをしなくてすんだだろう。もしかしたら、あんなふうにあっさり死ななくてすんだかもしれない。
時間が経つにつれて、うさこのことを少しずつ忘れていくのも、いけないことのような気がして辛かった。自分が忘れたら、そこでうさこの存在はなくなってしまうのに。
もう、あんな気持ちになるのは嫌だ。
本当のことを言わなくてはいけないと思った。相手が何も知らない小さき物だからといって、ごまかしてはならない。
誰に文句を言われなくても、誰が見ているわけじゃなくても、本当に自分を嬉しい気持ちにしてくれるものには、誠実でなくてはいけないのだ。
とにかく、昨日のこと――見知らぬ美少女の代用品にして傷つけたこと――を謝ろう。そして、自分はご主人様なんかじゃない、怒りにかこつけてご主人様になりすましているただのスケベな小心男だと告白しよう。タナベはそう心に決めた。
いつまでも妄想の中のS男ではいられないのだ。
夢を見ていた。
まゆりは、自宅の前でぼんやり突っ立っている。玄関には鍵がかかっており、鍵を忘れた彼女は家に入れない。久しぶりに帰ってきたというのに、家族はどうしたんだろう――。きっと私のことなんてどうでもいいんだろう。お姉ちゃんと甥の勇樹を連れて回転寿司にでも行っているのかもしれない。
気がつけばまゆりは薄汚れたピンクのジャージ姿だ。近所の人が、真っ昼間から寝間着でいる自分を物珍しそうに見る。恥ずかしくてタナベの家に逃げ帰ろうとするけれど、ずっと監禁されていたから家がどこにあるのかさえもわからない。どうしよう、子供みたいに座り込んで泣きたくなる。タナベが自分を探しに来てくれればいいのにと思う。どうしよう、どうしよう……。
目覚めると、眠りについたときと寸分たがわぬポーズでタナベが座っていた。熱は下がったから大丈夫だと言ったのに、ずっと付き添っていてくれたらしい。
外の様子は見えないけれど、夜の気配だ。「今何時ですか」と聞くと「8時だよ」と言う。ウトウトするだけのつもりが4時間も眠っていたらしい。道理で頭がスッキリしている。
幼い勇樹が熱を出したときは、暇なまゆりがキャバクラで働いている姉の富子の代わりに付きっきりで看病をしたものだが、眠っている病人の様子にじっと気を配るのはなかなかに骨が折れる仕事だった。家族でもない、朴訥な中年男が黙って4時間もそれをしてくれていたのかと思うと、少し感動した。
タナベは、「本当は昨日の朝言うつもりだったんだけど」と前置きをし、うつむいたまま訥々と話し始めた。
まゆりを満員電車で会った美少女の代用品にしたのではなく、本当は娘ほどの年のギャル達に痴漢の罪を着せられ金まで奪われたこと。その怒りと恥ずかしさを自分勝手にねじ曲げてまゆりにぶつけたこと。
僕はロリコンの犯罪者なだけじゃない。嘘つきで、そのうえ卑怯者なんだ。君が風呂場の窓から逃げようとしたんじゃないってことも本当は気づいてるのに、そう思い込んでるふりをしてた。そうやって悪い男のふりをしてるほうが楽だったからね。本当にすまない。
「どうして今さら……」
突然の告白に驚いて、まゆりは聞いた。
どうして今さらそんなことを言うの? あともう少し、4月になればこの生活は終わるんでしょう。だったらそれまで黙っていればよかったのに、と。
タナベは「言いたかったからだ」と、やっぱりまゆりの目を見ずに答えた。こんなふうに監禁してひどいことをしておいておかしいかもしれないけど、君はやっぱり僕の宝物なんだ。大事なものに嘘をつくのはよくないだろ?
「だったら、私だって嘘つきです」
え? タナベがようやく顔をあげる。
「どういうことだい?」
「私……私、あなたが思ってるような女子校生じゃないんです」
狐につままれたような顔でぼんやりと見つめられ、まゆりは焦って続ける。
「あの、女子校生は女子校生なんですけど、ちゃんとした女子校生じゃないっていうか……本当のことを言うと登校拒否のひきこもりなんです。一応星涼学園には合格したものの、クラスに馴染めなくていじめられて、もう学校なんて2年も行ってなくて……」
なんちゃって女子校生なんだ、とタナベはちょっと楽しそうに言った。
「あれ、でも制服姿だったよね。塾に行くところだったんじゃ……」
それは……。まゆりは思わず口ごもる。ひきこもりのダメ人間だとは言えても、この監禁が計画的なものだったとまではさすがに言えない。
「実を言うと、ちょっとおかしいところがあるなとは思ってたんだ。いきなりクロロホルム嗅がされてこんなところに拉致されたのに、本気で逃げ出そうとしてなかっただろう? それに、なんとなく寂しそうに見えた」
タナベは深く追及しようとはせず、ゆっくりとそんなふうに言った。昨日までのご主人様口調が嘘のようだ。
着古したスウェット姿に目をやる。トレーナーの裾をズボンにインしているのが、いかにもオヤジくさい。でも、まゆりはなぜだか、そのオヤジくさいスウェット姿に欲情した。くたびれた、でも意外にがっしりとしている胸板のあたりを、触りたいと思った。背中に顔をうずめて、少しクセのある体臭を嗅ぎたいとも思った。
――私、どうしちゃったんだろう。
滞っていたゲームが、また動き出した。
将棋なら、こういう時こそ流れを変えるチャンスだ。どうすれば自分が有利になるよう試合を進められるか、神経を研ぎ澄まし慎重に先を読まなくてはならない。なのに、頭がぼうっとして緻密な思考を重ねることができないのだ。
もう、計算なんてどうだっていい。
まゆりは、勇気を出して、さっきからずっと心にあった言葉をそのまま発してみた。
「あの……今日は何もしなくていいの?」
風邪で熱を出しているからとはいえ、2日間まったくいやらしいことをされないなんて、ここ何週間かで初めてだ。しっかり寝て体力が回復したからだろうか、体の芯が熱く疼いている。
「……大丈夫。今日はおやすみだ」
少女の目が欲望で潤んでいるのに気づかないのだろうか。
余計なことは気にしなくていいから、安心して休みなさい。タナベは静かにそう言うと、まゆりの頭に手を載せ、優しくぽんぽんと叩いた。
(続く)
関連記事
赤裸々自慰行為宣言 遠藤遊佐のオナニー平和主義!
「遠藤遊佐のオナニー平和主義!」連載100回記念スペシャル企画
イラストレーター・ナナタ × オナニーマエストロ・遠藤遊佐 初顔合わせ対談!!

(C)花津ハナヨ
遠藤遊佐 AVとオナニーをこよなく愛する三十路独身女子。一昨年までは職業欄に「ニート」と記入しておりましたが、政府が定めた規定値(16歳から34歳までの無職者)から外れてしまったため、しぶしぶフリーターとなる。AV好きが昂じて最近はAV誌でレビューなどもさせていただいております。好きなものはビールと甘いものと脂身。性感帯はデカ乳首。将来の夢は長生き。
遠藤遊佐ブログ=「エヴィサン。」

ナナタ イラストレーター兼和菓子屋兼主婦。好きな和菓子は麩饅頭。嫌いな家事は掃除。
もっぱらの悩みは家が倒壊しそうなこと。
ナナタ個人サイト=「769」
11.02.19更新 |
WEBスナイパー
>
監禁志願アリス
| |
| |
































