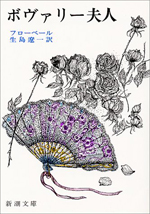WEB SNIPER special contents
特集:セックス表現の現在形2012
対談:村上裕一・佐藤心/萌えとセックスの過去・現在・未来【1】
かつては秘匿されてきた性の営みがメディアと技術の発展で白日の下に晒されている現在、様々なジャンル・作品においてセックスはどのように表現されていくのでしょうか。ゴールデンウィークの特別企画として好評を博したテーマをさらに掘り下げるべく、連載「美少女ゲームの哲学」でお馴染みの批評家・村上裕一氏と、ゲーム『波間の国のファウスト』が好評発売中のシナリオライター・佐藤心氏によるスペシャル対談をお届けします。縦横無尽な対話の先に見えてくるものとはいったい何か......。貴重な思索の記録を4週に分けて掲載!!
村上裕一(以降「村」) 先月、WEBスナイパーではゴールデンウィーク企画として現代のメディアにおける「セックス表現の現在形」を特集しました。今回の対談はそれに連なる形で行なわれるものです。僕は仕事の領域的に、萌えやオタクの文化からそれを考えようと思ったのですが、これは非常に奥行きのある仕事です。そこで、斯界の先輩でもあり、ちょうど発売されたばかりの美少女ゲーム『波間の国のファウスト』(bitterdrop、2012年)のシナリオライターも担当された佐藤心さんをお呼びしまして、対話の形で考えてみようと思いました。
というのは、僕と佐藤さんを比べるだけでも、性表現に対する興味の方向性がすでに大きく違うんですね。例えば僕はあまり男性性と女性性の対立でものを考えないんです。なぜかというと、斎藤環さんに『戦闘美少女の精神分析』(太田出版、2000年)という名著がありますが、そこでは戦闘美少女とはファルスを持った少女だといわれています。僕はこの流れで、キャラクターを一種の性エネルギーの凝集のように考えているんです。萌え文化というのはキャラクターの文化ですから、キャラクターをどう捉えるかで見方が変わってきますよね。
これを俗にいい換えるなら、キャラクターと性というものが密接な関わりを持っている、という話で、それは直感的に多くの人が分かっていることだと思います。例えばコミックマーケットへ行くと並んでいるものの多くがエッチな同人誌ですが、しかしそのネタ元は大部分が一般の作品です。ということは表層的には性描写のない健全な作品の多くが、むしろ性的な読まれ方をしているわけですね。これは私見ですが、むしろそういう見られ方をすること自体が、あるいは今は見られていなくともそういうふうに見られうるという可能性自体が、作品やキャラクターの強度なんだと思います。

『魔法少女まどか☆マギカ 1 』【完全生産限定版】 [Blu-ray] 監督: 新房昭之 発売日: 2011年4月27日 販売元:アニプレックス
こういう社会と文化のミスマッチは本当に頭を悩ます問題ですが、とにかく僕が思っているのはキャラクターというのが本質的に性的だということです。実際、『魔法少女☆まどかマギカ』(2011年)などもそういうふうに読めました。しかし、逆にいえば、僕のこの考え方というのはとても局地的、というか非主流といってもよくて、むしろ本流なのはジェンダーを絡めたセクシュアリティに関する思考のはずなんですね。それを重要な問題として受け止めていらっしゃるのが、僕の見るところ佐藤心という書き手です。
佐藤心(以降「佐」) なるほど。確かに村上さんよりも僕のほうが美少女キャラや、あるいは美少女キャラと、自分を含めた男性オタクがどういう関係にあるかということに関心があるし、執着していたといえるでしょうね。

『GUNSLINGER GIRL Blu-ray BOX』 監督: 浅香守生 発売日:2009年10月23日 販売元:メディアファクトリー
佐 僕がまだ評論を書いていた2000年代前半の話ですね。萌えブームが起き、アキバ系文化に社会的認知がされて以降、急速に見えなくなった視点ですが、当時は、男性オタクが美少女キャラクターを性的に搾取しているのではないかというフェミニズム的批判が根強く存在していました。そのときに『GUNSLINGER GIRL』は、女性に対する搾取、あるいは暴力の最悪の形と見ることもできました。生きる意味も希望も失い傷ついた少女がサイボーグ化され、喪失の穴埋めとして殺人兵器としての使命や充実した生が与えられるわけですから。非実在青少年の権利問題とも関わる視点ですし、いつまた浮上するか分からない規制ロジックです。
とはいえ『GUNSLINGER GIRL』の義体化された少女たちが、男性オタクの性的な対象にされるだけの存在かといえば、僕にはそうは見えなかった。誤解を恐れずにいうと、僕の目には彼女たちが自分たちの写し絵に映りました。表出しがたいトラウマに傷つき、生きる意味も希望もないこの社会で人はどうやったら幸せになれるのか。その問いの答えが、薬物による記憶喪失状態と、殺人兵器としての使命、フラテッロとの疑似恋愛にあるように思えたのです。美少女を対象化するだけでなく、彼女たちを内面化し、自分を女の子だ、女の子が自分だと思ってしまうような欲望なり感性に、フェミニズム的批判は届いていません。くわえてこうした欲望は近年の男の娘ブームや女装といったトピックとも密接に結びついているわけで、今日の対談においても重要なテーマになってくるのかなと思います。
村 ここが凄く分かりやすい。つまり佐藤さんは、女装や変身ということを凄く重要な要素として考えている。考えるための方法だとすらいってもいいのではないでしょうか。この点では仮面ライダーを重要視していた宇野常寛さんとも発想が通ずると思います。他方で僕はあまりそういう発想がないんですよ。もちろん理性のレベルでは把握しているんですが、OSのレベルでそういう方向性に行かないんです。そんな僕がこういう変身的欲望を捉えるために設定した術語が「人形」ですね。『GUNSLINGER GIRL』でも少女たちが義体人形なんて呼ばれ方をします。むろん人形というのは批判対象で、少女たちは人形ではない。
佐 キャラクターを外側から見るか、内側に入り込んで見るかの違いですね。前者の理論的突きつめはまさに村上さんの独壇場といったところですが、僕なんかは「人形」といわれるとそこに自分の空虚さを見てしまうきらいがある。だから『ゴーストの条件』(講談社、2011年)を読むと、とりわけ『Fate/Stay night』(TYPE-MOON、2004年)論のくだりには、人形である士郎の内側に入り込んでいる村上さんの影を感じとったりもするわけですが(笑)。
他方、話を戻すと、男性オタクとキャラクターとしての少女との内面的関わりの歴史はそれなりに長いものがあります。少女マンガを読む男性がその典型で、少女的な内面なるものをメディアを通じて男性が獲得し、それによって人格形成が行なわれるパターン。評論家でいうと新人類世代の宮台真司さんが有名ですし、エロマンガの分析においても、犯されている女の子のほうにオタクの男性は感情移入するというタイプの議論が説得力をもってなされてきました。男の娘や女装はその延長線上にある現象に思えます。
村 これは本当に古くからある議論でした。僕に引きつけていい換えると、美少女ゲームをやるときにプレイヤーがどういうモチベーションでプレイするのか、という問題ですね。そこでいわれてきたのは「ヒロインを救いたい」か、「ヒロインになりたい」の二項対立でした。ヒロインになりたいという欲望は僕には無縁だったんです。
佐 美少女ゲームの場合は、やや事情が異なるのではないでしょうか。あれは否応なく男性の視点キャラクターにのっとって物語を読み進めていくメディアだから、コミュニケーション対象となる女の子との偏差がむしろ際だってくる。ただ多くの美少女ゲームにおいて、主人公自身に動機や目的は原理的にはなくてもよい。ヒロインの抱えている問題を自分のものとして取り込み、それをテコにパートナーシップを築いていくものではある。乱暴を承知でいえば、美少女ゲームはヒロインを救うことを目的とした物語メディアなので。
村 もちろんそれはそうなんですよね。僕は美少女ゲームに関してはこれをヒロインの欲望の産物だと考えていて、それは「美少女ゲームの哲学」なんかも参照頂きたいんですが(笑)、そうなると男性主人公っていうのはヒロインの欲望の鏡になってくるんですよね。それこそ『Fate/Stay night』の衛宮士郎などは、ヒロインどころかあらゆる人の鏡になっちゃいますし。
佐 実社会で男性に求められるのとはいささか異なる人格モデルが描かれていったわけですね。ひらたくいえば、社会における自己実現というミッションがヒロインを媒介とすることによってのみ成り立つ。むろんその先に自立した主体なるものがあってもよいのですが、僕の目に映ったのはむしろ、カネを稼ぎ、実社会で出世をはかる上昇志向とは真逆の、ヒロインの救済に全人生を賭けるかのような、きわめて脆弱な、あるいは縮減された主体のあり方だったわけですが。
村 2000年前後に流行した泣きゲー(※1)特有の傾向なのかもしれませんが、表面的に見れば、確かに自分よりも弱いキャラクターを救うという物語の傾向があった。それは、こちらが求めたものなのではないか、という議論もありました。
佐 表面的に見ればそうでしょうね。しかしそこで描かれていたヒロインの「弱さ」は、カネと地位を手に入れるハイスペックな能力をもった「強い」人間ならば救えるかといったらそうではない、逆に手に余る類の弱さだった。裏を返せば、そこで描かれる救いは、ヒロインを救うことで自分も救われるといった、どこか宗教的ニュアンスをもった救済だったわけで、この脱世俗的あり方はいまだに興味深いものとして残っているのかもしれません。
その一方、通底する特徴は別に見いだせるでしょう。すなわち、オタクが好んだ想像力とは、男性性を弱くするように働き、同時に女性優位に働くものだったということです。オタクの欲望なるものは非常にご都合主義であり、それは過去から今に至ってもほとんど変わらないものだけど、しかしそこには独特の捻れが刻まれている。自ら好んで弱さを志向するとは、客観的に見ればとても不思議な話です。
■欲望のパースペクティブ
村 ところで女装というキーワードが出ましたけど、佐藤さんはコミケでもよく女装系のコスプレをしていらっしゃるようですが。
佐 急にボールが来ました(笑)。まじめに答えておくと、ちゃんと女装をするのって大変なんですよ。事前にダイエットとかしなければいけないし。仕事そっちのけで趣味に没頭できる状況でもないから、仮にやりたくてももうできないかもしれません。ただ、コミケのコスプレなんかも含めて、ますます賑やかになってはいますよね。
村 格闘ゲームのキャラクターのコスプレの人なんか本当に凄いんですよね。僕が見たことのある例だと、上半身裸なんですが、腹筋がバキバキに割れていて、すわ本物か!と思ったことがあります。本当に蒙を啓かされたんですが、コスプレというのはもはや単なる仮装ではなくて、極まっていくと人体や精神の改造に至るんだと知らされました。だから、これは直接は関係ないんですが、格闘家の長島☆自演乙☆雄一郎が熱心なレイヤーだというのには不思議な納得を得ましたね。格闘家というのは肉体改造が必要な職業の代表例でしょう。
肉体改造とかいうと拒否反応を示されるかもしれませんが、これは要はライフハックなどと同じ発想なのだと思います。変身とか改造を抽象的にいい換えるとハッキングなんです。宇野さんの『ゼロ年代の想像力』(早川書房、2006年)はいわば自分探しの批判として自己ハッキングを勧めている本です。本当の自分なんていないんだからコミュニティに合わせて変身せよ、ということですね。そう考えると『リトル・ピープルの時代』(幻冬舎、2011年)のハッキング論も、その延長線上のものとして見えてきますね。レイヤー的な想像力が強まっているんだとしたら、恐らくこういう時代趨勢との連動があるのでしょう。
佐 ハッキングか......能動的な話ですね。村上さんは変身とかコスプレに関心はあったりするんでしょうか?
村 僕は自分が誰かキャラクターに成り代わろうという気持ちはさらさら起きないんですよ。これは分かりやすくて、簡単にいえば僕が佐藤心になる、みたいな話だからですね。僕は佐藤さんがいる世界で佐藤さんとお話がしたいだけであって、佐藤さんの存在の場所を奪おうなんて全く考えていないわけです。そしてそのような形で世界に存在する様々なキャラクターとの付き合い方を考えている。もちろん、例えば『化物語』(講談社、2006年)のコスをすることで『化物語』の世界に入門した気がする、というような発想があるのだとすれば凄く親和的ではあるのですが。
佐 なんとなく論点のずれが分かってきました。僕は別に成り代わりたいんじゃないんですよ。ハッキングとも違って、最初の一撃はもっと受動的なんです。村上さんふうにいうなら、一番最初に「ゴースト」が入ってきてしまう感じなんです。例えば僕、『GUNSLINGER GIRL』を読んだ時に、トリエラは俺だなって思ったんですよ。義体少女たちの中で彼女だけが現状を肯定できず、義体としての生に懐疑がある。そういう内面描写もあったせいでこの娘は自分だ。あとはフィジカルだけだなと(笑)。
村 これは凄く面白い話ですよね。似たような有名な逸話がフランス文学者のフローベールにあります。彼は『ボヴァリー夫人』という世紀的な傑作を書いたのですが、それについて「マダム・ボヴァリーは私だ」という発言を残しているんですね。
これは実は非常に象徴的な話なのではないかと思うんです。特にフローベールの場合は、「私だ」といってボヴァリー夫人の話を書いているわけですから、ほとんど降霊術みたいなものなんですよね。こういう成り代わりの力、共感性みたいなものこそが近代的な発想のように感じます。特にフローベールは写実主義を確立させた作家だと考えられているわけですが、普通に考えれば写実なんて対象となる現実がなければできませんよね。ところが、大塚英志=東浩紀的なラインにおける写実主義――というかリアリズムは、むしろ別なロジックで構成された別の自然を写生しているのだ、という話(※2)になっていました(フローベールにしてもヌーヴェル・クリティーク以後においてはそういうふうにも読まれているはずです)。その極端がデータベース的な絵柄、トリエラでもいいんですが、分かりやすいところでは初音ミクに対する感情移入や没入だったりするわけですよね。しかし、単なる絵だろといわれればそこまでのところはあって、これは確かに従来の方法では不可能な感情移入であり、なるほどポストモダンだなと。
佐 フローベール的な没入、同一化能力みたいなものは、僕の場合、シナリオを書くときに発揮されているなと確かに思います。トリエラのときも、その能力がたまたま消費の局面で働いたのだといえなくもない。
村 こういういい方をすると露悪的ですが、例えば芸能人や俳優、リアルな有名人の情報に際して、そう思うことはないんですか。
佐 内面を操作するという形ではできると思いますが、没入の深さでいうと、実写より絵のほうがより深く入り込みやすいようには感じます。それに僕の場合、ビジュアルに配置されている「かっちりとしたスーツを着こなす」的な男性記号がフックになっているのはあるかなと。トリエラ以外に「この娘は俺だ」感が強かったキャラに御坂美琴というのがいるわけですが、あれはどういうわけか、『とある科学の超電磁砲』(2007年、メディアワークス)第一巻を手に取った瞬間、稲妻に打たれるような衝撃が走って......。
村 (笑)。
佐 『とある魔術の禁書目録』(メディアワークス、2004年)ではいわゆるツンデレ中学生ですし、特にうんともすんともなかったのですが、百合スピンオフ作品ではぐっときました。女性キャラの中に置かれた途端、ボーイッシュというか、がさつでさばけた性格が前面に出るようになったからだと自分なりに分析はできますが。
けれどそこではっきりしているのは、僕は御坂美琴が好きなのではないんだと思います。御坂美琴を愛したいとか、御坂美琴を愛するがゆえに一つになりたい、そんな欲望ではなくて、まさにそこに自分を見たという形。中高生の頃の自分を召喚すれば、メンタルどころかフィジカルもシュッとはまるだろうみたいな感覚が働いたというか。
村 一種の多重人格のような感性が、目の前のキャラクターとの繋がりを保っている、という感じでしょうか。
佐 どうなんでしょう。ひとつには明らかにナルシシズムの一種なのだと思いますけど。私事で恐縮ですが、僕の中には、順調に社会化しつつあった自分が、ある時点でものの見事に去勢に失敗した、というトラウマ的な感覚があって。その失敗した何かが、残留物のように自分の中に漂っていて、それがあるタイプの美少女キャラクターと化学反応を起こして結びついてしまう。あえて説明すればそんな感じかしら。
村 去勢されてない感覚というのは面白いですね。精神分析では去勢によって社会化されるという見立てがあります。言語を内面化することによって社会的な役割を担えるようになるということですが、去勢というのはもちろんペニスを切り取るとかそういう話ではなくて、去勢コンプレックスによって性を受け入れていく過程のことです。ファルスはそこで母親と子どもを切断するわけですが、去勢をしていないがゆえに女性のキャラクターとしばしば同一化できるというか、成り代われるのかもしれません。その場合重要なのは、対象がフィクションの住人だということですが。
佐 フィクションであることによって、ある種の全能性が獲得されるというのは間違いなくあるでしょう。しかし虚構の少女性を内面化した、あるいはトリエラなり、御坂美琴なりのゴーストに浸食された「私」のあり方というのは、全能的な願望を裏切る形でむしろ強く変質を迫られていくようにも思うのです。『GUNSLINGER GIRL』を読んで、自分がトリエラだと規定していった途端、「私」は担当官のヒルシャーに愛し、愛される関係に組み込まれていくわけで、ひらたくいえば「男に抱かれるか否か」という問いを絶えずつきつけられる。そこまで含めて美少女文化を見渡せば、こうしたカルチャーは男性オタクの全能性をひどく脅かしているし、その意味で決して「安全な」ものではないというのが僕自身の見立てです。
■純愛モデルとしての処女と運命的な関係性
村 ずっと休載が続いていた『かんなぎ』(一迅社、2006年)が最近復活しました。『かんなぎ』にはナギというヒロインがいるんですが、彼女が実は非処女だったということで一部のファンから大きな不評を買って、そのせいで落ち込んだ作者がずっと連載を休んでいた――という風評が立っていたのですが、実は作者がくも膜下出血という重病を患っていたんです。そういうわけで休載はまったく別な事情だったわけですが、興味深いのは、そういう風評が特に疑われずに蔓延していたということです。漫画家さんは激務なので病気になる方も多く、そういう想定があって自然なのに、なぜか悪評に対する精神的ショックで......というストーリーが自然に受け入れられていた。これは逆に、作者よりも消費者の側がそういうものに対する強い感情的反応があって、それゆえに、消費者がこれだけ重要視している問題なのだから作者も重要視していた当然だ、という発想がかいま見える気がします。不幸なことに当時は非処女問題が立ち上がっていた時期で、美少女ゲームである『下級生2』(エルフ、2004年)の柴門たまきが、メインヒロインであるにも拘わらずゲーム開始当初から医大生と付き合っていて、当然のごとく処女ではなくなっていたんですね。それでキレた人たちがCDを割るなどのパフォーマンスをして過激な抗議行動をしていたのは今でも覚えていますね。しかし、ぶっちゃけ絵じゃないですか。ゲームにしても漫画にしても絵なのに、それが処女か非処女かに驚くほど興奮する人たちがいたわけです。もちろん、僕はそれが無理もないことだとも他方では思うのですが――ともあれ、『かんなぎ』は虚構とセクシュアリティを議論するいい導入になるかなと思っていました。
佐 いわゆる「処女厨」問題ですが、僕はそれについてはもっと素朴に捉えています。つまり、美少女キャラとユーザーとの関係は、ある種のお約束の上に成り立っていて、そのことをほとんど誰も疑っていなかった。けれどそのお約束を、女性作家である武梨さんが踏み破ってしまった。しかしそれは同時に萌えブーム、あるいはアキバブームによってお約束の外にいる人たちが、キャラクター文化の担い手として参入してきたこととパラレルな現象でもある。よって起きるべくして起きた事件だろうと。僕はそういうふうに見ました。
村 しかし、そのお約束が性にまつわるものだというところが症候的ですよね。こういう話をしていて思い出すのは一部のライトノベルです。まず一つはこのジャンルが凄く様式化されているということですが、それと同時に思うのはエッチな描写が増えたなということです。ちょっとエッチというくらいじゃ済まなくて、かなり濃厚な性描写と見まごうようなものまである。もちろん、ある種の真剣な物語展開としてセックスを描く場合もあるんですが、カジュアルエッチ路線のものはそういう発想ではない。そちらで興味深いのは、絶対にセックスそのものはしないということですよね。普通、セックスをしたら非処女化するわけですが、むしろそれを巧妙に避けながらエロをやっている。もちろん、おおっぴらに一般向けのコンテンツで性表現をするわけには行かないから、という制度との兼ね合いの問題はありますが、それにしてもここには本質的な捻れがある気がします。
佐 ペッティング的なものが横行する一方、比喩的ないい方ではありますが、どんなにセックスをしても妊娠しないキャラクターが描かれてるということですか?
村 仰るとおりで、ヤッてるのかヤッてないのか分からないけど、そこを隠して凄いエロいキャラクターがいっぱいいるなということです。でも、後者の「妊娠しないキャラクター」という指摘のほうがより重要な気がします。
佐 エロいキャラは望むが、決して妊娠しないような存在であって欲しい、生々しい女性性は忌避したいという欲望のあり方は、ハーレム願望のしかるべき到達点ではあるでしょうね。もっともそういうご都合主義的な欲望の裏でピュアさを志向する存在でもあるからオタクは分かりにくいのかもしれませんが、処女厨問題にはそうした欲望の捻れがよく現われていると思います。
というのも、処女非処女にまつわるお約束のコアにあったものが、性体験の有無という身体的な問題ではなく、ヒロインの運命という観念的問題だったと思うからなんですね。自分以外の人間がヒロインと運命的な関係を持っていること自体が純粋性を失わせる、すなわち自分以前の過去は基本的にノイズという発想です。こうした過去を広く依存対象と見れば、恋愛ものにおいて、依存対象を断ち切らせてヒロインを自分に振り向かせるモチーフが減り、依存対象を自分へと移行させるモチーフが増えたようにも感じます。ある側面から見れば、恋愛描写がどんどん単純になっていったといえるかもしれない。
村 運命をめぐるコンフリクトが描かれなくなったということですかね?
佐 そうそう。自分とヒロインの運命を脅かす存在はいつの頃からか物語から綺麗に排除されるようになったわけです。そうなった事情は分からなくもなくて、たとえセックスをしていなくても、ヒロインに過去の男とかがいるとその男と「俺こそが運命の相手だ」といって争わなくてはならなくなる。しかしそんな話は誰も読みたくないでしょう。
村 そういえば佐藤さん、『コードギアス』(2006年)ではC.C.が好きでしたよね。
佐 はい、好きでしたけど。でもどうしていきなりその話に?
村 今の話を踏まえると、佐藤さんはC.C.を争ってルルーシュと対決する妄想なんかをしてるのかなと思いまして。
佐 そんなアツ苦しい妄想はしませんよ。勘弁してください。
村 すみません(笑)。ところでヒロインと主人公の運命的関係といえば、『下級生』(1996年、エルフ)にティナというキャラクターがいましたよね。
佐 いましたね、そっちの話につなげましょう。ティナはまさに今話していたテーマにおける典型的なノイズで、実は主人公の婚約者だったと判明する宇宙人のお姫様でした。しかしプレイヤーにとってその婚約は未知の経験なのであって、ぶっちゃけ知ったことではないのに、他のヒロインと恋仲になろうとするとダメージを与えてくる。運命に対するノイズが別にヒロインの過去の男でなくてもよいという意味でティナは重要なキャラだといえるでしょう。
村 『下級生』はその点で『Kanon』(Key、1999年)に似てますね。つまりティナって月宮あゆみたいなものじゃないですか。二つの作品の違いは、ティナは急にやってきて、やってきたことに対する必然性に関するフォローアップがまったくなかった。
佐 むしろ嫌がらせをするためにやってきたような振る舞いをする。あゆはそれとはまったく正反対の行動を取る。つまり忍ぶ愛みたいな感じで、表面的には腹にパンチしたり結構ひどいやつだけど、内面的にやってることの帰結を辿ると、他の女の子のためにボクは犠牲になるよ的な感じでいる。おいおい、どんだけいいやつなんだと。
村 とはいえ僕の考えだと、あゆはいいやつじゃなくて凄く恨みがましい子なんですけどね(笑)。だってすべてのルートに現われて、探し物見つかったんだよ、見つかったんだよ、見つかったんだよって呟いて消え去るわけじゃないですか。本人からしたらトラウマみたいなもので、その後の幸せな生活に対するノイズになると思いますね。そういう点でいえば、ティナは単純なノイズですが、あゆは複雑なノイズですね。思わせぶりなので、彼女のルートで秘密を解明しなければならない、と思わされます。こういうところには、ナンパメソッドの蛭田と、恋愛メソッドのそれ以降のクリエイターの違いは現われているのでしょう。
佐 運命的なものに関する限り、『同級生』パラダイムというか、leaf/key以前のパラダイムは基本的に現実世界のルールに即していたともいえるわけですね。だからいろんな女の子とヤッてもいいし、その中から運命って見つけられるんじゃない?っていう、リア充的感性からすれば普通のことを描いている。
村 ノベルゲームが隆盛したのは、事前に設定された運命の存在感をもの凄く強調したからでしょうね。事後的に選べるようになる選択肢の存在とか、ゲーム自体がそういうシステムの現前性を凄く説得的にプレイヤーに対して示してくる。オタク自体もそこでどんどん感性を先鋭化させていった帰結として、2000年代のオタク文化があったのだと思います。
佐 かたやマルチヒロイン型のシステム、つまり運命の分岐によってコントロールされていたものが、単線的なストーリーに落とし込まれたことで起こすエラーを描くような作品が生まれたりもしました。『School Days』(オーバーフロー、2005年)あたりは、そうしたエラーが引き起こす悲劇を楽しませるニュアンスすらありましたが。
村 美少女ゲームって実はハーレムであることを巧妙に隠蔽したメディアなんですが、『School Days』はそれに責任を取らせる話ですよね。『うみねこのなく頃に』(2007年、07th Expansion)の謎解き編じゃないけど、『Kanon』のようなゲームでは美しく糊塗されているものが、幻想を剥いだら要するにこういうことだろうというかたちで批評的に指摘したものが『School Days』にある。結局、ほとんどのルートで主人公の誠は死ぬわけです。アニメ版でも驚くべき死に方をしました。こういうものが出ないと納得しないくらいには、市場が飽和していたのかもしれません。
佐 そこはもう無意識の話ですね。したがって『School Days』を運命を軸にすえた純愛モデルの破綻というか臨界みたいなものとすることはできるでしょうが、そのあと恋愛もの、ラブコメ的なものにおいて広がっていった光景というのはむしろお約束を再強化したものという気がします。
(続く)

※1 20世紀末は単なるポルノだったはずのアダルトゲームが感動という意匠によって物語化を強めた時期だった。代表格としては『Kanon』(KEY, 1999)や『加奈~いもうと~』(D.O., 1999)など。他にもドラマチックなノベルゲームがこの範疇の作品として消費されたところがあり、『AIR』(KEY, 2000)にて頂点を迎えることとなる。
※2 大塚英志『キャラクター小説の作り方』、東浩紀『ゲーム的リアリズムの誕生』、ジャン=リカルドゥ『言葉と小説』などを参照。
関連記事
美少女ゲームの哲学
第一章 恋愛というシステム
第ニ章 地下の風景
第三章 探偵小説的磁場
第四章 動画のエロス
第五章 臨界点の再点検
補遺
第六章 ノベルゲームにとって進化とは何か
第七章 ノベル・ゲーム・未来―― 『魔法使いの夜』から考える
第八章 美少女ゲームの音楽的テキスト
村上裕一 批評家。デビュー作『ゴーストの条件』(講談社BOX)絶賛発売中!最近の仕事だと『ビジュアルノベルの星霜圏』(BLACKPAST)の責任編集、ユリイカ『総特集†魔法少女まどか☆マギカ』(青土社)に寄稿+インタビュー司会、『メガストア』2月号のタカヒロインタビューなど。もうすぐ出る仕事だと『Gian-ism
Vol.2』(エンターブレイン)で座談会に出席したり司会進行したりなど。またニコニコ動画でロングランのラジオ番組「おばけゴースト」をやっています。http://d.hatena.ne.jp/obakeghost/
WEBスナイパーでは連載「美少女ゲームの哲学」とラジオ番組「村上裕一のゴーストテラス」をやっています。よろしくね!
佐藤心 駆け出しのシナリオライター。代表作『波間の国のファウスト』(bitterdrop)、『風ヶ原学園スパイ部っ!』(Sputnik)。「この世界はカネが全てだぜぇ~?」を処世訓としながら、とある中堅スーパーのお弁当を日々半値で買い叩く。そんな涙ぐましい生存戦略の果てに、講談社BOXより『波間の国のファウスト』のノベライズが決定(今秋発売予定)。