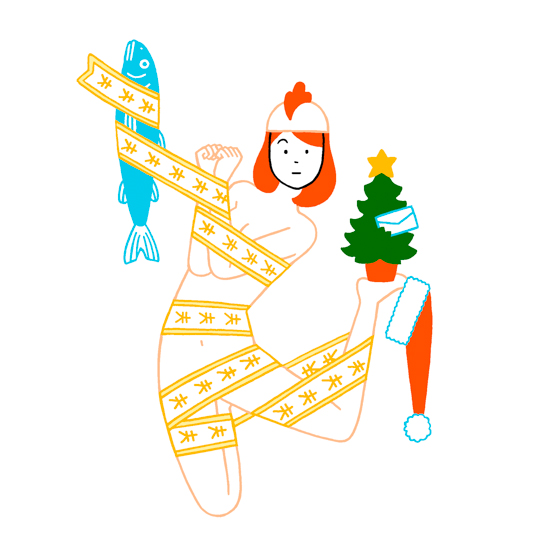月一更新
the toriatamachan season2
女の子にとって、「美醜のヒエラルキー(それによって生まれる優劣)」は強大だ! 「酉年生まれゆえに鳥頭」だから大事なことでも三歩で忘れる(!?)地下アイドル・姫乃たまが、肌身で感じとらずにはいられない残酷な現実――。女子のリアルを見つめるコラム、シーズン2は「お金」にまつわるアレコレです。その編集さんは、私と話した最初の日に漫画をくれました。ひたすら猫がおかゆを作る話で、けれど、その唐突なプレゼントと、私が猫を好きなことは関係がありませんでした。たまたま彼が読み終わったから。それだけのことです。その後、しばしば他の編集さんと一緒に、彼からごはんをご馳走になりました。食べきれなくても、いつも卓いっぱいに料理は並びます。あれから何度も、読み終わった漫画を人にあげる彼を見て、大量に買い込んだ食料品を袋ごと編集部のデスクに置き去る彼を見ました。でも彼がたくさんごはんを食べたり、何かに熱中しているところは見たことがなくて、本人の手元あるのは空になったペットボトルと仕事用のパソコンだけなのです。
ある夏日、私たちよりも鮮魚に合わせているとしか思えない過剰な冷房の寿司屋で、彼とサンタさんの話になりました。
私の家では、毎年、サンタさんに手紙を書いて、ツリーの枝に引っ掛けておきます。翌日になると手紙はなくなっていて、代わりにツリーの下にプレゼントが置かれていました。一度、弟と一緒にサンタさんへクッキーを作ったことがあります。翌朝、クッキーは半分だけ食べられていて、床には食べかすが散らばり、急いで次の家に向かったのか、窓が半分開けっ放しになっていました。12月の冷たい風に吹かれながら、弟とふたりで「サンタさんって、忙しいんだねえ」と話した記憶があります。
我が家のクリスマスはこうして緻密に行なわれ、ドライなクラスメイト達に「サンタなんかいないよ」と言われる度に、「サンタ『さん』でしょ」と思っていたし、サンタさんが来ない代わりに両親から現金をもらうという子の話を聞いては、そんな制度もあるのかと首を傾げました。こうして私も弟も結構大きくなるまで、サンタさんを信じていました。私はなんとなく両親にはお願いできない大きなプレゼントも、サンタさんには遠慮なくお願いできました。
それなので、彼が「ほしいものが思いつかなくて、泣いた」と話した時は、素直に驚きました。それも、ものすごい恐怖を伴って泣いていたことに。
クリスマスに現金をもらっていた女の子も、両親から直接プレゼントをもらって「サンタはいないよ」と話していた男の子も、何枚も何枚もサンタさんへの手紙を書き直した私も、いまでは22歳か23歳になっていて、自分でお金を稼いで、好きなものを買えるようになりました。
でも私は、いろんなことに、こと、手元に残るものは、ゲームもファンシーな文房具にもどんどんと興味がなくなって、成人してからもブランドものや化粧品に興味を持つことはありませんでした。不思議に思われるかもしれませんが、でもお金は稼ぎたいのです。使い道はどうでもよくて、自分の価値を知る手段として。もっと厳密に言うと、仕事をした後にお金が振り込まれることよりも、最初にギャランティを提示される瞬間のほうが、ずっと重要なのです。
地下アイドルでいると、自分自身にいろんな人から値段をつけられます。私の技術や、経験や、知識や、時間に。でも、私は、本当は、私が嫌な思いをしたぶんにお金が払われていると思う時があります。時々、こっそり。
ライターの先輩は、「仕事は選ぶけどギャラは選ばない」と言います。面白い仕事だったら安くてもいいし、ギャラが高くてもやりたくない仕事だったら断わるということです。私もそうです。面白い仕事だったらギャラはいくらでもいいのです。その代わり、やりたくない仕事でも、身の丈に合っていない(と、自分で思う)高いギャラが提示されれば受けてしまう時があります。自分を高く評価されたからって、自分を曲げるなんて。嘘つきだなあって思います。
でも本当は、そんなことよりも、嫌な思いをしないとお金を稼ぐことに罪悪感がある自分と向き合うことのほうがずっとずっと怖いのです。思えばアルバイトをしている時からそうでした。だから私は、お金を稼ぐとき、いずれにせよ痛みを伴います。
ところで、プレゼントが思い浮かばなくて泣いていた彼は、そのまま大きくなって、お金を持つようになって、好きな時に好きなだけ、すべて手元に残らないものに使っています。私も彼も、手元に残るものにあまり興味がありません。自分のためにお金を使うことにも。でもお金の使い方は違っていて、不思議だなって思います。
彼はずっと仕事をしていて、時々、ほんの少しうつらうつらする時と、人と食事をするとき(それから漫画を買いに行く時。でも私はそれを見たことがありません)以外は、ずっとパソコンと向き合っています。夏は過剰な冷房と、冬は過剰に暖房がきいた編集部で。朝は輝度を落としたパソコンの画面に、夜は輝度を上げたこうこうと光る画面に照らされて。すべてが逆転していて。
「実はおかしくなってたりして」と、私は言います。こちと、中トロと、赤身と、煮蛤と、いさきと、鮎と、うにと、牡丹海老の寿司の前で。彼は「あー、もう狂ってるかもしれない」と言ったあとに、嘘ですけどね、と言って笑いました。鮎の寿司を食べながら。
鮎は、私が一ヶ月ほど彼と同じ編集部で過ごして、唯一彼が食べたいと言ったものでした。毎日毎日、ほかの編集さんに何を食べたいか聞いてから飲食店を探す彼が。「ああ、鮎食べたいな」と。
サンタさんの話に戻りましょう。
なんと私の家には恐ろしいことに(22歳にもなって恥ずかしすぎて)まだサンタさんが来ます。もう私は手紙を書かないし、クッキーも作っていません。それでも、サンタさんからのプレゼントを、私はいつもとても気に入ります。今年も見てくれていた、と思います。なんの痛みも伴わず、特別にされていると思いながら。
文=姫乃たま
関連記事
とりあたまちゃんシーズン2
the toriatamachan season2

姫乃たま 1993.2.12下北沢生まれ/日本の地下アイドル/アダルトライター/司会/女子大生
アイドルブログ「姫乃たまのあしたまにゃーな」=http://ameblo.jp/love-himeno/
アダルトブログ「地下アイドル姫乃たまの恥ずかしいブログ」=http://himeeeno.hatenablog.com/
Twitter=https://twitter.com/Himeeeno
アダルトブログ「地下アイドル姫乃たまの恥ずかしいブログ」=http://himeeeno.hatenablog.com/
Twitter=https://twitter.com/Himeeeno

白根ゆたんぽ 1968年埼玉県生まれ。イラストレーター雑誌や広告、webコンテンツなどにイラストを提供しているほか自身のZINEのシリーズ「BLUE-ZINE」や個展の図録「YUROOM GIRLS SHOW」などの制作、販売も行っている。最近の仕事に「ノベライズ・テレビジョン」(河出書房新社)装幀、「セックスペディア」(文藝春秋)カバーイラストなど。
15.09.05更新 |
WEBスナイパー
>
とりあたまちゃん
| |
| |