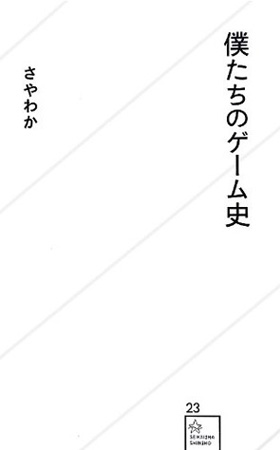WEB SNIPER special contents
対談:さやわか × 村上裕一
『僕たちのゲーム史(星海社新書)』をめぐって【前編】
昨年、星海社新書より上梓された『僕たちのゲーム史』。膨大な史料と明快な論旨からゲームの歴史を読み解く本書をめぐり、著者であるさやわかさんと批評家の村上裕一さんによって行なわれた対談を前後編でお届けいたします。執筆にあたり著者として臨んだ態度、ゲーム史におけるパチンコの位置づけ、拡大していくゲームの枠組みなど話題は多岐にわたります。大変ボリュームのある対談となっていますので、どうぞゆっくりお楽しみください。

『ゲーム的リアリズムの誕生~動物化するポストモダン2 』(講談社現代新書) 著者=東浩紀 発売日=2007年3月16日 出版社=講談社
村 おっしゃる通り、ゲームというものが持つ単なる娯楽以上の文化的思想的な部分を取り出そうとしたものですね。そのため、巷では思惟のようなものの結晶として捉えられている「文学」をあえて対置することで、ゲームのゲーム的ではないある一部分を強調した側面があります。実際、あくまでもゲームの一部門としてのノベルゲームには、素朴に見ればそういう対象としての物語が前景化していますからね。
さ でもそれは結局、散発的なものとして捉えられてしまった節がある。東読者ですらも、つまりこれは美少女ゲームなりライトノベルなり、オタクカルチャーを分析するための概念なんだというふうに読み取ったように僕はずっと思っていた。一方でいわゆるゲームファンみたいな人たちも、そういう分析に対して否定的なんですよね。彼らが言うのはつまり、ゲームというのは物語ではないんだよということなんです。東浩紀がやったのはフィクションの立場からゲームを捉えているか、あるいはノベルゲームなどに限定された内容に基づきながらゲーム一般であるかのように語ったものなのだという。それはゲームというものを単に物語の器として考えるような風潮に拍車をかけるものだから、許容できない。もう、ゲームについて語る時に一言でも「物語」という言葉を使えばアレルギーを起こしかねない人たちだっているんですよ。しかし僕は、たとえば「ゲーム的リアリズム」というのはつぶさに検討するとゲームをプレイするという体験一般について書かれたもので、つまりいわゆる物語性の高いゲーム以外にも敷衍できるものだと思っていました。
また、そもそも日本のゲーム史というのは、まさにこのような対立、つまりゲームを一種の物語体験として考える人たちと、ゲーム論から物語分析を排除しようとする人たちの対立すら、重要なトピックとして位置づけられるべきものだと考えたんです。だから物語的なものを尊びつつもそれに対する抵抗が発生していく、拮抗していく文化としてのゲーム史を書きたかった。そうすることで、日本のゲーム史を過不足なくまとめられると思ったし、ゲーム史全体の中に「ゲーム的リアリズム」が重視したゲームと、そうでないゲームを両方組み込むことができると思った。
村 なるほどね。いや、そうじゃないかとは疑っていたんです。というのも冒頭で宣言されるゲームの定義、つまり「ボタンの反応」と「物語との関係」という枠組がまさに「ゲーム的リアリズム」に対応する構図ですから。しかし、本書では「ゲーム的リアリズム」という言葉そのものはいっさい登場しないので、なかなか初めての読者はつらそうですね。

『BLACK PAST vol.2』 発売日=2012年8月12日 サークル=BLACK PAST

『ゴーストの条件 クラウドを巡礼する想像力』(講談社BOX) 著者=村上裕一 発売日=2011年9月2日 出版社=講談社
村 僕の本が出たのは2011年ですから、僕はゼロ年代ではないんですよ、といつも言うようにしています(笑)。
さ まあ厳密にはそうですが、しかし単著を出される前からご活躍でしたから(笑)。ともあれ、若手を中心にしてポップカルチャーの批評を繰り広げていこうという時代がありましたね。
村 はい。
さ 僕はそれを興味深く拝見していたんですが、しかし最終的にはそれ自体一つの島宇宙の中に閉ざされてしまったように感じていた。偏狭なサブカルライターとかは「とんちんかんな文章を書く居丈高な批評家連中が仲間内でオタク文化を語ってた」みたいに失笑してみせるのだと思いますが、むろん僕はそうした見方は間違っていると思います。そこには間違いなく批評的達成があった。しかしだからこそ、最終的には僕が思ったほどに外部へと影響を及ぼさなかったのは残念に感じていました。そこで、この10年に培われたものを、どうやって外に密輸入しようかと考えたんですよ。そのためにこの本ではいろいろな工夫をしていますが、たとえばまず第一に何をしたかというと、一般から見てジャーゴンに見えてしまいそうなものを全て排そうとしたんです。
村 大変素晴らしいと思います。
さ 考え方の枠組みだけを残して、さりげなく批評界隈では定番の発想を盛り込んでいくわけですね(笑)。究極的にはこれは要するにライトノベルを書くような作業なんだなと思ったんです。ただし、おわかりだと思いますがこれは「高度な」文学をスポイルしたものとしてラノベを捉えたわけではありませんが。
村 ある種、ビジネス書を書くような作業ですね。
さ そうです。いま新書という形態はビジネスマン向けのものとか比較的手軽な社会評論がよく売れていますよね。それを理解した上でさらなる読者価値を創り出す文体や構成を模索しているうちに出てきたのが「ラノベとして考える」というアイデアなんです。ラノベという比喩でないとしたら、「ポップス」として新書を作り上げるというアプローチに可能性を感じたんです。だから文章も一文一文を短くして、切れるところは切りながら、改行をとても多くしてるんですよね。そういう文体を新たに作るところから始めたんです。だから、僕にとって最も書きやすいというわけでもなくて、初めは書くのにすごく時間がかかりましたが(笑)。そしてさらに、本全体に物語としての構成みたいなものをなんとなく作って、ドラマティックに書く手法も使っている。
村 僕が本書に抱いた印象は「日本史や世界史の教科書みたいだな」というものです。それはよくもわるくも、というところがあって、個別のトピックをドライに書きすぎているような気がした。もっとここを読みたい、というようなところでもだいたいさらっと次へ行っちゃうんですよね。しかし、そのことによって包括的な記述になっている。この感じが教科書みたいだと思いました。僕は教科書という言葉を完全に好意的な意味で用いています。これからの人はゲームについて知りたければ本書を読めばいい。一家に一冊置いておきたいですね。
さ ありがとうございます(笑)。
村 あと面白いのは、取り上げなかったゲームを強調していることですね。表3にそのリストがずらっと並んでいますが、これは示唆的ですね。
さ そこに取り上げなかったゲームを載せようというのは、実は本文がいったん書き上がってから出たアイデアなんですよ。表3には本文からの引用として書いてあるんですが、実は事前のカバーデザイン時に表3を書いて、後からそれを本文に書き足したんですよね。なぜこういうのを入れたかというと、村上さんの連載でも、「鬼畜ゲームを『臭作』(エルフ、1998)一本に代表させることは難しいが」みたいな断わり書きが書いてあるじゃないですか。
村 書きました(笑)。
さ あの気持ちは、非常によくわかるんです。実は『僕たちのゲーム史』は、最初の原稿ではほとんど固有名が出てこない本だったんですよ。で、いったん最後まで書いてから編集者に読んでもらった時に、「あれもないしこれもないし」みたいに、かなりいろんなゲームの名前を言われた。僕は重要な作品名をいくつか挙げて考え方のフレームを提出すれば、あとはいろんなゲームに敷衍して読者は考えてくれるだろうと思ったんですが、そうでもないんですね。
村 そうでもないんですよね(笑)。
さ 「あれがないじゃん」みたいなことを言われてしまう(笑)。「いや、この理論に従えばあなたの言ってるゲームは当然入ってくるぞ」と思うんですけど、でもそこで、「むしろ、このこと自体が歴史の本を書く上でのテーマになりうる」と気づいたんです。だからまずは出てこなかったゲームを表3にいっぱい載せて、「これは敢えて出てきませんよ」ということを書いた。そして「歴史というのは何について書かないかが重要である」というテーマを本全体に行き渡らせるようにリライトした。しかし同時に、重要なゲームの周囲に、似た傾向を持ったゲームを、名前だけ列挙するような形にした。つまり、もともとは思考のフレーム提示を中心にしようと思って書いていた本だけど、結果的には教科書的な読み方もできるような本になったし、記述の背景に批評的な文脈も走らせてある本になった。

『セックスメディア30年史欲望の革命児たち』(ちくま新書) 著者=荻上チキ 発売日=2011年5月11日 出版社=筑摩書房

『ゼロ年代の想像力』 著者=宇野常寛 発売日=2008年7月25日 出版社=早川書房

『風の歌を聴け』(講談社文庫) 著者=村上春樹 発売日=1982年7月 出版社=講談社

『スーパーマリオブラザーズ』 発売日=1985年月13日 プラットフォーム=FAMILY COMPUTER メーカー=任天堂
さ むりやり増やしてますしね(笑)。でもその「歴史というのは何について書かないかが重要である」というのは、この10年のポップカルチャー思想を論じる上でも凄く大事な考え方だと思ったので、それを示唆したくて書いた部分なんですよね。僕の印象に強く残っているのは、宇野常寛さんの『ゼロ年代の想像力』(早川書房、2008)が出た時に、宮台真司さんが帯文で「単なる『好きなもの擁護』を超えた」って書かれてたじゃないですか。それはわかるんですよ。なぜ好きなもの擁護がダメかというと、これだけ世界が細分化していると、自分が好きなもののことを書いても「お前が好きなだけだろ」というそしりを免れないというか、社会全体に対する目線も影響力も持てないものになってしまうというわけですよね。でも実際のところ、その全体性みたいなものって、結局は持てないものなんですよね。
村 重要なのは最初に「これは好きなもの擁護ではない」ということをいかに宣言するか、ですからね。
さ そうそう(笑)。その通りなんです。あまり理解されていないと思いますけど、宇野さんの著述が真に優れていたのはそこだと思うんです。好きなもの擁護に堕してはいけないということと、それでも全体性を持つことはできないということの両方に自覚的なんですよね。『ゼロ年代の想像力』でも冒頭でノートの中央に一本の線を引いて、右側には埋葬すべき古いものを並べ、その左側には現在的かつ将来越えられるべきものを並べていくという整理をするわけじゃないですか。この宇野さんの書き方自体は村上春樹の『風の歌を聴け』へのオマージュだと思うんですけど、しかし宇野さん自身、これが選別の作業であるということを自覚してやっているんですよね。これは今日ポップカルチャーを題材にした、評論や批評の書き手であるためには、絶対に自覚的でなければならないことだと思うんです。何を選んで、何を棄てているかに自覚的であるからこそ、闇雲に「好きなもの擁護」をやる態度から距離を置くことができる。
ところが話をゲームに戻すと、今日のポップカルチャー、ことにゲームの評論には、そういうものが非常に少ないんですよね。ゲームはデータがデジタルで手に入るわけで、『スーパーマリオブラザーズ』(任天堂、1985)と、2012年の今日発売された横スクロールアクションを、全く等価値に並べることができちゃうせいもある。そうすると、古今東西のあらゆるゲームのアーカイブを手中に収めているような気分になって、何を選び取って、何を棄てているのかという視線が薄れてしまう。
村 それはおかしいですよね。
さ 同じことは、DVDによって過去の映画が手軽に手に入るようになったことについて蓮實重彦が指摘していた覚えがあります。いずれにしてもそれは避けねばなりませんでした。だから、この本を作っていく中で取り上げるゲームを自覚的に選択しているということを明らかしたのはいいことでした。あと、もともと考えていたアイデアとしては史料に頼るということですね。つまり基本的に過去の史料を根拠にしながら、文中で取り上げるべきゲームの選出とか、あるいはその価値についての判断を下していったわけです。
村 最初のアクションゲームの項目に、70年代に早くも、ゲームというものはすでに出尽くしているという議論が引用されていましたね。普通ああいう議論は、当たり前ですが、若い読者は知らないものだと思います。

『巴里の憂鬱』(新潮文庫) 著者=ボードレール 訳者=三好達治 発売日=1951年3月 出版社=新潮社

『善悪の彼岸』(新潮文庫) 著者=ニーチェ 訳者=竹山道雄 発売日=1954年5月
出版社=新潮社
それは実は僕が学生時代に文学を学んだ時の経験が基になっている。たとえばエドガー・アラン・ポーとか、あるいはボードレールは、近代的な「都市」というものを初めて描いた人たちなんです。ボードレールの『パリの憂鬱』には「群集のなかに湯浴みする」という言葉が出てくるんですが、つまり群衆の一人になることは悦楽だと言うんですよね。誰でもないものになるのは心地がいい。それは今ならわりとどんな人でも理解しやすい考え方じゃないですか。誰でもない存在になって群集の中にいるとラクだ、心地がいい、あるいは逆に群集の中でひとりぼっちだから辛いというような考え方は、今やほとんど普遍的な考え方だと人は思うんだけど、それより前の歴史には群集というもの自体がなかった。群衆を生み出す都市そのものがなかったので。だからそうした考えは普遍的どころか、全く存在しなかったんです。そしてこの『パリの憂鬱』はそのことを初めて指摘した本なんです。しかしこれを、現代人が単にアーカイブから取り出して「当たり前のことを言っている本だ」と言っても意味がない。当時に群衆がそのようなものとして見出されたということに意味があるんですよね。
僕は作品自体がデジタルで、当時のままに再生できてしまうゲームというメディアに、何とかそのような歴史的な観点を付加したかった。そのためにまずゲーム雑誌などを史料として使うことを思いついたんです。ある種のアクションゲームが80年代の半ばにはすでに「出尽くしていた」と当時の雑誌に書かれているという事実を指摘すれば、あらゆるゲームを一括して「過去」として扱うような姿勢を揺さぶって、そのゲームの前にも、今とは全く違う、その時点から見た歴史があったということを思い出させてくれるんじゃないかと思ったんですよ。

『定本 日本近代文学の起源』 (岩波現代文庫) 著者=柄谷行人 発売日=2008年10月16日 出版社=岩波書店
そういう視座を欠いた議論は滑稽にもなる。マルクスが「歴史の事件は二度現われる。一度目は悲劇として、二度目は喜劇として」ということを言っていました。そしてこの言葉はそのままジジェクに引用されたわけですが、確かにジジェクが引用すると喜劇っぽい(笑)。というのは余談としても、「出尽くした」という議論がすでに何度も現われているということの喜劇性には意識的であるべきでしょう。
さ 「出尽くした」と書かれていたという話から始めるのは、実はかなり意識していました。つまり我々が読み始めた時点で、すでに歴史は終わりかけている。そして、それに関連してもうひとつ意識していたのはこの本の大きなテーマの一つである「ゲームが物語をどう扱うか」という話が、実は全九章のうちの第六章で終わってしまうように見えるという部分です。つまり、すでに歴史は終わりかけたところから始まって、本の半ばを過ぎたところで本当に終わりが来てしまうわけですね。だけど、それは一つの終わりでしかない。そういう話にしたかったんですよ。

『ひぐらしのなく頃に -鬼隠し、綿流し、祟殺し、暇潰し編-』 プラットフォーム= Windows XP Home Edition サークル=07th Expansion

『空の境界 上』(講談社ノベルス) 著者=奈須きのこ 発売日=2004年6月8日 出版社=講談社
さ そうそう。
村 あのラストは感動的だと思いました。
さ 「ゲームの歴史とは、物語をいかに扱うかを追い求めてきた」というだけの内容だったとしたら、この本は第六章で終わったはずなんです。でもさっきも言いましたが、僕がしたかったのは、ゲームって別にそういうものじゃないよねということなんですね。結構、念頭にあったのは『空の境界』(講談社、2004)なんですよ。あの小説は第五章で最大のラスボスみたいなものが出てきて、それを倒してしまうんだけど、なお物語は終わらないんです。歴史が終わった後も何かが残るということが最後のクライマックスになっている。僕はあの構成は、ポストモダンを条件とするなら、すごく妥当だと思ったんですよ。だから僕もこういう構成にして、論というか、歴史は閉じないのだというところを最終章に書いた。
村 まさか単にトレンドの推移という観点のみにて、最後をカジュアルゲームで終わりにしちゃったら「マジかよ......」って感じになりますからね。文字通りに悲劇的でしょう。
さ 何もかも終わらない状態で終わっちゃうみたいなことがやりたかったんですよね。それが一番歴史というものにたいして誠実だと思った。
■複雑なゲームの問題を歴史として語るために
村 本書を読んでいて、ゲームの問題は本当に複雑だなと思いました。というのも、複数の問題系が交差しているからです。たとえば、途中までソフトの話をしていると思ったらハードの話になっている。ゲームの話をしていると思ったら、メタゲームの話になっている。コンテンツの話をしていると思ったら、コミュニケーションの話になっている。ところが、こういう二項対立を単純に並べて、ソフトとゲームとコンテンツは同じ目に入るもので......などという整理はできません。
さ できないですね。
村 そこが複雑なんですよね。この話はメタ・メタレベルみたいなところがあるんですが、しかしゲーム史の問題そのものでもあると思うので、網羅的なこの本と並べてもこの本に書いていないことが喋れるかな、と考えていました(笑)。
さ (笑)。それを最も実感したのはやっぱり奈須きのこの扱いなんですよね。村上さんの連載にもありましたが、TYPE-MOONのゲームというのは極端に物語的なもので、しかも直線的なものである。これは何なんだろうと。普通に考えると、まさに美少女ゲームが『AIR』(Key、2000)あたりで臨界点を超えて、その後にはただ単にエンタテインメント性が高いだけの作品が流行る時代が来たんだよって話になる。でもよくよく見ると奈須きのこは、完全に物語を使いながらシステムの話をしている作家なんですよね。だからコンテンツだとかコミュニケーションだとか、ハードだとかソフトだとか、そういう話を超えてすべてが接合できてしまうということの頂点にいるのが奈須きのこだと思うんです。 それは村上さんの連載を読んだ時にも思ったんですよ。奈須さんは伝奇ものとしてベタな話をやってるようでありながら、実はものすごい多様なテーマを組み込んでいるんだという話をしてるじゃないですか。
村 ハードウェアがやるべきものを物語が代行しているということですね。しかもそれに関する自意識を抑えこんでいて、メタであるようには決して見せないようにしている。極めてストイックで、こういうものが文学だったはずだと思わされますね。
さ TYPE-MOONって本当に変わってるなと思うのは、システム上はどんどん洗練されるというか、ユーザーが従来的な意味でゲームとして関与する余地が何もなくなっていくわけじゃないですか。村上さんの連載を読んで思ったんですが、あれだけ研ぎ澄ましていくと、二次創作の可能性は本来なくなるんじゃないかと思うんですよね。でもそれが反転して、二次創作を生むための装置になっている。

『月姫読本 Plus Period』 発売日=2004年10月22日 出版社=宙出版
奈須さんといえば、『月姫読本 Plus Period』(宙出版、2004)の話が引用されてますよね。しかもそれは『Kanon』(Key、1999)についての話題なんですが、僕はこの作品こそ美少女のゲームを最高にシンプルにしたものだと思っているので、この引用はさすがだと思いました。
さ (笑)。そこはね、村上さんの連載と、ばっちりかみ合ってるところなんですよ。奈須きのこはあそこで、まさしく「美少女ゲームというのは、つまり〈女の子が物語を持っている〉ものだ」ということを言ってるんですよね。そして村上さんも連載の中で、美少女ゲームの定義というか、その条件とは「女の子が物語を持っていて、主人公を争奪する話である」としているじゃないですか。
村 そうです。
さ それと同じことをね、僕は奈須さんが言ってるところを見つけられたんですよ(笑)。
村 やられたなあ、って感じです。
さ 奈須さんが言う「『Kanon』もいいと思ったけど、主人公が活躍する話にしたかった」っていうのは、つまり王道のバトルものがやりたいというような、単に物語回帰したいという話ではないんですよね。そうではなくて、物語論とゲームシステム論が完全に融合しているんですよ。
村 そうなんですよね。主人公に活躍させると恋愛ゲームというフレームが壊れるので、TYPE-MOONのゲームがいわゆる美少女ゲームっぽくないのはまさにそこに起因してるんですよね。でも主人公を活躍させることによって、主人公もいなくなってる気がするんです。
というかもう群像劇ですよね。『Fate/stay night』(TYPE-MOON、2004年)だって、士郎が主人公と言えば主人公だが、凛が主人公だと言えばそう見える。
さ それはまさに、村上さんが連載で「鏡」っておっしゃってた問題ですよね。
村 なるほど、そんなこともこの本から読み取れてしまうんですね(笑)。
さ そうそう。そういうことを実は全部込めたうえで書いてあるんですよ。意外にそういうふうに読まれないんですけどね。
村 いやあ、でもなかなかそういう論理を読み取るのは難しいでしょうね。特に一般のゲームファンの方は。
さ そうなんだ(笑)。
村 たとえば奈須きのこがシステムについて語っているから、システムの問題として取り上げることができるという話がありました。文章はいろんなものをフラットにできるため、「Xについての話」と「Xの話」を同じように扱えますが、しかし本当は二つのものはかなり異なったもので、僕なんかが書く文章だとまずその変換の妥当性に批判が入ってきますね。もっとうまくやりたいものですが。
さ (笑)。そこはね、「好きなもの擁護」みたいな話に近づいていくと思うんですが、要するにお前が奈須きのこのゲームでよく遊んでるから、いわば我田引水的に持ち出してきて「彼はこういう考えで書いていて、ここには時代の意識が反映されてる」みたいな話したかっただけじゃんみたいな批判がくるということですよね。それってまあ、ここ10年くらいのいわゆる「ゼロ年代の思想」としても、それに向けられる批判のあり方としてもステレオタイプだと思うんです。だから僕は2012年に本を出す者としてそれを超えるやり方をしないといけないと思った。それが資料を使うことに顕れてるんですね。つまり単純に「ほら、ここに書いてあるじゃん!」というのを持ってきてるんですよ。
もちろん僕の書きたい歴史というのはあるんだけど、それに合致するような、とりわけ大事なのは「当時の」書物を持ってきて、議論の流れを妥当なものにしている。
たとえば、奈須きのこは単にウェルメイドな物語作家ではなくて、美少女ゲームというシステムを考え尽くした上であの物語を作っているということに傍証が生まれる。そうやって、我田引水だと言われるのを回避してるんですよね。
村 大丈夫です。充分回避できてると思います(笑)。唯一問題があるとしら、『ひぐらし』で締まってるところですね。

『ラブプラス』 発売日=2009年9月3日 プラットフォーム=Nintendo DS メーカー=コナミデジタルエンタテインメント

『モンスターハンターポータブル』 発売日=2005年12月1
日 プラットフォーム=Sony PSP メーカー=カプコン
村 『ラブプラス』でしょうねぇ(笑)。
さ なぜ『ラブプラス』じゃなきゃいけないんだろうって、僕は書きながら全然分からなかったんですが、でも結果的に『ラブプラス』になったんですよ。内容としては『モンハン』と併記する形なので、そっちが最後になってもおかしくなかったはずなんですが。
村 でも、僕はすごく整合的だと思いました。特に感心したのは『ゴーストの条件』の語彙でいうと、「目的外使用」がはっきりと現われていたところです。そこではゲームがゲームじゃなくなっていく過程(『ひぐらし』)があって、他方ではゲーム機じゃないものがゲーム機になっていく過程(『携帯電話』)があった。そういうものが同時に描かれていて、歴史の弁証法を感じました。この流れを逃さずに書かれているのは凄いことだと思います。
さ ありがとうございます。
■はたしてパチンコはゲームか?
さ あとこの本で語り落としたのはゲーム実況とかRTA(Real Time Attack/ゲームクリアまでの時間を競うプレイスタイル)みたいな文脈なんですよね。
村 その話をまさに今日しようと思ってたんですよ。
さ ああ、本当ですか。
村 しようと思ってるネタはいっぱいあるんですよね、実は。
さ 他に何があるんですか(笑)。
村 ゲーム実況の話しようと思ってますし、ソーシャルゲームの話と、あとパチンコの話しようと思ってきたんですよ。
さ ああ、パチンコね。パチンコかぁ!

『ファイナルファンタジーVIII』 発売日=1999年2月11日 プラットフォーム=PlayStation メーカー=スクウェア
さ なるほど。
村 こういうもののせいで筐体機をベースにしたコミュニケーションって追いやられていて、たとえば対戦格闘ゲームなんてどんどんやれる場所が減ってるんですよね。それもあって僕個人としてはこれをゲーム史の中の出来事として常々考えていたんですね。それが本書ではどういう扱いになるのかにはちょっと興味があります。
さ なるほどね。一応僕は、あまたのゲーム、つまり掲載されなかったものでもありとあらゆるゲームをこの本の中に位置づけることが可能だと思って書き上げたんです。しかしパチンコはソーシャル感もないし、そもそもギャンブルだもんな(笑)。考えたこともなかったな。まあ、システム的には『ひぐらし』的なものだと考えるのが正しいんでしょうね。つまりボタンを延々と押し続ける、ガラケーだったら「5押しゲー」とか言われるような単調さを感じさせるものですね。その中に、確率的に数字が上がるとか下がるとかいう展開が用意されていて、それが具体的に自分の人生という物語に跳ね返ってくるようなものだ、と説明付けられるかなあ(笑)。
村 僕、この本にとってパチンコは本当に重要だと思っていて、何故かというと、最初にボタンを押したら反応するゲームと、物語の扱い方か変わっていくゲームっていうじゃないですか。これは一見、ゲームのゲーム性が消失していって物語が前景化してくる本に見えるんですが、パチンコとかパチスロは最近アニメとのタイアップが増えた結果、まったりとアニメを観る台になってるんですね。ところが人はアニメには興味はなくて、単に当たって玉が出てくるから気持ちいいので、物語がゲーム機になってるんですよね、この中で。
さ パチンコは画面をぼーっと眺めてやり続ける中毒性があるみたいなことはよく言われますけど、あれもまたゲームだということですよね。「ボタンを押す」と、画面が光ったりアニメが動いたり、玉が増えたり減ったりするという「反応」のあるゲーム。
村 僕はゲームだと思うんですよね。もちろんゲームセンターにもありますし。
さ ただ今僕はそれが『ひぐらし』と近いと言ったんですが、それを少し訂正しつつ、僕が本に書いたことに補足したいところがあります。というのも『ひぐらし』というゲームについて、僕は「プレイヤーはボタンを押してるだけで、物語の進行には関与していないのだ」と書いてるんですが、厳密に言うと本当はそこまで割り切れるものではない。プレイヤーはスペースバーなりなんなりというボタンを叩くタイミングによって、テキストをどのように表示するかをコントロールしてるわけで、僕は話をシンプルにするためにそれを書かなかったんですよね。本当はプレイヤーは台詞や地の文を任意のタイミングで「言わせている」。あるいは自分が担当する画面演出の一種として、地の文を表示させるタイミングを制御している。これによってゲームに参加していると言えるはずなんです。
村 それは挿絵ですよね。後半のほうに「新しい一人称」って話があるじゃないですか。FPS(First Person Shooting game/一人称視点シューティングゲーム)のところに。ボタンは単に理解を分かりやすくするための装置であって、読んでいることが参加することじゃないですか。
さ おっしゃるとおりで、ゲームをプレイする上では単なる読み手という立場はなかなか取れない。そもそも僕の本の「ゲームとはボタンを押すと反応するものだ」っていう定義自体、実は/(スラッシュ)が入るようになっていて、「ボタンを押す/反応する」に分かれる。つまりはこのダイアローグこそがゲームなんだってことを言いたくてこういう定義を作ったんです。まあしかしやはり、「ゲームとはインタラクティビティのあるものだ」みたいな言葉ではなくて、「ボタンを押すと反応するもの」とすることで、柔軟に定義を使いこなすことができるよう配慮したんですが。
村 なるほどね。ところでパチンコには、当たり外れには全く関係ないんですが、演出を盛り上げるチャンスボタンっていうのがあるんですよ。それを押すと、状況に応じて「アツい」演出が起きたりする。そうすると、人はそのボタンを押したから当たったのだという体験を得たりするんですよ。正直、実体的な行く末にはこれは何の関係もありませんから、非常に不思議なものです。どんなに当たりっぽい演出が来ても外れたりするから、さらにわけがわからない。ある意味で「理解を撹乱するための装置」です。こういうものを押すこともゲームになるんですかね。
さ いや、しかしどっちみちその「参加した」という感覚自体がゲームだと僕は考えているんですね。ゲームというのはもともと全てはプログラムされているわけです。できることは限られている。しかしその決定されたプログラムに対して自分が何か関与することによって、あたかも機械との対話が成り立ったかのように感じる。どうかするとプログラムされていない動作があったように思われたり、実際に起こったりもする。その「意外さ」という体験自体がゲームだなというふうに考えてるんですよね、僕は。
村 僕もそうです。
さ そういう意味では、パチンコもやっぱりゲームになるはずですよね。
村 だからむしろこうなってくると、ゲームと思ったらゲームという世界に非常に近づいてきてるんだと思うんですよね。それが恐らくゲーミフィケーションの話なんですが、それはオバマが選挙で利用したというような例で理解されている話ではないと思うんですよ。今直面している事態はもっと、超ゲーミフィケーションみたいな感じがするんですよね。
さ どういうことですか?
村 ここまでくると、これはどう世界を認識するか、あるいはどう生きるかというような問いが直接召喚されかねないということです。というのも何がゲームか、そして人生はどうゲームと同じでどう違うのかを考えざるをえないからですね。そして美少女ゲームはそういう問題の現われ方とすごく関わってきていました。こういう話は、僕の知る限りさやわかさんもかなりコミットしていたように思います。
さ その通りだと思います。そして、この本でそういう話をなぜ抜いたかというと、そっちへいくと「真正な物語探し」みたいなものに参加する可能性があると思ったんですよ。
村 そうですね。
さ 単純な例で言えば「このゲームはストーリーが優れているからゲーム史的に重要である」みたいな言い方もできてしまう。あるいは「現代人のあるべき生き方、ロールモデルを提示している」とか。しかし先ほどから話しているように、ゲームとは物語ではないんです。だから僕は倫理の問題を語らなかったし、この本は物語内容にはまったくと言っていいほど踏み込んでないんですよ。
村 だからむしろ、さやわかさんが自分の欲望にいかに抵抗するかという原稿になってるんですね(笑)。
さ 全くその通りです。僕自身はゲームの物語内容がすごく好きなんですから。
村 珍しいなと思ったのは、今回「物語評論家」って肩書きについてるじゃないですか。
さ そうそうそう。それは編集者が、「ライター」じゃなくてもうひと声、この本を読む人が「あっ、この人はこういう人なんだ」って分かるようにしてくれと言ったんですね。で、前にばるぼらさんと話した時に「最近、『専門は何なんですか?』ってよく聞かれるんですよ」って言ったら、「じゃあ物語評論家とかでいいんじゃないですか?」って言ってくれたんですね。それを思い出してこの肩書きを書いたんですよ。ただ物語評論家と言いながら、実は物語の中身については全然書いていないという、ちょっと不思議な本になっている。
村 最後まで読んでいって、終わったーと思って裏表紙を見たら物語評論家って書いてあって、「ああっ」ってなるんじゃないですか。
さ つまり物語内容じゃなくて、「物語というものに人々は拘泥しているのです」という意味で物語評論をやってるんですよね。実際、なぜそうやって物語内容に触れないものにしたかというと、やはりいわゆる「ゼロ年代の思想」の多くが、物語内容を重視しすぎていたように感じるからです。それは多数の分野を横断的に語るために有効な手段だったんだと思うんですけど、しかしそれぞれのジャンル的な条件を度外視してしまう。言ってみればアニメと漫画とゲームと小説と映画からナラティブに関わる部分だけを取り出して、書き手の価値観だけで評価できるんですね。それにはやはり問題もある。たとえばそうしたやり方だと音楽についてはほとんど扱えませんから、「ゼロ年代の思想」には歌詞や産業分析以外の側面から音楽を対象にしたものがとても少ない。僕がいま単著を出して10年代の書き手になるのなら、それを次の段階に進ませていくべきだと思った。だからまずはロールモデルになりうるかとか、あるいは倫理的に正しいかみたいな反映論は、ほぼ書かないようにしてますね。
村 一瞬触れてるのは、ゲーセンのところですかね。風紀を乱すような問題だというのがあって。

『(NDS)ULTIMATE MORTAL KOMBAT(輸入版:北米版)』 プラットフォーム=Nintendo DS メーカー=Midway Entertainment
そういう経緯は非常に面白いんですけど、僕の本に盛り込むことは避けました。それを語ることが、必ずしも「ゲームの歴史」とは呼べないというのもありました。だから僕がこの本で物語の内容について一番言及しているのは、メタ物語についてだと思います。つまり「このゲームは再帰的に、物語というものについて物語内で言及している」ということだけは何度か書いています。言い換えればそれはもう、一般的な意味での物語の中身については何にも言う必要がないということの表われなんですよね。
村 そうですよね、文学論的なものがあって、メディア論的なものがあって、あと歴史論があるとして、上にいくほど僕が書くようなものに近づいていくんですが、さやわかさんはいちばん基礎的なレイヤーでふんばっている気がする。
さ そうですね。
村 だからたとえば法規制の話、この流れだったら書いてもいいと思うんですよ。でも本当に、意地でも、意地でも「僕たちのゲーム史」(笑)。
さ そうですね。まあ、あくまで「ゲーム史について書いた本ですよ」という範囲を守りながら、めくばせみたいなことをして、いろんな論点を引き出せるような本になっている。だから人文系の読者にしっかり読んでほしいなと思っているんですよね。
村 とにかく実証的な本になっているので、人文系の読者にはありがたい内容だと思いますよ。みんな、読んでないふりをして読んでいるタイプのものじゃないでしょうか(笑)。
さ 単に「要するにゲームの歴史が網羅的に書いてあるだけ」という本に見えるかもしれないので、難しいところでしょうけどね。
■最も重要な美少女ゲームは『AIR』だが......
村 それはそうとして、せっかく僕の「美少女ゲームの哲学」も参考にしてくださっているからにはちょっとそこのところのお話もこの機会に伺いたいですね。
さ その話は僕もしたかったんです。さっきも言いましたけど僕が村上さんの連載からインスパイアされたアイデアは、最終的には『同級生』(エルフ、1992)と『To Heart』(Leaf、1997)のみになってるんですけれども 。もう、『AIR』の話すらこの本はしていない。『Kanon』のことは奈須さんの発言の引用で少し出てきますが。
村 僕は『Kanon』にこそ最大の評価を与えているので、この話題が間接的にでも出ているだけでとても嬉しいですね。
さ そうなんだ。それはけっこう意外ですね。何故ですか。
村 『AIR』は、余計なものが多いんですよ。すごくよくできていて、歴史に残ってるし、後の世界のゲームを変えたんですが......。
さ つまりあまりにラディカルというか、美少女ゲームという形式についてクリティカルな指摘をしてしまったから、むしろよくないとか?
村 『Kanon』が、一番形式を純化してるんだなあと思ったからです。
さ なるほど、そこまでの泣きゲーうんぬんみたいな流れもきちんと追い求めつつ、それが、破綻しないところで、最も純粋な形をもっているということでしょうかね。
村 泣きゲーって言葉は重要で、美少女ゲームっていわば泣きゲー化したから実存と関わり文学化した側面があると思いますし、そう考えられてきたとも思うのですが、内容のレベルでそのいちばん純粋な形が『Kanon』にあると僕は思います。その前後の『ONE ~輝く季節へ~』(Tactics、1998)や『AIR』になってくると、なんかおかしいぞって感じなんですよ。普通に考えると、主人公が突然消えるとか、理不尽な千年前の呪いとか、設定が振り切れていて感情移入を阻害するはずなんですよね。しかしながらもちろんこれらの作品は世界に評価されている。しかし、それを純粋な意味で泣きゲーと言ってよいのかは、些細すぎる問題ですが結構ずっとひっかかっていました。
さ だって、それこそメタ的な構造を踏まえて泣くようなゲームですもんね、『AIR』って。あれは要は「お前は全てをコントロールできるつもりでゲームをやってるつもりだったかもしれないけど、ゲームというのはつまりお前が関与できない世界なのだぞ」ということを突きつけられて、その衝撃によってプレイヤーは泣く訳ですよね。
村 物語の中で完結しているものと物語の外と異常に関係しているものに凄くくっきり分かれてしまっているので、そっちはとりあえず置いておきたいなみたいな気持ちがずっとあったんですよね。と思ったんですが批評的趨勢に負け、そっちばかりを語る世界になってしまいましたけど。
さ まさに僕が気になっていたのもそこで、批評的な文脈では確かに『AIR』は最も重要な作品だろうと思うんですよ。
村 最も重要ですね。
さ しかしそうであるがゆえに、その後ノベルゲーム市場は停滞していく。『AIR』はたしかにすごいのだけれど、いい悪いの問題ではなく、あそこまでの作品が作られてしまうと一つの限界が見えてしまう。そのことを僕はきちんと書いてみたかったんです。だから、この話では最終的に『ひぐらし』も出てくるけども、「『ひぐらし』最強です!」みたいな本にはならないんですよね。ノベルゲームがますます伸びていくわけじゃない。それはゲーム市場全体から見た場合、マニアックな文化になっていってしまった、あるいは島宇宙のひとつになってしまった、と書くしかない。

『うみねこのなく頃に[第1話~第4話]』 プラットフォーム=Windows 2000/XP/98/ME サークル=07th Expansion
さ (笑)。そうそう。『うみねこ』になるとね、もう一般性とかほとんどないじゃないですか。
村 全ての前提が壊れてますからね、『うみねこ』では。
さ あれは竜騎士07さんも『ひぐらし』という達成を踏まえたうえで書いてる感じですよね。だとすると、もちろん熱心なプレイヤーにとっては重要作になってきますけど、一般ユーザーとか、ゲーム史全体にとってみると、うまく位置づけられないように思う。だからこの本には『AIR』も『うみねこ』も出てこないんです。
村 僕が絶対に悩んだ挙句に左折を選ぶところを全て右折してくれたなという感じがしますね(笑)。
さ (笑)。なるほどね。そうか。でもそれは結構意識したかもしれない。できる限り一般読者に向けて書かれているし、もう用語のレベルで、「ゲームというのは要するにプレステとかDSとかそういうやつのことです」とか、「美少女ゲームというのは要するにエッチな絵が見れるアレです」とか、徹底的にそういう書き方をしているんですよね。あと「物語」とか「物語性」という言葉の意味も猛烈に広く使ってる(笑)。
村 でもそうでもないですよ。最初に押したら反応するってことと物語で分けた時に、ある種のゲームの発達史みたいなものも物語だって言ってしまえるわけじゃないですか。
さ はいはい。
村 それをさっきみたいな感じにしたので、素晴らしいなと思って見てたんですよね。
さ (笑)。ありがとうございます。
村 そういうのが世界にありがちだし、僕がそういうことしがちなので。でもだから逆に、それを心がけたせいでゲームが内在的に持ってる複雑な文脈ってものがかなり明らかになりましたよね。
さ ゲームとかゲーム史とひと口に言ってるんだけれども、それをひとつに定めないことこそが正しいやり方だと思ったんですよね。それもやはり今日の状況を鑑みてのことなんですけど、要するに「自分の信じているものだけがゲームだ」とだけ信じてる人たちのために書いたり、あるいは対立する派閥に対して挑発的に書く形になることは避けました。実際そういうことは、アニメなんかもそうですけど、ゲームのファンダムにはもの凄く分かりやすく起こっていますし、そのヘゲモニー競争に参加してしまうと、ゲーム史として客観性があるとは言えなくなってしまう。むしろそれを何とかして、脱臼させるような本にしたかったんです。今の時代に何が真正なものなのかは決められないみたいなことに気づける本にしたいと思ったんです。
村 それくらい価値中立的な本になってると僕も思います。
■それがゲームだと思えば、ゲームである
村 『ゲーム史』を読んで、普遍的だったり批評的な興味からの話題が多かったと思うんですが、実は僕「闘劇」が凄い好きで......。
さ とうげき?
村 格闘ゲームの全国大会で。
さ ああ、はいはい。分かりました。そうなんですか。
村 僕はニコニコ動画とか全く観ない奴だったんですが、毎日中野TRF(中野東京ランキングファイターズ/東京・中野ブロードウェイにある格闘ゲーム機の比重が非常に高いゲーセン。)の格闘ゲームの動画だけは観続けていたんですよ。
さ (笑)。そうなんだ! 意外ですねぇ。
村 中野に住んでいるので、中野TRFが近いというのもあるんですが、行ったことはあるがコミットはしてないんです。今までの話には実はその伏線がチマチマ入っていて(笑)。僕、格闘ゲームって本当に素晴らしいと思ってるんですよ。何が素晴らしいかというと、自分がやったら絶対クソゲーだと思うんですが、スト2の大会の様子をレビューして小説化した人が『ゲーム史』に出てくるじゃないですか、まさに僕もまったく同じ楽しみをこの数年していて。
さ (笑)。
村 あまりにも愚かなカミングアウトをしますが、実はこっそり全国大会の様子をSNSに小説的にレポートしたことがあります。自分しか見ない文章を眺めながら、なんていい文章を書くんだろうとか悦に入っていたんですよ(笑)。
さ 『僕たちのゲーム史』で言ったら第四章の、「プレイヤーが物語化していく」というやつですね。
村 何が素晴らしいかと言ったら、これはゲーム実況の問題にすぐ繋がるんですが、ソーシャルゲームとかカジュアルゲームって、苦労しないゲームになってるじゃないですか。時間はかかるけど。でも格闘ゲームってそれこそ50万円とか100万円とかかけて毎日毎日練習して、それでもダメかもしれないという驚くべきゲームですよね。そういう連中でスポーツのアスリートのようにしのぎを削っていく様が大会化して、それが全国から集まってきて甲子園のように闘うという様が、格闘ゲームでは組織されていて本当に素晴らしいなって思ったんですよね。たぶん、もう2010年代のゲームだからじゃなくて、90年代後半の文化ですよね。
さ そうですね。そこから始まってるものですね。
村 余談の結論としては、それがパチンコ屋に駆逐されていって、本当にムカつくな、ゲーセン潰しやがってと。こういうのに抵抗していくことが重要であって、やっぱりイベントとかもっと増やしてかなきゃいけないし、この面白さをもっと人に知って欲しいと僕は思ったわけです(笑)。
さ (笑)。そんなに好きだと思わなかったです。
村 いや、凄い好きですよ。
さ 格ゲー、あるいは音ゲーもそうですけど、コミュニティ化を図りながら、閉ざされてはいるんだけど、その小さなサークルを作ったからこそ延命したというところがありますよね。
村 そうなんですよ。これって、ゲーム観戦という文化ですよね。ゲーム観戦の文化として確立できるかどうかにこの文化の去就がかかってるんじゃないかと思うんです。
さ なるほど。
村 僕はたぶん、格闘ゲームは少年時代に流行ってたものをやったくらいで、それ以上のコミットはしてないんですが、流行った以上のコミットをしたものに音ゲーがありまして。僕、音ゲー死ぬほどやったんですよ。僕、岩手県ではランカーでした。
さ マジですか!
村 と言ってもインターネットがなかった頃なんで、地域的なランキングですが。だから毎日学校休んでゲーセン行って、僕『Dance Dance Revolution』(コナミ、1998)凄くやってたんですが、死ぬほどやりこみ、その後隣接する音ゲーを結構やったんですが、どれくらいやったかというと、一日中やってたんで足とか手とか怪我したり。もの凄い大変なんですよ。
さ (笑)。
村 寝食を忘れてやりました。徹夜もしましたし。
さ 徹夜で音ゲーやるんですか(笑)。
村 東京は条例で出来ませんけど、岩手県は全然余裕で徹夜でやってたんです。金曜の夜に行くと、遠征勢がやってきて、みんなで競いあうんですよね。で、みんなは結構パフォーマンスするんですが、僕はスコアラーだったんで淡々とパーフェクトを加算していってスコアを取りに行くというタイプでした。
さ かっけー(笑)。プレイスタイルがあるんですね。
村 だからその時は東京に遠征に来て、吉祥寺だったか御茶ノ水だったかのゲーセンに行って、ランキングのスコアネームのところ全部書き変えて帰るということをしてたんですよね(笑)。
さ そういえば梅ラボさんも、『beatmania』(コナミ、1997)とかやってて、凄いんですよね......。
村 そう、カオスラウンジ勢はみんな『beatmania』や『Pop'n music』がすっごくうまいんですよね。
さ 異様なスポーティさでやってるんですよね。
村 途中からアートと関係してくるのかもしれないですが(笑)。
さ でもね、そういう文化とか、先ほどおっしゃったゲームを鑑賞する文化みたいなものも、ひとつのゲームと言ってしまっていいと思うんですよ。プレイするということ以外に、鑑賞するという側面も含めてのゲームだと思います。あるいはそこでのコミュニケーションもゲーム。『僕たちのゲーム史』ではポケモンのところで、「環境も含めてゲームなんだ」という文章を引用していますが、もっと言えば身体的な体験もゲームなんじゃないか。『DDR』なんてまさにそういうものなので。
村 そうなんですよ。やる、見る、話題にするとかも全部ゲームで、揃ってなくてもいいんですよね。揃っててもいいところがまた面倒臭いところなんですが。
さ もはや「ゲームだと思った行為はすべてゲームだ」という感じになってきますよね。
村 それに関連する切り口として、昔はてな匿名ダイアリーでバズっていた「人生は神ゲーか」という問題があると思います。あれは人生の艱難辛苦を神バランスのゲームに例えたものですが、実際、そういうリアリティで生きている人っていますよね。大きな金を動かすビジネスマンや出世競争に励む官僚なんかもゲーム的な世界観とは無縁ではないだろうし、それこそSNSをナンパツールとして使っている人なんて完全にそういう人種ですよね。SNSの多くはナンパのために作られたものじゃないけれど、そういう風に読み替えて使うわけです。これは明らかにゲームですよね。
さ そうですね。
村 今の発想で、ゲームにはいろいろな要素がある。どれかを満たしていればいいんだと。とは言っても、コントローラーを持ってプレイするのがゲームだよという常識があったわけじゃないですか。でも常識がどんどん論理的にはがされていった結果、たとえば見てるだけでもゲームだよ、みたいなことがホントに露呈してきたわけですよね。ニコニコ動画なんてそのもので、ゲーム実況の隆盛はこれもゲームの遊び方だったんだってことをまさに定量的に示しましたよね。

『高機動幻想ガンパレード・マーチ』 発売日=2000年9月28日 プラットフォーム=PlayStation メーカー=ソニー・コンピュータエンタテインメント
そういう進歩史観を脱却した書き方をすることで、ゲームは物語だと感じている人とか、ゲームを物語として捉えることが許せないと思っている人とか、あるいはコミュニケーションのためのものだと思っている人、ゲームに対してそれぞれに考え方を持って対立するようになったということそのものをゲーム史の末尾として持ってくるようにしたんです。ここに、この本の大きな意図の一つが凝縮されているんですよ。つまり東浩紀の「ゲーム的リアリズム」みたいな達成もあり、ゲームは物語じゃないと言ってアレルギーを起こす者もいる。その全体図を描くことによってのみ、今日的な状況は俯瞰できる。「物語をどのように扱うか」というテーマは、実はそれを描くために用意されたんです。
(続く)
『僕たちのゲーム史』(星海社新書)
【さやわか氏出演イベントスケジュール】
■いまこそ語ろう『花の詩女ゴティックメード』!!
開催日:1月18日(金)
出演:金田淳子、岡田育、さやわか、矢野健二
場所:リブロ池袋本店
http://www.libro.jp/news/archive/003079.php
■メディア/アイドルミュージアム「アイドルミュージックビデオの制作法」
開催日:2月16日(土)
出演、高橋栄樹、さやわか
場所:SKIPシティ 彩の国ビジュアルプラザ 映像ミュージアム
http://mediaidol.net/?p=337
【村上裕一氏出演イベントスケジュール】
■[genron school]村上裕一 「ノベルゲームの思想」第1回(全3回)

2/15(金)より、毎月1回の連続講座(全3回)「ノベルゲームの思想」を行ないます。
明らかに連載「美少女ゲームの哲学」が下敷きとなった講座です。
チケットの購入やイベント詳細については下記サイトをご覧ください。
[genron school]村上裕一 「ノベルゲームの思想」第1回(全3回)
http://peatix.com/event/9319/
ゲンロンカフェ
http://genron-cafe.jp/
関連記事
美少女ゲームの哲学
第一章 恋愛というシステム
第ニ章 地下の風景
第三章 探偵小説的磁場
第四章 動画のエロス
第五章 臨界点の再点検
補遺
第六章 ノベルゲームにとって進化とは何か
第七章 ノベル・ゲーム・未来―― 『魔法使いの夜』から考える
第八章 美少女ゲームの音楽的テキスト
村上裕一 批評家。『ゴーストの条件』(講談社BOX)絶賛発売中!
メールマガジン"めるまがbonet"始めました。http://ch.nicovideo.jp/channel/bonten
ゲンロンカフェにて連続講座「ノベルゲームの思想」やります。
最近の仕事は『P8』(PLANETS編集部)、『ユリイカ』永野護特集/平成ライダー特集などで対談や評論を寄稿。
『Gian-ism DX』(エンターブレイン)のサイコパス特集も取材・執筆しました。
2月には新たに発足する株式会社梵天の代表に就任します。
13.01.13更新 |
特集記事
| |
| |