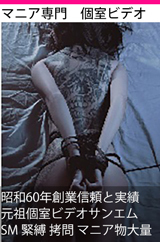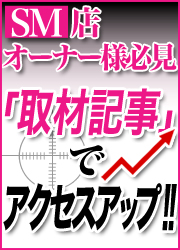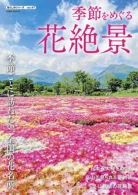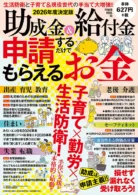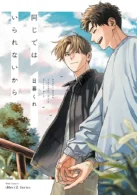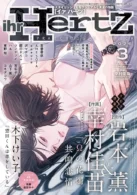月一更新!
「お絵描き文化」の特異な発達を遂げた国、日本。「人は何のために絵を描くのか」、「人はなぜ描くことが好きに/嫌いになるのか」、「絵を描くとはどういうことなのか」――。さまざまな形で「絵を描く人々」と関わってきた著者が改めて見つめ直す、私たちと「お絵描き」の原点。お絵描きに失敗はつきもの。特に着色は一番失敗しやすい上、やり直しが難しく、その痕跡も残りがちだ。
小学校の図画工作の時間、「下書きは完璧。さあ塗るぞ」と意気込んで色を塗っていった結果、「なんか違う。こんなはずじゃなかった。失敗だ......」と暗澹たる気持ちになったことを思い出す。
同じような経験のある人は、多いのではないだろうか。輪郭の失敗なら消して描き直せばいいが、色塗りの失敗はかなりの手遅れ感がある。
慎重にやっていたのに、他の色との境目で色が重なって滲んでしまったり。パレットの上ではこれだと思ったのに、絵の具が乾いたらイメージが違ってたり。一つの絵の具だけ残り少なくなって、全体のトーンが狂ったり。絵が好きでも、その時点でかなりやる気が失せてしまうもの。
色鉛筆でも水彩絵の具でもポスターカラーでも油絵の具でもいいが、予期せぬ厄介なことが起こるのは、それが物質だからだ。
絵を描くという行為は、洞窟絵画を参照するまでもなく、ある物の表面に別の物を物理的に擦り付け、その痕跡を残すところから始まっている。壁や板や紙やキャンバスその他の物質に、さまざまな顔料、塗料、絵の具などの物質を、手指や棒切れや筆などを使って擦り付けて、何らかの形象を表わすもの、それが絵。
黄色い岩肌に擦り付けられた赤茶色の粘土の軌跡。アスファルトの凹凸にひっかかっているチョークの粉。ケント紙にわずかに沁み込むインク。画用紙に滲みながら浮き上がる水彩絵の具。キャンバスから盛り上がる油絵の具。張られた絹や和紙の上に極薄の層を成す日本画の顔料。
そこで、色は物質そのものである。そして物質は、そう簡単にこちらの思い通りにはなってくれないゆえに、厄介である。
「小学校の図画の色塗りでは苦労したけど、今はペンタブ使ってるので平気です」という人もいるかもしれない。
ネットや紙媒体で目にするイラストやマンガを見ても、ペンタブレットに代表されるデジタルお絵描きツールの普及は、目覚ましいものがある。それは、手間と時間のかかる着彩において、特に効力を発揮しているようだ。
ペン、鉛筆、水彩、エアブラシ、油絵などの多彩な選択ツールがある上、さまざまな色を試すことができるし、間違えてもすぐ前の状態に戻せるし、レイヤー機能で細かなところの塗り分けもスムースだし、発光やグラデーションの効果も簡単に得ることができる。すべて、アナログお絵描きでは、入念な計画や下準備やテクニックが必要だったことだ。
デジタルにおいて、色は記号と数字に置換され、画素として現われる。そこに、取り扱いの厄介な物質としての色はない。
三次元空間において色とは、物に光が反射して見えるものであり、色と物質は常にセットだ。空が青いのだって細かなチリに光が反射して青く見えるのだから、そこにあるのは物質だ。
他方、デジタル上では色は光そのものである。私たちは、色が初めて物質と切り離された時代を生きている。デジタルお絵描きツールは、デジタルでしかできない方向に先鋭化した、新しい表現を生み出していくだろう。
話を戻して。
アナログ画材をデジタルに切り替えて、「手間がかかる」「きれいに塗れない」「やり直しがしにくい」などの悩みが解消されたとしよう。残るは自分の思ったように線を引き、形を描く描画力の差だけということになるのだろうか。
もっともそれらは、デジタルツールを使う前の段階のクロッキーやデッサンで、誰でもある程度の力量をつけているものだ。その上で、効率とよりきれいな仕上がりを求めてペンタブを使うというのが普通の順序だろう。
となると、アナログ画材で描こうがデジタルツールを使おうが残るであろう最大のネック、悩みどころは、色の選択をめぐるものではないだろうか。
あるレベル以上のかたちの確かさが備わった上で、絵の印象を左右するのは色。色の選択如何では、傑作も凡作に堕ちる。
ペンタブだったら色なんかいくらでも試せるから、必ず一番イメージに合ったぴったりの色が見つかるはず?
しかし、どれだけたくさんの色があろうと、どれだけ色の組み合わせを実験できようと、実際に人が試すことのできるのはその中のごく一部、せいぜい数十種類に過ぎない。明度、彩度、色相と組み合わせパターンは一見無限に思えても、あらかじめ選択の範囲は絞られている。そこから先は、その人の色彩感覚に左右される。
いやその、色彩感覚の善し悪しってのがよくわからないなぁという人もいるかもしれない。それは育った環境で決まるのではないか。でなければ、絵の展覧会などにしょっちゅう行って「審美眼」を磨かないといけないのでは?
確かにそういう面もあろうが、日常で学べることもあるのではないだろうか。私たちは、日常生活の中で豊富な「色の体験」を積んでいるのだから。
私たちの毎日の「色の体験」は、常に、質感や光の体験とともにある。
例えば白という色は一色しかないが、日常の中で見る白は千差万別だ。朝起きてから目にした白を、思い起こしてみよう。
朝の光が透けるカーテンの白、トーストを載せた皿の白、履き古したスニーカーの白、雨に濡れた横断歩道の白、向こうから歩いて来る女性のブラウスの白、花屋の店先の胡蝶蘭の白、配られたレジュメの紙の白、蛍光灯の下のホワイトボードの白、文字を打ち込むパソコンの画面の白、時計の文字盤の白、午後の太陽に照らされた入道雲の白、ショーウインドウに飾られた帽子や日傘の白、書店で手に取った本のページの白、炊きたての御飯の白、暗がりにいる猫の背中の白......。
すべて、白さの色味(というのはおかしな言い方だが)やニュアンスが異なるはずだ。白と一口に言っても、軽かったり重かったり、薄かったり厚みがあったり、滑らかだったりざらついていたり、冷たかったり温かみがあったり、乾いていたり濡れていたり、眩しかったり沈んでいたりする。その違いは当然のことながら、それぞれの物質の違いや、その色を見ている環境や光の違いによるものだ。
またそれらの白は、単独では存在しておらず、周囲の色との関係の中でそれぞれ「白く」見えている。つまり色は、他の色との関係において初めてその色の特徴を発揮する。だから白でも、美しく映える白もあれば、冴えなく見える白もある。隣の色と喧嘩する白もあれば、寄り添う白もある。
「この絵のここに白が欲しい」となった時、どんな種類のどんな質感の白なのか瞬時にイメージできる人は、こうした「色の体験」を頭の引き出しにたくさんストックしている。色彩感覚とは、色と色の関係性を多角的に把握する感覚と言える。ここには年齢や性別もいくらか関わってくるだろう。
個人的な話を書くと、幼少時の私にとって、ピンクや水色はきれいな色で、茶色や灰色はどっちかというとあまり使いたくない汚い色だった。方眼紙の升目を好きな色で埋めて形を作る遊びをした時、ピンク、赤紫、紫、藤色、青、水色の色鉛筆を使って、紫陽花の花のようなモザイク絵を作り、周囲の大人に褒められた。
そんなこともあって、自分の色のセンス、「自分の世界」には子どもの頃から何となく自信を持っていた。が、思春期に美術を志した時、マチスの絵の色遣いがどうしてもピンとこなかった。色の魔術師と言われたあのマチスなのに! 当時の私には、自分の美的感覚をはるかに超えた、摩訶不思議な配色に見えたのだ。
マチスの配色の凄さが、じわじわわかってくるまでには、数年かかった。世の中に「汚い色」も「きれいな色」もないことも、やがて実感としてわかった。色は、組み合わせによって美しく見えたりそうでなかったりするだけだし、それも素材とシチュエーションによって変化するということを、私は生活体験の中で学んでいった。
色を質感とともに感知しつつ、周囲の色との関係の中で認識する。そして好みに合ったり気になったりした配色を、脳のどこかに記憶する。そんな複雑なことを、私たちは毎日無意識のうちにやっている。そこでおのずと、それぞれの色彩感覚が作られている。
もちろん色を非常に意識的に扱うこともある。たとえば、服の色合わせで悩んだことのある人なら、わかるのではないだろうか。全体をベージュ系でまとめたいと思っているのに、一つだけ微妙に色味が合わない、それは素材感がマッチしてないからだと気付く。
さらには、このくらい重量感のあるグリーンのスカートなら、もっと淡い紫のブラウスのほうが引き立つとか、この黒にこのピンクの組み合わせはどぎついけど、こっちの艶消しのピンクならOKだ、などと感覚的に判断したりする。
料理も「色の体験」の宝庫だ。食材の彩りはよく言われることだが、食器との関係も大きい。
秋刀魚の塩焼きをツルッとした真白な皿に載せるとよそよそしいが、ざっくりした質感の皿だと美味しそうに見えるとか。いつも木製のボールに盛っているサラダを、真っ青なガラスのボールに盛ったら新鮮に見えたとか。
ファッションでもインテリアでも雑貨でも製本でも建築でも、およそ色のデザインが関係するジャンルで、配色と質感の関係は非常に大きなテーマである。
何かを見ては、「この色のコーディネート、素敵」と感動したり、「この配色はいまいちだね」などと反応している時、その人の中で色と物質はわかちがたく結び付いている。
色は、純粋にその色単独であるのではない。この三次元空間で色は常に物質の色として現われ、他の色=物質と共存している。
絵を描く人々は、そういうことを一般の人よりも実体験としてよく知っているのだ。なぜって、あの取り扱いが厄介なアナログ画材で、物としての色彩と向き合ってきたからだ。
鉛筆を尖らせて描いた時のピリピリ緊張する線や、描き込んで底光りしてくる鉛色の物質感。クレパスが画用紙の細かい凹凸を拾っている手応えと、力を込めて塗った時のコッテリした感触。
色鉛筆を何色か薄く重ねていったらセーターの風合いに見えてきたり、水彩絵の具の滲みから偶然できた模様がプールの底を連想させたり、うっかりポトンと落としたポスターカラーの色の鮮烈さに、ハッとしたりする。
画材それぞれの物質が生み出す、色のさまざまな貌。デジタルではすぐに修正できる色むらや、色の重なりやぶつかり合い、はみ出しや滲み。偶然の出来事は一面では「失敗」だが、別の一面では思いがけない方向に絵を作っていくきっかけとなる。
自分の色彩感覚の下でコントロールされていたはずの「自分の絵」が、初めて見るようなものに変わっていく時、色彩感覚は更新される。そこで絵を描く人々は、絵が何か具体的なイメージの表現である以前に、色と物質の果てしない実験場であることを体感するのだ。
庭に落ちて冷たくなっていた雀の雛。巣立ちに失敗してしまったのでしょうか。雨に打たれていたために、毛がずいぶん乱れていました。生前の姿をまだ留めつつ、刻一刻と「物」に近づいていく亡骸。プロの画家なら肚を括ってもっとじっくり仔細に描くのかもしれませんが、私の中には妙な恐れ戦きがありました。すみません、急いで描かせて頂きますね、という。なのでやや性急なタッチになっています。デッサンの後、庭の隅に埋めました。合掌。
絵・文=大野左紀子
関連リンク
絵を描く人々
第1回 人は物心つく前に描き始める
第2回 「カッコいい」と「かわいい」、そしてエロいvs
第3回 絵が苦手になる子ども
第4回 美大受験狂想曲
第5回 人体デッサンのハードル
第6回 演出と詐術の世界にようこそ
第7回 自画像と似顔絵をめぐって
第8回 ヘタウマの功罪
第9回 絵が描けるといい仕事
第10回 描くことの光と闇
第11回 絵を描くおばあさん
第12回 日本・お絵描き・女の子
第13回 「欲しい絵」と「なりたい絵」
『あなたたちはあちら、わたしはこちら』公式サイト

大野左紀子 1959年、名古屋市生まれ。1982年、東京藝術大学美術学部彫刻科卒業。2003年まで美術作家活動を行った後、文筆活動に入る。
著書は『アーティスト症候群』、『「女」が邪魔をする』、『アート・ヒステリー』など
著書は『アーティスト症候群』、『「女」が邪魔をする』、『アート・ヒステリー』など
17.06.03更新 |
WEBスナイパー
>
絵を描く人々
|
|