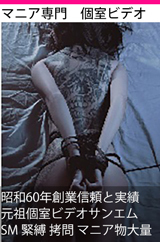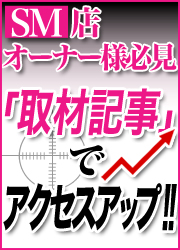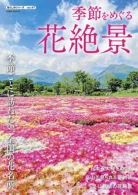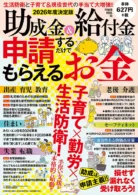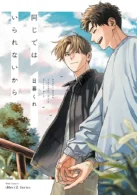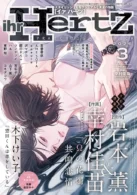月一更新!
「お絵描き文化」の特異な発達を遂げた国、日本。「人は何のために絵を描くのか」、「人はなぜ描くことが好きに/嫌いになるのか」、「絵を描くとはどういうことなのか」――。さまざまな形で「絵を描く人々」と関わってきた著者が改めて見つめ直す、私たちと「お絵描き」の原点。最初に、ちょっと「絵を描くこと」を離れて考えてみたい。個性って、一体何でしょうか。自分の個性は何か、あなたはちゃんと把握していますか?
実は私はこの歳になっても、自分の個性がどういうものかよくわかっていない。自分の好き嫌い、趣味嗜好については把握している。癖や言動・考え方の傾向もだいたい自覚している。しかし「あなたの個性は?」と言われると、はて......と考え込んでしまう。
人に「それはやっぱり大野さんの個性だね」などと言われれば、「そういうもんかな。うん、そうかもしれない」と消極的に納得はするけれども、確信は持てない。率直に言って、私の個性は私にとって「謎」である。
その反面、人の個性は自分のより見えやすい。この時の「個性」とは、「あの人すっごい個性的!」といった目につきやすい特殊性のことではなく、個々のパーソナリティのことだ。
パーソナリティとは、心理学では気質・性格・能力の三要素の複合体を指す。持って生まれた気質と、環境に影響を受けやすい性格や能力を合わせて、その人のパーソナリティ(=個性)が生まれる。
これは「あの人すっごい個性的!」と区別するために、むしろ「個別性」と言ったほうがいいかもしれない。まったく同じ気質・性格・能力を持つ人は2人といない以上、人は皆個別的であり、その意味においては「誰でもその人なりの個性をもっている」とも言える。
ところで、個性という言葉は教育の場でよく聞かれる。「子どもの個性を伸ばす」、「個性的な子どもに育てる」など。
と言っても、たとえばクラス40人の子どもを全員「すっごい個性的」と言われるような強烈なキャラクターにしようということではないし、そんなことは実際起こりえない。
要はそれぞれの子どもの興味・関心のありどころを探り、それを肯定し、好きにさせ、褒め励まして得意にさせる。短く言えば「その子の得意分野を伸ばしてやりましょう」という意味で使われているようだ。勉強でも運動でも学級・クラブ活動的なことでも趣味でも、一つ得意なものができれば自信もつくし、それによって苦手なことにトライしようという余裕も生まれるかもしれない。
ただし、言い出したら聞かないのでその強情っぱりな個性を伸ばそうとか、集団に馴染めないらしいのでその孤独な個性を育てようとかいうことではない。
「個性を伸ばす」とは、その子どもの持つ何らかの能力の可能性を、その子の気質や性格を踏まえて育てるということであり、そこでの「個性」は、人々と共生しつつ社会を生きていくためのパーソナリティ形成の一部とされている。
これが美術教科になると、少し事情が違ってくる。
まず美術、芸術の世界ほど、個性が重要視される世界はない。そういう共通認識は行き渡っている。ここでの個性はまさに「個性的!」と言われるような際立ったものを指す。美術の世界での「個性がある」は単に個別性ではなく「面白い」とほぼ同義であり、それは「絵が上手い」などよりずっと上位に位置付けられる。
いや、中学校の時の美術の先生、普通に上手い生徒ばっかり褒めてたけどなぁという声もあるかもしれない。勝手に構図や色を指定してくる先生もいたけどなぁ、と。美術は教員によってかなり授業内容が左右される教科なので、そういうケースはままあろう。
しかし教科の建前としては、「子どもの豊かな個性と創造性を育成する」ということになっているのだ。その大目標のベースには、これまでのアートの歴史は「豊かな個性と創造性」をもつ芸術家によって脈々と担われてきたではないか......というこれまた大きな、なかなか否定しにくいテーゼがある。
学校教育ではともかくとしてもアートの世界においては、「言い出したら聞かない」ような「強情っぱりな個性」がなければならないし、「集団に馴染めない」ような「孤独な個性」こそ芸術家のものとされてきた。誰かに意見されてコロコロ方針を変えていたり、みんなと同じようなことをしてないと不安、ではダメなのだ。
アートの世界で個性的、個性があるとは、言い換えれば「独自性が感じられる」「オリジナリティがある」ということ。この考え方は、巷の「絵を描く人々」においてもほぼ共有されているのではないだろうか。
では、どうしたらそういう個性的なオリジナリティ溢れる絵が描けるのだろうか。
自分なりに一生懸命描いていれば、個性なんて誰でも自然に出てくるのでは? 残念ながらそれは多くの場合、「個別性」に過ぎない。絵を描けば、その人のパーソナリティは何らかのかたちで現われるということであって、それがすなわち独自性があるということにはならないのだ。「その人らしい」ということと、「オリジナリティがある」ということとは別の話である。
その人らしさで満足するか、オリジナリティある絵を描きたいか。少し別の回路から考えてみよう。
際立ったオリジナリティを見せた芸術家は誰かと聞いたら、多くの人はピカソと答えるだろう。それからゴッホ、ゴーギャン、マチス、ダリ、デュシャン、といった近代から現代にかけての芸術家が上がるだろう。
もちろんダ・ヴィンチやミケランジェロやデューラーやカラヴァッジョなど、近代より前にも独自性を発揮した芸術家は多いが、西欧美術に関して言えば、ギリシャ神話とキリスト教の影響力は無視できないものがあったし、絵は基本的にはパトロンの求めがあって描かれるものだった。
そうした制約がなくなり、モチーフの選択から何からすべてが画家に委ねられた近代以降のアートは、まさにオリジナリティが命脈となった。
そこでのオリジナリティとは絵で言えば、絵を作っていく新しい方法論を指す。
対象を筆の筆致に置き換えるのも、立体感をあえて無視して平面的に描くのも、面によって対象を組み立てるのも、物を断片化して配置するのも、再構成するのも、それまでになかった方法だ。それらは、新しい世界の見方、感じ方から編み出された。「こんなふうに世界が見えるのか」「こんなリアリティがあったのか」と気付かせるようなものが、オリジナリティと言われてきたのだ。
いやはや、オリジナリティのハードルは高い。ちょっとやそっとでは出てきそうにない。
だいたい「新しいもの」なんてもう散々やり尽くされて、先人のやったことを組み合わせたりアレンジしたりして少しでも「目新しさ」を狙っているものが多いじゃないか。
ただ絵が好きで描いているんだから、「自分らしさ」が出ればそれで充分だ。自分らしく、自由に楽しく描きたいんだ。だって別にアーティストになりたいんじゃないんだもん。いやその気持ち、よくわかる。
ちょっと私的な話をさせて頂きましょう。
子どもの頃クラシックのピアニストを目指していた私は、中学2年で挫折した。基礎的反復練習の繰返しにうんざりして、暇さえあれば即興で遊びっぽく弾いたりしていたので、こんなんじゃプロは無理だということになったのだ。
人の作った曲を人より上手に弾くのにアクセクするなんて......と私はピアノを投げ出し、「自分の個性」が発揮できそうな美術に進路を変えたわけだが、アカデミックな学校世界では美術においても基礎トレーニングが重要視された。トレーニングとは、見方の型、描き方の型を習得することだ。
見て描く、記憶で描く、線だけで描く、点や面で描くなどなど、いろんな画材を使ってさまざまな方法で描いてみることからそれは始まった。人のスタイルを真似してみたり、模写もしたりして、絵にはたくさんの型があることを知った。
トレーニングというと石膏デッサンの反復みたいなものを想像するかもしれないが、そればかりではない。トレーニングというものの幅は広い。そしてとりあえず、自分らしさとか個性などということは考えなくていい。
その後、彫刻のコースを選択したので絵を深く追求はしなかったけれども、基礎トレのお陰で大概のものは大体自分の思ったように描けるようになり、それをアレンジしたりもできるようになった。
そして、ああこれはピアノと同じだなと思ったのである。基礎の反復練習をある程度積んで指が自由に動くようになっていたお陰で、私は自分勝手な即興演奏も楽しめていたのだなと。
オーソドックスに普通に描ける、そして少し違う感じにも描けるとは、こうしたいなと思うように手が動くということだ。
こうしたいなと思っても、そのように手が動かせないのは、さまざまな動かし方をまだ充分にしていないからだ。
一握りの天才を除いて、いつまでも自由闊達に描ける人はいない。大抵はしばらくすると頭打ちになる。好きに描いているつもりでも、それは一つの型の反復でしかない。自分のやっていることがつまらなくなり、やっぱり絵なんて才能ないとダメだなと思ってしまう。
でもその前に、さまざまな方法を学び、さまざまな型を知り、自在に手を動かせるようにしておいたら、それはずっと後で、自由に楽しく描く場面に効いてくるのではないだろうか。
その時はもう、方法や型のことなんかいちいち気にしなくていい。むしろ忘れてしまったほうがいい。
そしてある時、「個性的だね」と言われるようになっているかもしれない。
一カ月以上前に花屋で求めた、数本の薄いピンクと黄色のカーネーション。活けたまま萎れていったのをずっと放置していたら、すっかり水気が飛んで枯れました。もともと縮れた花びらが、さらに縮れて収縮して固まってます。萼(がく)の少し下のところで切ってテーブルの上に転がしてみると、時代劇などに出てくる斬首されて色を失った人の首のよう......。切られた花と首。単なる連想でしょうか。でも物は、別の物にも見える瞬間がありますよね。描いたのは一つの花を三方向から眺めたところ。少し角度を変えると、違う形や表情が現われて面白かったです。描いたものを見たら今度は、クシャクシャに丸めた紙くずのようにも見えてきました。
絵・文=大野左紀子
関連リンク
絵を描く人々
第1回 人は物心つく前に描き始める
第2回 「カッコいい」と「かわいい」、そしてエロいvs
第3回 絵が苦手になる子ども
第4回 美大受験狂想曲
第5回 人体デッサンのハードル
第6回 演出と詐術の世界にようこそ
第7回 自画像と似顔絵をめぐって
第8回 ヘタウマの功罪
第9回 絵が描けるといい仕事
第10回 描くことの光と闇
第11回 絵を描くおばあさん
第12回 日本・お絵描き・女の子
第13回 「欲しい絵」と「なりたい絵」
第14回 色についてのいろいろな悩み
第15回 写真を見て描く、実物を見て描く
『あなたたちはあちら、わたしはこちら』公式サイト

大野左紀子 1959年、名古屋市生まれ。1982年、東京藝術大学美術学部彫刻科卒業。2003年まで美術作家活動を行った後、文筆活動に入る。
著書は『アーティスト症候群』、『「女」が邪魔をする』、『アート・ヒステリー』など
著書は『アーティスト症候群』、『「女」が邪魔をする』、『アート・ヒステリー』など
17.08.05更新 |
WEBスナイパー
>
絵を描く人々
|
|