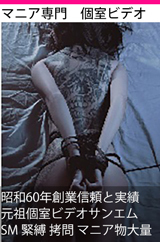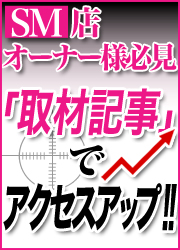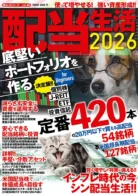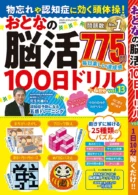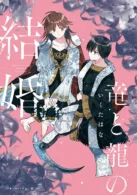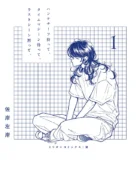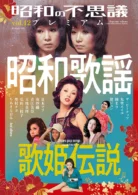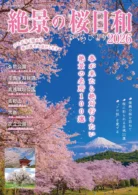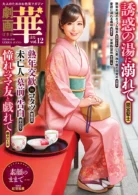月一更新!
「お絵描き文化」の特異な発達を遂げた国、日本。「人は何のために絵を描くのか」、「人はなぜ描くことが好きに/嫌いになるのか」、「絵を描くとはどういうことなのか」――。さまざまな形で「絵を描く人々」と関わってきた著者が改めて見つめ直す、私たちと「お絵描き」の原点。物心ついた頃には、絵を見るのが大好きになっていた。幼い頃の私にとって絵とはまず「きれいなもの」。人でも動物でも花でも風景でも、絵の中にあるものは現実よりずっと多彩で美しく、幼い私に向かって無言のうちに語りかけてきた。
最終回となった今回は、「絵を描く人々」の一人だった自分の幼少から少女時代を中心に振り返りつつ、「私は絵を描くことで何を見たかったのか」を探っていきたい。
何を「美しい」と思うか、その美意識には当然、文化の刷り込みがある。引目鉤鼻は平安美人の条件だったが、欧米文化に慣れている私たちには「おかめ顔」にしか見えない。
一方、時代や文化にかかわらず多くの人に「美しい」と思わせるものもある。それはその表現が、時代や文化の波を越えて生き残り、一つの「美」の基準となったからだ。
子ども時代の私に影響を与えたビジュアルは、ディズニーアニメ、絵本で見た初山滋、武井武雄、いわさきちひろ、長新太などの挿絵、藤城清治の影絵、中原淳一や高橋真琴のイラスト、父の持っていたヨーロッパ古典絵画の画集など。やはり時代と文化、環境の影響が色濃い。
とにかく暇さえあれば、それらの気に入った絵を何度も隅から隅まで舐めるように眺めて過ごした。どの絵も私一人に向かっていろいろなことを囁き、目配せしてくる。その中に浸るのは、憧れとも陶酔とも興奮ともつかない悦楽だった。絵に没入することで、厭なことも忘れ心地よくなる状態というものに、私は早い時期に嵌ったのだった。
現実の世界で「美しいもの」はそう簡単には見つからない。しかし絵の世界にはそれがたくさんある。まだまだ自分の知らない「美しいもの」、とびきり「美しいもの」があるに違いない。
そんな単純な動機の陰には、自分が「女の子」で「美は女性の特質」というジェンダーを知らず知らず学んでいた事情も、深く関係していただろう。
とりわけ「美しい顔」の描かれた絵を見るのが好きだった私の中には、「自分もこんなふうに美しくなりたい」という欲求と、女であろうと男であろうと美しくリアルに描かれた顔を遠慮なくいつまでも眺めることの快楽や性的興奮が入り交じっていた。
ただ眺めているのに飽き足らず、自分でも描きたいと思うようになった。小学生くらいの女子の多くが、可愛い女の子の絵を描きたがる現象について以前触れたが、私もその典型だ。
家ではマンガを禁止されていたので、友達の家で読むのが常だった私の脳に、甘く華麗な色彩や流れるような線描のニュアンス、誇張と描き込みと省略の妙は、確実にインプットされていった。
母の読んでいた洋裁の雑誌や婦人雑誌にも、大人っぽい「美」が溢れていた。モードでも料理でも優れたグラビア写真には、思わず見入ってしまうような吸引力がある。現実より美しく現実を写した写真。これは何なんだろう、魔法みたいだと思った。
雑誌から画集まで、飽きるほどそうしたビジュアルを眺めてさまざまな情報が知らぬ間に脳にストックされていたせいか、しばらくすると自分なりに満足のいく絵が描けるようになった。
いろんな材料から得たヒントを元に、私は自分の幼い美意識に忠実に従って絵を描いた。それらはもちろん全部借り物の組み合わせでできていたけれども、人に褒められて、ますます描くことにのめりこんだ。
だがそのうち、あることに気づいた。自分が「美しい」と感じ深く惹かれる絵は、ただ単純に「美しい」だけじゃない。どこか「不思議」なところがあるということに。
その最初のきっかけは、パウル・クレーの絵画だった。そこに「美しい顔」は描かれていないし、色や線の使い方も少し変わっている。なのにとてつもなく魅力的。こういう「美しさ」というものがあるのかと、小学生の私は感動した。
クレーの隣にはカンディンスキーがいて、さらにムンクやクリムトを知った。当時の私の貧しい語彙では「美しいっていうのとはちょっと違うやつ。なんか不思議な感じのやつ」。
美術に進路を定めた頃、シュルレアリズム絵画に嵌った。絵を描く少女でシュルレアリズムに一時心酔しない人はいないのではないか?と思うくらい、10代半ばの心にそれらの不条理な情景や冷え冷えとした叙情は深く沁みてきた。
自分の惹かれる「なんか不思議な感じのやつ」があらゆるバリエーションであったシュルレアリズム。「私が本当に見たかったのはこれだ」と思った。
シュルレアリズムの絵画では、「不思議なもの」はしばしば「不気味なもの」に隣接していた。「不気味なもの」だけを直に見ることは難しいけれども、「不思議」という膜を通してならかいま見ることができる。
自分が惹かれるのは、単に「美しい」でも単に「不思議」でもなく、「不思議」を通して見る「不気味」ではないか。それがいつのまにか、最初に惹かれていた「美しいもの」とは違う別種の「美」に変容する。そういう瞬間を味わうために美術というものはあるのだ。16歳の私はそう確信した。
ところで「不気味なもの」とは、フロイトの有名な論文のタイトルである。そこでフロイトは「不気味なもの」を指して、「慣れ親しんだもの」が一度抑圧を受けて再帰してきた姿だと述べている。
実はよく知っているものだが、普段は目を背けて意識しないようにしているもの。それが期せずして現われ人を不安にさせる例として挙げられているのは、なぜか同じことが繰返し起こる現象、偶然の一致現象、ドッペルゲンガー、まるで生きているような人形、幽霊など。
じゃあ幽霊や人形の絵を描けば「不気味なもの」を表現した絵になるかというと、そうではないのだ。そんなふうに正面切って物象化してしまったとたん、「不気味なもの」はどこかに消えてしまう。
ギョッとするのは一瞬で、「それ」だとわかった時点でよく知っている凡庸なものになり下がる。
「不気味なもの」とは、抑圧が緩んだ時に無意識にあるものが別の形で現われるもの、夢の中で出会うものという言い方もある。フロイトの精神分析から強い影響を受けたシュルレアリズムの作家たちは、無意識としての「不気味なもの」を捕まえようとさまざまなチャレンジをした。無意識そのものを表現することはできないから、それは「不気味なもの」に限りなく接近しようとして失敗する試みだった。
当時の私にまだそういう知識はなかったし、考察もできなかった。そして日々、非常にオーソドックスなデッサントレーニングと課題に明け暮れ、シュールな絵にトライしてみる余裕もほとんどなかった。スケッチブックの隅に時々落描きするのがせいぜい。
そうこうするうちに、絵画ではなく彫刻コースで芸大に進学することを決め、私は本格的に絵を描くことから離れていった。絵は上手いほうだという自負はあったが、倍率の高い東京芸大の中で一番競争の激しい油画科に合格するほどの画力がないのはわかっていたので、若干倍率の低い彫刻科を選んだのだ。
彫刻にももちろん興味はあったけれども、とにかく芸大に入らねばという「圧」が、内外ともに高かった。高校を出て別の大学に進学するか働きながら絵を描いていくという選択がその時許されていたら、その後の経路は変わっていたかもしれない。
結局、私は割り切ることにした。絵を描くのは描きたいとさえ思えばいつでもできる。紙と鉛筆から始められる。歳をとってもやれる。別に画家になる必要はない。自分と絵との付き合いはそういうものでいいんじゃないかと。
芸大在学中に描いた絵は、すべて彫刻を作るためのクロッキーやデッサンに終始した。一枚だけ、バイト先の美術系予備校で銅版画の講座に参加した時、気楽に描いた下絵に普段やっていることとは別のものが現われた。その刷り上がりを見た講師は、「大野さんは彫刻しか見たことなかったけど、こういう世界もあるんだね」と言った。
その作品は、エロ要素を盛り込んだ女体をメインに、日常のいろんなアイテムや記号を空中に散りばめた、どことなく往年の横尾忠則風のシュールでポップなものだった。下絵を構想するのがとても楽しかったことを覚えている。
その時、私はやっぱり絵を描くのが好きだなと思った。「絵画に取り組む」という姿勢ではなく、気楽なお絵描きが好きなんだと。
大学を出てからの作家活動は現代アートに接近し、絵の要素は空間全体を使ったインスタレーション作品の中に組み込まれた。20年経って作家活動を停止しものを書くほうに移行してからは、ごくたまに人に頼まれてデッサンやイラストを描く程度になった。
その中で、オーソドックスなデッサン技術だけはずっと私の絵の土台にあり、それはもう取り除こうとしても取り除けないものになっている。
一方、自分が絵を見る時に求めるものは、16歳頃からほとんど変わっていない。「美しいもの」「不思議なもの」「不気味なもの」を頂点とする三角形の中で、何かが突出してくることをいつも待ち望む。しかしそれが一旦認知されてしまうと、最初の衝撃は見る間に薄れていくことが多いということも実感している。
最後に、私が一度だけ「不気味なものが発現した瞬間だった」と感じた話で締めくくりたい。
この連載の第7回「自画像と似顔絵」の終わりのほうで、当時死期の迫っていた父の肖像デッサンを、母のために描いたエピソードを紹介した。父が元気だった頃の小さな写真を見ながら鉛筆で描いていって、「ちょっとまだ似てないな、まだだなーと思いながらあれこれやっていって、ある時点から突然、嘘のように似てくるのが面白い」と。
たしかに面白いのだけど、「嘘のように似て」きた時、まるで自分が描いたのではない感じがして、手が止まった。絵のほうが勝手に父の顔に擬態したような気持ち悪さを覚えた。絵でもなく実物でもない何かがそこに現前していた。私はその時「不気味なもの」に出会っていたと思う。
もちろんそれは一瞬のことで、「描く人」である私はすぐさま、「もっと描き込んでもっとそっくりにしたい」という欲求の虜となって再び鉛筆を動かした。
気味が悪いほどそっくりに描けてしまった絵は、やはり母を一瞬たじろがせた。絵を見るなり、口に手を当てて目を見開いた時の彼女の顔は、見てはいけないものを見てしまった人の顔のようだった。
絵を描く人々は、それぞれの美意識や感受性に従ってモチーフやテーマを選ぶ。そしてそれぞれに合った媒体と描画材料を使って絵を描く。描くのにはそれなりの時間がかかるから、描きかけの絵を何十回何百回となく見直しながら、手を動かしていく。
そして、ふと気づくと絵がこちらを見ている。
絵を描く人々を捉える「不気味なもの」とは、自分が絵を描いているはずなのに絵に自分が描かされているような、自分が絵を見ているのに絵のほうが自分を見ているような、主客の転倒の中に現われるのではないか。
絵という自分だけの小さな支配圏で思うがままに振る舞ってきたことの延長線上に訪れる、絵が自らの手を離れて見知らぬ別の何かになり、こちらを見返す瞬間。それがいつ到来するか予測はつかない。でも絵を描く人々、いや絵を描くことにのめり込んでしまった人々なら、一度は体験しているのではないだろうか。
そんな深い穴に落ちてみたいものだと、日常的に絵を描かなくなった今でもたまに思うのだ。
カンディンスキーがまだ具象的な絵を描いていた頃、ある日、帰宅した彼は、アトリエの片隅に「神秘的な輝きに満ちた美しい作品」が立てかけてあるのに気づきました。驚いてよく見ると、たまたまキャンバスを横向きにして置いてあった自分の描いた馬の絵。見慣れたものを違う角度から見た時、「美しいもの」「不思議なもの」が現われたという例ですね。さて今回は、本文の最後に触れた父の顔のデッサンを、目の部分を中心に切り取り、天地をひっくり返してみました。「なんだこれ?」と一瞬でも感じて頂けたでしょうか? 「不気味なもの」は描けません。でも、普通に見えるものがたまたまひっくり返っていたという偶然性の中に、それが発現することがあるかもしれません。
絵・文=大野左紀子
関連リンク
絵を描く人々
第1回 人は物心つく前に描き始める
第2回 「カッコいい」と「かわいい」、そしてエロい
第3回 絵が苦手になる子ども
第4回 美大受験狂想曲
第5回 人体デッサンのハードル
第6回 演出と詐術の世界にようこそ
第7回 自画像と似顔絵をめぐって
第8回 ヘタウマの功罪
第9回 絵が描けるといい仕事
第10回 描くことの光と闇
第11回 絵を描くおばあさん
第12回 日本・お絵描き・女の子
第13回 「欲しい絵」と「なりたい絵」
第14回 色についてのいろいろな悩み
第15回 写真を見て描く、実物を見て描く
第16回 個性と型
第17回 構図と余白
『あなたたちはあちら、わたしはこちら』公式サイト

大野左紀子 1959年、名古屋市生まれ。1982年、東京藝術大学美術学部彫刻科卒業。2003年まで美術作家活動を行った後、文筆活動に入る。
著書は『アーティスト症候群』、『「女」が邪魔をする』、『アート・ヒステリー』など
著書は『アーティスト症候群』、『「女」が邪魔をする』、『アート・ヒステリー』など
17.10.07更新 |
WEBスナイパー
>
絵を描く人々
|
|