

「はぁ......」
男に尋ねられ、曖昧な返事をしたこの宿の女将は、差し出された名刺を前に、あきらかに狼狽していた。
女将とはいっても、まだ若い。少女とまではいかないが、まだ20歳を出て間もなく見える。
だがその表情や、急なできごとに対処しなれていないことが察せられるおどおどした目つき、硬さの残る着物姿などは、やはりそれほどの年には達していないことを語っていた。あどけないといっても差し支えない。
男のほうは、年齢は20代後半から30代ほどだろうか。痩せた体つきで、浴衣をだらりと着た姿は、単なる湯治客に見える。
<有明不動産・土地開発部/眉月一郎>
それが、名刺に書かれた男の肩書と名前だった。
眉月が切り出した話は、本来ならそれなりに堅苦しい場所を選んでされるべき内容だった。少なくともここのような、さびれた温泉宿の帳場でするような話ではない。
黙りこんでしまった女将を前に、眉月は目だけ動かして、あたりの様子を窺った。帳場はまるで営業をしていないように薄暗かった。
帳場だけではない。ここは宿全体が休業状態に入り、ひっそりと息を止めているかのような場所だった。じっさい、眉月は、昨日から女将以外の人影を目にしていない。それでいて三和土や廊下、柱、帳場台、周囲の調度品などは客の目を気にするようによく磨かれているのが、何ともアンバランスだった。
あたりで鳴きかわす野鳥の声や、渓流のせせらぎが聞こえてくる。
女将は名刺から、ふたたび男に視線をもどした。
眉月が話した内容はこうだった。特急電車の開通に合わせて、彼の会社では、この地域一帯に大規模なレジャー型温泉施設を建設したいと考えている。そのためには、一軒だけぽつんと建っているこの温泉宿に立ち退いてもらわなければならない。納得してもらえる金額を出す用意はあるから、廃業を前向きに検討してもらえないか......。
眉月は最初、知り合いの紹介でこの人知れぬ秘湯的な宿に湯治に来たのだと女将に語ったが、こっそり視察するのが目的だった。宿側の反応を窺うべく、ためしにさわりだけ持ちかけてみたのだ。
有明不動産はこの不景気の時代にあって、古株を押しのけて業績を伸ばしている新進の総合不動産会社だ。帳場には今朝の新聞が、一般紙の地方版と、地方紙と、なぜか経済新聞まで置かれていたし、昨夜は奥の部屋からニュース番組の音声もしていたので、世事にまったく疎いわけではないだろうと、眉月は踏んでいた。
「10月といえば観光シーズンまっただ中ですけど、今月はこれからお忙しくなるんですか」
「はい......あ、いいえ。まだ多少、余裕はあります」
「多少ですか、すごいなぁ。特に観光名所があるわけでもないし、交通の便だってよくないのに、昔ながらの湯治だけのスタイルでやっているなんて。やっぱり常連さんが多いんですか」
「えぇ、まぁ......」
眉月は何か考えこむようにちょっと首をかしげた。
「僕、湯治初心者なんですよ。せっかくだから常連さんにいろいろ教えてほしいなぁ。僕の10日間の滞在中に、そういうお客さまがいらっしゃるご予定はありますかね」
「いえ、今のところ特に予定は......」
「まぁ、常連さんじゃなくてもいいんですけど」
眉月が笑うと、女将のほうはまた口をつぐんでしまった。
眉月の誘導の仕方は巧妙だった。女将はすでに、身よりや頼りにできそうな親戚がいないことまで、ぽろぽろと取りこぼすように喋っていた。
「やめたい気持ちも、なくはないのですが......」
やがて、女将が追いつめられて仕方なくといったように呟いたのを、眉月はとうぜん逃さなかった。
「何かやめられない理由でもあるんですか」
「それは......」
女将は躊躇していたが、「座敷童でもいるとか」と冗談めかすと、はっと息をのんだ。
「あの、信じていただけないとは思いますが......この宿には、いるんです」
「座敷童が?」
嘘から出たまことにしても、あまりにも突拍子もなさすぎる。眉月は目を丸くした。
「あの、棲みつく家に福をもたらす......ってやつですよね」
「はい。この宿にはもう何代も前から、その座敷童の女の子が住んでいるんです。この宿がなくれば、その子も消えてしまうでしょう。その子がそんなことを受け入れるかどうか......それに、あの、何より......かわいそうですし」
女将は上目でちらちらと眉月を窺いながら話した。いつ噴き出されるか怖れているふうである。
「その座敷童には、私も会えますかね?」
「えっ?」
女将は睫毛をぴくんと跳ねあげて、驚きを隠そうともしないまなざしを眉月に向けた。
「いえ、ただの好奇心なんですけどね」
「......わかりません、気まぐれですから。私だって、会いたいときに会えるわけじゃないんです」
まさか、こういう反応が返ってくるとは思ってもいなかったのだろう。女将はどもりながら、言い訳でもするように答えた。眉月は本人の言うとおり、好奇心を練り上げて固めたような笑みを浮かべていた。
「まぁ、そういうものですよね。じゃあ会えたら幸運、というぐらいに考えておきます」
柱時計が午後4時の鐘を打った。眉月は何も返せないでいる女将を残し、軽く頭を下げて帳場を去ろうとしたが、数歩進んだところで、「あ、そうだ」と立ちどまった。
「よかったら近々、東京の本社に一度いらっしゃいませんか? いろいろと資料をお見せしますよ」
「東京......?」
女将は一瞬、顔をこわばらせた。
「ありがたいお申し出ですが、私はあまり遠出ができないんです。ここの人手がつねに足りていない状態で」
「そうですか」
こんな山奥で日々暮らしているから、きっと恐ろしいか面倒か、都会に対して肥大したよからぬ印象を抱いているか、そんなところだろうと眉月は思った。
彼は今度は振り返らず、悠々とその場を離れていった。
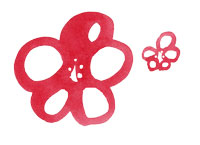
宿の名は「大瀧屋」といった。敷地内には本館と別館のふたつがあったが、今は別館しか使用していないらしい。
眉月は暇にまかせて、築50年はくだらないであろう本館のまわりを何度か回ったが、時代を感じさせる厚い色ガラス張りの入り口には鍵がかけられ、しかもその鍵には錆が浮いていた。ただ、扉は洋風なのに唐破風の玄関を持った入母屋造の建物や、窓からわずかに覗くことができた格天井の広間などからして、かつては大いに隆昌し、それを惜しみなく投資していた時代もあったのだろうと推測された。外側から見るかぎりは3階建てのようだ。レジャー施設をつくる際には、このまま利用できるかもしれない。
別館は部屋数10にも満たない民家風建築だったが、それでも眉月の部屋は本間10畳に次の間2畳、床框(とこがまち)を漆仕上げにし、付書院のついた床の間まである造りだった。襖に描かれた繊細な筆の椿も悪くはないし、掃除も行き届いている。
浴場は本館と別館のあいだに独立して作られた専用の建物の中にあり、タイル張りの風呂に湯が満たされているだけの、質素だが清潔なものだった。利用の際にはいったん別館を出、庭を横切って行く。さすがに手に余るのか、庭だけはほとんど整備されていなかったが、それが荒削りな野趣ともなっていた。
しかし......。
――どうも、陰気なんだよなー。
部屋にいても館内や庭、浴室棟をうろついていても、眉月はそんな印象を拭うことができなかった。
あからさまに怪しい物があったり、不審な人物や生き物がいるわけではない。建物全体にうっすらとそんな雰囲気が漂っているとしかいいようがないのだが、感覚的であるだけに対処も気持ちの整理もできなかった。
それが、急に変わった。
より悪いほうに、である。
女将に目的を晒したときから、感覚的なものでしかなかった陰気な印象が、とつぜん具体的な形を帯びた。
夜、湯に浸かっていると、急に明かりが消え、磨りガラスの窓の外にひとだまのような、炎のような光が映る。廊下を歩いていると、ほかに宿泊客はいないはずなのに、ほかの部屋からひそひそと囁きかわす声がする。部屋に戻ると、今しがたまで誰かがいたみたいな、生あたたかい、「人のにおいのする」空気がわだかまっている。庭に出ると、荒れた草や木の合間から、あきらかに動物のものではない眼光がいくつもこちらを覗く。
さっさとここを出て行けということなのだろうとは、すぐにわかった。
――わかっちゃいたけど、やっぱり歓迎されるもんじゃないね。けどまぁ、こっちもそのつもりで来たからね。
女将がやっていることではなさそうだった。どうしてあんな年端もいかない娘が孤独に女将をやっているのかはわからないが、とにかく、まだ世間のこともそれほどわかっていないような娘がこなすには、器用にすぎる。あるいは彼女が見せたのはよくできた仮面だったのかもしれないが、彼女以外の人の気配を感じないこの宿で行なうには無理があることが多すぎた。
それにじっさい、ときどき館内ですれ違う女将は、困ったように会釈はしてくるが、探るような質問を投げかけてきたり、様子を窺ってきたりすることはなかった。
3日過ぎた。
その夜、本間に敷いた布団で眠っていた眉月は、次の間から注がれる視線を感じて目覚めた。
眠る前に閉めたはずの襖が、人ひとりが通れるほどの幅に開いている。その向こうから自分の半分ほどもない小さな人影が、ちょこんと正座した姿勢でこちらを見ていた。
次の間に行くには本間を通らなければならないが、いつの間に入ったのだろう。布団のまわりを歩かれても目が覚めなかったのだろうか。
部屋は小さな常夜灯がぽつんと灯されただけの暗さだった。それ以上に暗い次の間の陰に入りこんでいる相手は、何となくの背格好はわかっても、顔だちや、どんな表情を浮かべているのかはわからなかった。
人影は、何も喋らない。
「きみが座敷童?」
眉月のほうから尋ねると、人影はちょっと迷ったようだったが、すぐに「はい」とうなずいた。
声が妙にしわがれている。まるで老婆のようだ。
「ここがなくなったら、私は居場所がなくなってしまいます。ここのことは、あきらめて下さい」
最初は聞き違いかと思ったが、こう続けたことで、やはりそういう声なのだとわかった。
眉月は黙ってしばらく座敷童と対峙していた。やがて座敷童は子どもらしい短い手を伸ばして次の間の襖を閉めようとした。
次の間には出入り口もなければ窓もない。隠し扉なんて気の利いたしかけもなさそうだ。眉月が襖を開けさえすれば、正体はすぐに露見する。それにもかかわらず出て行かないということは......。
「本当はね」
眉月はゆっくりと半身を起こすと、口を開いた。
「ぼくはこの宿をというよりは、正確にはここの座敷童を終わらせに来たんだ。この宿がなくなれば、棲みついている座敷童も消える。そういうことで、この宿を終わらせようとした。見たところお客さんもいなければ、経営を続けなければいけない強い理由があるようでもない。悪くない条件を出せば、ここの持ち主も決して不幸にはならないだろうと思った」
座敷童の頭部が傾く。こちらをあらためて見すえているらしかった。
「それが、きみがこうやって出てきてくれた。これでもう、しち面倒くさい手順を踏む必要はなくなったはずだった。きみの首根っこを掴んで、きみが本来行かなければいけないところに連れていけばいいだけの話だ。でも......」
座敷童はあいかわらず沈黙していた。ただ、息だけが少し早くなったようだった。
「きみは自分が何者だったのか、どうして座敷童になってどうしてこの宿を守っているのか、忘れているみたいだね。思い出してもらわないと、僕はきみを連れていけない。記憶の抜けた魂は、僕にはどうしようもできないんだ」
「お前こそ何者だ」
低く響く声で座敷童は尋ねた。
「早く手柄を立てたがっている不動産会社の社員」
「ふざけるな」
「固有名詞が必要なら、終わりの神様って呼んでよ」
そう言って眉月はにやりと笑った。
(続く)
異色ファンタジー小説連載 毎週火曜日更新
Abnormal Fantasy Novel 2013 [god of the end]
Abnormal Fantasy Novel 2013 [god of the end]
作=Kamisuwa Jun
絵=Inoue Chihiro
絵=Inoue Chihiro
関連記事
終わりの神様
【1】 私が見つめた水
【2】 8月5509日の邂逅
【3】 猫屋敷の住人たち
底本・今昔物語集
口中の獄
稲荷山デイドリーム
百鬼女衒とお化け医師
朱の風吹く

上諏訪純 フェティシズムと日本史と妖怪・人外と幻想文学をこよなく愛しすぎて、
全部足さずにはいられなくなった水瓶座・A型。
好きな歴史上の人物は世阿弥。

井上千裕 絵本とイラストレーションを中心に、物語の表現を研究、制作しています。映画とマンガ、お酒が好きな乙女座A型です。うどん県と納豆県のサラブレッド。






















