

常夜灯のあかりに、座敷童の姿が映し出される。眉月が声を老人のようだと聞きつけたのは間違っていなかった。座敷童は体こそ幼児だったが、老婆の顔をしていた。
――女将さん......?
そう思ったのは、目鼻だちの特徴がよく似ていたからだ。あの女将が年をとったら、きっとこんなふうになるだろう。
「お前は不吉なにおいがする。さっさとここから出て行け」
座敷童は立ち上がり、眉月に掴みかかった。子どもとも老人とも考えられないすばやく鋭い動作だった。眉月はすんでのところでそれをかわし、逆に座敷童を押しのけた。小さな体はあっけなくよろけて転んだ。
「不吉なのはお互いさまでしょ」
眉月も布団から立った。
ふいに、襖絵の椿がせり出してきた。紅白の花弁が左右から迫って、そこに包まれそうになった。
――絵の中に取りこまれる......。
危機を感じたのと同時に、花弁のど真ん中に拳を渾身の力で突きだす。紙の破れる音、続いて木枠が割れる音がして、椿はぱっとかき消えた。
安心したのもつかの間、今度は胸から腰に黒い縄のようなものが絡みついた。振り返ると、床の間の掛け軸の「吉祥」という筆文字の線がにゅるにゅるとこちらにまで伸びていた。
「不吉呼ばわりした上に『吉祥』に攻撃を仕掛けさせるなんて、なんていやみな」
眉月は掛け軸の端に手をかけ、横に引き破った。「吉祥」はちょうど真ん中で「吉」と「祥」に分かれて破れ、体に巻きついていた縄状のものはぱっと消えた。
「付喪神まで操るなんて、そうとう長くこの宿にいついているんですね」
手に残った紙くずをはらいながら言う。
座敷童は何か答えようとしたが、べつの声に打ち消された。
「お客さま! 大きな音がしましたが、どうしました!?」
入口の戸を叩きながら、女将が叫んでいる。
合い鍵を持ってきたらしく、返事をしないうちに戸が開けられた。
「失礼します!」と入ってきた女将の前には、乱れた布団と叩き割られて倒れた襖、真っぷたつに裂かれた掛け軸があった。常夜灯の光量でも惨状は認識できたのだろう、寝間着に羽織の女将は、ぽかんと口を開けて立ち尽くした。
「す、すいません!」
眉月はすかさず頭を下げた。
「えーと、こ、これにはやむにやまれない事情がありまして......! 後ほど会社のほうから弁償しますので、被害額を計算して請求していただけると......」
だが、女将の視線はすでに眉月や壊された調度には注がれていなかった。
「あなたには、その......子が、見えるんですか」
視線を追うと、むくれた幼女のように口をへの字に曲げた座敷童に行きついた。
「あ、ふつうは見えないんですか、やっぱり」
そのとき、床の間から音もなく陶器の壺が飛んできた。
女将が「危ない!」と悲鳴をあげたときには、眉月の後頭部に強烈な打撃が入っていた。鈍い音とともにぶあつい陶器がこなごなに砕け散る。女将はとっさに羽織の袖で顔を覆った。
「だ、大丈夫ですかっ......!」
女将はすぐに顔を上げたが、そこに彼女が予想していた眉月の姿......頭から血を流し、白目を剥いてばたりと倒れる......はなかった。
眉月は頭だけでなく鼻からも血をぼたぼたと流していたが、表情自体はたったいま会話していたときと変わっていなかった。
「大丈夫です、痛かったけど。ところで、あの座敷童なんですけど......」
「逃げます!」
さえぎって、女将は眉月の腕を握った。
「何をしたのかわかりませんが、このままでは殺されます。あの子はこの宿や私を傷つけようとするものには容赦がないんです」
「じゃあ、以前にも似たようなことがあったんだ」
女将はもう何も言わず、眉月の手を引いて部屋を飛びだした。
館内はそれほど広くない。普通に歩いても10分もあれば一周できてしまう程度だ。二人は数分足らずで玄関に着いた。
座敷童は追ってはこなかった。女将は眉月を帳場の脇の椅子に座らせると、タオルを持ってきて、まだ出血の止まらない後頭部に当てた。
「もう、この宿からお出になったほうがいいでしょう。私はいったんお部屋に戻ってあの子を落ち着かせてから、お荷物とお着替えを持てるだけ持ってきます。足りない分があったら後でお送りしますので、ここでお待ちになって、動かないでください。車の鍵はその後に」
女将は怒ったようにも困ったようにも吐き出すと、きびすを返して部屋に戻ろうとした。
「ずいぶんあの座敷童に気を遣っているんですね」
「だって......福の神ですもの」
背中に掛けられた声に、女将が向き直った。
「それにしてはここ、ずいぶん寂れていますよね。お客さんも僕以外にはいないみたいだし」
女将は怪訝そうに眉をひそめた。
「何が言いたいんですか」
「あなたも出ていけばいいのに」
その瞬間、それまで毅然としていた女将のまなざしの底がぐらりと揺らいだ。何か訴えかけるような色が滲み、しかしすぐにかき消えた。豊かな頬が、表面に薄氷が張ったようにひき締まる。その下に、言葉があるように見えた。
直後、足もとがぐらりと大きく揺れた。
「逃がさない!」
建物の底から、座敷童の老いた声が響いた。
(地震!?)
身がまえたが、地震ではなかったことは瞬時に視界の風景が屋外のそれに変わったことでわかった。いつの間にか開いていた玄関の戸から、外に投げ出されたのだ。
尻餅をついた眉月はとっさに正面を見上げたが、そこに女将はおろか、人らしい者の姿はなかった。
玄関の奥から甲高い悲鳴があがった。逃がさない、というのは女将に対してだったらしい。
「女将さん!」
戸に向かって走ると、奇妙に人間的な速さで戸が閉まっていった。もともと意志を持っていた家が、眉月の動きを感知したかのようだった。
「......セーフ」
だが、眉月はすんでのところで手を差し入れて、戸が完全に閉まるのを阻止した。そのまま両手を使って、逆にぐいぐいこじ開けていく。
わずかずつ開いていく戸の奥が、つい今までとくらべて、やけに明るくなっていた。陽気な節まわしの三味線や長唄が、香気がほのかに漂うごとく聞こえてくる。何人かが廊下をばたばたと走り回ったり、怒鳴っているような慌ただしさもあった。
たった一人しか客のいなかった、寂れに寂れきった宿のそれではない。
「なるほど、思い出しかけているね」
うまく手に力が入る角度を見つけると、開けるのが容易になった。
「女将さんには申し訳ないが、僕は核心に近づけることを言ったみたいだ」
抵抗をあきらめたように、急に戸が軽くなった。
いきおい、つんのめって転がりこんだ眉月は、数えきれないほどの艶めいた行燈の灯と、嬌声や三味線や筝、鼓、唄の鳴りひびきと、酒と白粉と汗と香の匂いに同時に包まれた。
そこは広さや建物の造り自体、先ほどとそもそも異なっていた。振り向いてみると、木製の引き戸のはずだった玄関は、重厚でありながらきらびやかな色ガラス張りになっている。
――本館のほうか、こっちは。
すぐに察した。
――座敷童の記憶の中に入りこんだらしい。
帳場にも廊下にも、中庭にも広間にも、人はいたるところに見えるのに誰も眉月には気がつかなかった。しかしそれ以上に異様なのは、そこにいる人々の頭部が、女は満開の百合の花、男は帳場のそばで働いている数人を残して、雑に塗りつぶされたような黒になっていることだった。
百合の女たちは、あるいは長襦袢一枚であったり、あるいは薄紫に染め上げたつややかな綸子(りんず)に、はっとするような原色ばかりが使われた花車紋の着物を帯も締めずにざっと羽織っていたり、そんな風情ばかりだった。それが顔の黒い男たちにしなだれかかったり、からかったりからかわれたりして、あちこちを水底の流れのようにゆるゆると、しかし複雑な取り決めにしたがって進んでいる。
――ここは遊郭だったのか。
それも、すぐにわかった。
――ずいぶん前だな。100年以上は経っていそうだ。
楽の音は、再生する機械の調子が悪いみたいに、しょっちゅう音程や速さがずれた。生ぬるく澱んだ空気の中を歩いていくと、廊下がところどころぷつんと切れていたり、襖を開けて覗いた部屋がいきなり海鳴りのする断崖絶壁になっていたりした。吹きぬけの人工庭園に置かれた石灯籠は、目を逸らすたびにいちいち場所を変えた。
――記憶が曖昧なのか、完全に思い出すことを拒否しているのか......まぁ、両方だろうけど。
ふと、賑やかな音の洪水の中を細い絹糸が一本たよりなげに伸びてくるように、女の咽び声が聞こえてきた。
眉月は耳に神経を集中させた。気を抜いたらすぐに聞きとれなくなってしまいそうなほど微かだった。音を注意深くたぐっていくと、足は次第に階上へ向かっていった。
最上階である3階には、人影はなかった。あちこちに食器や酒器が積み上げられていたり、壊れた調度が隅に押しやられているところからして、一階まるまる物置として使われているらしい。樟脳と黴が入り混じって匂っている。
声はいくつかある部屋のひとつからしていた。その部屋の襖を、眉月はとくに迷いもせずに開けた。
赤い奔流が、目に飛びこんでくる。
部屋のあちこちに積み上げられた赤い布団だった。眉月の背丈ほどになっているものもある。天井に無造作にぶら下げられた裸電球の灯りに陰影を刻んでいるさまは、真紅の山々とでもいうべき様相だった。
その中で電球と同様、天井から宙吊りにされている女がいた。女将だった。両手を後ろ手に回され、両脚は頭部よりも高く上がって、海老が跳ねているような格好で縛り上げられている。
萌黄色の襦袢が腰の上までずり上がってというべきか、ずり下がってというべきか、とにかく尻が剥き出しになっていた。尻はもともとは白くなまめかしかったのだろうが、それはもはや肌のほんのわずかな部分からしか想像することができない。今は至るところに縦横に棒状の跡がつき、真っ赤になって腫れあがっている。口には頬に食いこむほどきつく締められた猿ぐつわが噛まされていた。
恥ずかしいのか、助けてほしいのか、女将は眉月が来たことに気づくと体をよじらせたが、縄は体に食いこむばかりで緩みはしなかった。もっとも緩んで落下でもしたら、今以上にたいへんなことになるだろう。
「座敷童さん」
布団の影からにゅっと突き出ていた長い棒に向かって、眉月は呼びかけた。
「そんなにまでして、女将さんを逃がしたくないんだね」
「ふん」と、鼻を鳴らす音がした。
近づくと、座敷童が布団と布団のあいだに小さな体を埋めこんで座っていた。その姿は顔が老婆であることを除けば、いじけて隠れている幼児のようでも、血まみれの産道をこじ開けて今にもこちらの世界に出てこようとしている赤ん坊のようでもあった。
長い棒は、まだ青々として硬そうな竹だった。座敷童の身長の倍ほどはあるだろうか。これで女将を打擲したのだろう。
「血のつながった娘......なんでしょ?」
尋ねるというよりは確認のつもりだった。
「だからだよ」
座敷童はいまいましげに唾とともに吐きだした。
「ときどきはね、自由にしてやりたいと思うこともある。だけど、すぐにそんな気持ちは消えてしまうんだ。何代も何代もこんなことが続いて、私たちはあまりにも澱んで、ただれてしまった」
「......思い出したんだ」
「お前が無理やり入りこんできたせいだ。思い出したくなんてなかったよ。宿と女将をわけもわからないまま守る、無邪気な化物でいたかった」
眉月は座敷童に近づいて、しなびた首にゆっくりと手をかけた。座敷童は拒みもせず、自嘲するように小さく笑った。背後で女将が猿ぐつわごしに息を呑んだ。
「今は人より鹿や狸のほうが多いぐらいになっちまったけど、このあたりは昔はずいぶん栄えていてね、ここの女は代々この遊郭の女将だった。何人もの女を使っていたし、自分自身も体を売っていた。今、ふん縛られてる娘もそうなんだよ。女はいなくなったし、本人だって昔よりこなす回数はずいぶん少なくなったが、何にしたって股を開いてなんぼの姐御さね」
手をかけられたまま青竹を置いて、座敷童はおもむろに左目をえぐり出した。最初から軽く嵌めこまれただけだったように、目玉はあっけなく摘みだされた。眼窩から血が噴きだすこともなかった。
座敷童は取りだした左目を電球に透かし、残った右目で覗きこんだ。
「悪いことばかりでもなかったけどね、いいことばかりでもなかった。悪いことのほうがずっと多かったかな。こういう仕事だ、わかるだろう」
座敷童は目玉をぽとりと落とした。乾いた音を立てて、目玉は床を転がった。
眼窩にはべつの目玉がせり出していた。座敷童はまたえぐり、覗いて、また落とした。
「遊郭でなんぞ生まれたら、それ以外で生きていくすべなんて見つけようもないんだ。それにいつしか、出て行きたくても出て行けなくなってしまった」
「どうして」
「座敷童が、ここから出してくれなくなった」
まるでそっけなく他人を指すような口調だった。
「さっき、私ではなく、私たち、と言ったね。座敷童はあなた一人じゃないんだ」
「座敷童、つまり私は、歴代の女将の死霊が集まったものだ。その中の誰ということはない。女将が死ねば、その魂は私たちに取りこまれる」
何度えぐっても、目玉はつぎつぎ現われた。座敷童は中身を透かし見るたびに、うっすらと笑ったり、歯を食いしばったり、泣きそうになったりした。いつしか目玉は飽きられて捨てられたビー玉さながらに、あちこちにいくつも転がっていた。
「家を栄えさせようとしたのか?」
「いや、もっと......どうしようもない理由だよ」
落ちた目玉のひとつから、小虫の羽音よりも小さな音で女の叫びが聞こえた。拾って、座敷童をまねて覗いてみた。
そこに見えたものに、眉月は思わず顔をしかめた。
目玉には、かつて女将たちの目に映った映像が焼きつけられていた。何年、何十年、ひょっとしたら何百年にもわたる記憶が、それぞれの眼球に湛えられているのだ。手のひらに握りこむと、それはほのかな熱を帯びていた。
「女将たちの怨念は、今、生きている娘が自由になることを許さない。悔しいんだ。取りこまれる前はみんな自分にはそんな気持ちはないと思っているし、意識にさえ上らないこともある。でもぜったいに、どんなに少なくても、ないことはないんだ。取りこまれると、その思いがどうしようもなく膨らんでしまう。私たちは決して、ここから娘を解放しない。同じように体を売らせて、同じようにここで朽ち果てさせる」
東京の本社に行かないかと持ちかけたときに表情をこわばらせた女将を、眉月は思い出した。
「もし、娘が無理に出て行こうとしたら?」
「『呼びもどす』だけだ。どの娘も体と心が壊れて、一年もしないうちに帰ってきたよ。この娘もそうだった」
座敷童は顎で女将を指した。
「そうかい、よくわかった。......どれほど娘が憎いのか」
眉月は握っていた目玉を浴衣の袂に入れながらうなずいた。
片手はかわらず、座敷童の首に掛けられている。
「つらいだろう」
「......まさか」
「じゃあ、どうして記憶を封じこめていた? 姿を変えて、みずからを座敷童だなんて思いこんでまで」
「............」
「行こう。僕と一緒に来たら、あなたはずいぶん楽になれる」
「......いやだ!」
座敷童は首に掛けられた眉月の手を払い、布団の隙間を飛び出した。眉月が振り返ったときには、吊られた女将の頭部に青竹を打ち下ろす体勢をとっていた。
女将の目が恐怖と驚愕に見ひらかれる。
「いやだ、私たちが行ったらこの娘は自由になってしまう」
「......そうだけど」
「そんなことは絶対にいやだ。この娘だけが幸せになるなんて。私は出て行けなかったのに」
縛られた女将は必死の形相で、頭を前後左右に激しく振った。体が巨大な振り子さながらに揺れる。縄を巻きつけた梁がきしんだ。
噛まされていた猿ぐつわの結び目がゆるみ、ほどけた。手ぬぐいが涎の糸を引きながら落ちた。
「おかあさん」
女将は息を吸うのももどかしそうに、座敷童を呼んだ。さんざん呻いた後だからだろう、声がかすれていた。
座敷童の動きが止まる。
いや、座敷童は最初から、青竹を振り上げた姿勢のまま止まっていた。それが、さらに凍りついたようになった。
「おかあさん、ごめんなさい」
「........................」
座敷童は、膝から崩れ落ちた。
いつの間にか後ろに立っていた眉月が、その首からゆっくりと手を放す。
倒れた座敷童のうつろな左の眼窩から、積みあげられた布団よりも赤く鮮やかな血が、堰を切られたように流れだした。
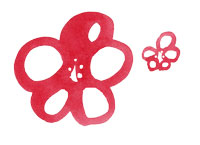
「女将さんは、座敷童の正体をご存じだったんですよね?」
荷物をまとめた眉月は、帳場前の椅子に座って、出された茶をすすった。
質素な朝食をとり、チェックアウトを済ませたところだった。予定していた滞在日数より短かったが、女将は何も言わなかった。
「記憶を失った私たちの先祖なのだというのは、小さいころからずっと聞かされていました。それに、祖母や母と似た顔をしていましたし」
「ご家族がいないことと座敷童とは関係があるんですか。じつはご家族は、どこかにこっそり避難させているとか」
「いいえ、私にはほんとうに家族はいません」
女将は寂しそうに笑いながら首を横に振り、こう説明した。
先代の女将......つまり女将の母は、夫を迎えず子どもも生まないことで座敷童に対抗しようとした。しかし、やっていることがやっていることである。結局、今の女将が、父もよくわからないままに産まれてしまった。そのうちに先々代が死に、先代も若くして死に、彼女だけが残った。
「母は生前、自分はぜったいに座敷童にはならないと言っていました。口を開けば私にあやまってくるような人でした」
眉月が黙って湯呑に口をつけると、今度は女将が質問した。
「どうしていきなり母たち......座敷童を連れていくことになったのですか?」
眉月は腕を組んで首をかしげた。今までも何度も「残された」者に尋ねられたことのある質問で、そのたびにしてきた仕草だった。
「さぁ、詳しいことはわかりません。僕も上から命じられてやっているので。でもとにかく、彼女たちのような存在は、いつまでもこちら側に留まっているべきではないのです。あとはたぶん......」
「たぶん?」
「こういうの、もう時代遅れだからじゃないですかね」
玄関にまで差しこんだ午前の日差しの向こうで、名前もわからない鳥がチチ......と茶化すように鳴いたのが、妙に響いて聞こえた。
もしかしたらあまりよくないことを言ってしまったのかもしれないと、眉月は「お若いのに、ずいぶん長いあいだ我慢してきたんですね」と咳払いにまぶしたが、すぐに、これも少し違うと思った。
「たしかにいやでしたけど......こんなのはおかしいんじゃないかって、実際に逃げ出したこともあるけれど」
女将は話しにくい告白をするように目を逸らし、かわりに眉月のコートのボタンに焦点を合わせた。
「いつからか、座敷童がかわいそうになってしまったんです。おばけにまでなるなんて、よっぽどの目に遭ってきたんだろうって」
そういえば、女将は座敷童を「かわいそう」だと言っていた。
「それと、眉月さんはひとつ、大事なことをご存じになっていません」
「大事なこと?」
眉月は覚えず背筋を伸ばした。
頭の中で、ぴんと張りつめるものがあった。
「この家の座敷童は、福をもたらすという意味では、むしろ私なんです。そして座敷童も、もとはそういう意味でもたしかに座敷童でした」
「......どういうことですか?」
「ここの女には遺伝的に、交わった男を極端に出世させる能力があるんです。初代の女将はそれに気づいて、娘や孫たちに同じように体を売らせました。ここが規模は小さくなりながらも続いているのは、私たちの秘密を知る政界や財界の人たちが、数は少ないながらも今もひっそりと訪れているから」
女将は例として3人ほど政治家と財界人の名を挙げた。その名は政治や財界にほとんど興味のない眉月でも知っていた。
眉月はもう一度、こっそり近くの内装や調度品を眺めた。だが、あらためて確認するまでもなく、質も意匠も地味ではあるがきわめて上等であることは、この数日の滞在でわかりきっていた。
「国を変え、根底から動かす男が、子宮から生まれ直すかのようにこの宿から出ていく。そういうところを何度も見ていると、何というのでしょう......やみつきになってしまうんですよね。もちろんこんな仕事ですからいやなこともありますが、それでも癖になるんです」
女将ははにかむようにうつむいて、手と手を重ねた。その指に、昨日まではなかった指輪がはめられていることに、眉月はやっと気がついた。指輪の頂点には透きとおった小さな石が嵌めこまれていて、ほくそ笑むようにひっそりと輝いていた。
「時代遅れとおっしゃいましたけど、私たちの内面も、母まではたしかにそうだったかもしれません。でも私は、みんなもっと楽しんだり、自分の力に酔ったり、こちらから男を選んであげたりしてもよかったのにと思っていました」
妖女の系譜、という言葉が、ふと脳裏に浮かんだ。家や先祖に翻弄され、疲弊しきって古妖怪になってしまった、華やかで美しいが哀れな女たち。この女将はその果てに生まれた鬼子なのだろうか。血に支配されるのではなく、血と戯れることを知った突然変異体なのだろうか。
そんなことを考えていると、彼女が苦しげに「ごめんなさい」と謝ったのは、何に対してなのかわからなくなってきた。
眉月はまじまじと女将を見すえた。最初は見くびる材料になっていたあどけない目鼻だちが、今度は逆にそらおそろしいものに思えてきた。
「苦しんでいた先祖を救って下さったことには感謝します。でも、この宿は手放しません」
女将はきっぱりと言って、それから、可憐に微笑んだ。
「私も母たちと同じところに連れていきますか? 座敷童として」
「不機嫌な座敷童」了
異色ファンタジー小説連載 毎週火曜日更新
Abnormal Fantasy Novel 2013 [god of the end]
Abnormal Fantasy Novel 2013 [god of the end]
作=Kamisuwa Jun
絵=Inoue Chihiro
絵=Inoue Chihiro
関連記事
終わりの神様
【1】 私が見つめた水
【2】 8月5509日の邂逅
【3】 猫屋敷の住人たち
【4】 不機嫌な座敷童
底本・今昔物語集
口中の獄
稲荷山デイドリーム
百鬼女衒とお化け医師
朱の風吹く

上諏訪純 フェティシズムと日本史と妖怪・人外と幻想文学をこよなく愛しすぎて、
全部足さずにはいられなくなった水瓶座・A型。
好きな歴史上の人物は世阿弥。

井上千裕 絵本とイラストレーションを中心に、物語の表現を研究、制作しています。映画とマンガ、お酒が好きな乙女座A型です。うどん県と納豆県のサラブレッド。






















