
というのも、それからすぐにおじさまは亡くなってしまったのです。
修三郎さんが私を連れ出した理由も、そのときになってやっとわかりました。
おじさまは私を殺そうとしていました。
平川のお家のあった村は、人蛇に関する伝説がたくさん残っていたところでした。「人蛇を飼う家は栄える」というのもそのひとつで、それでおじさまはずっと私の世話をしてくれたようなのですが、ほかに「人蛇の心臓を食べればどんな病もたちどころに癒えて、不老の体になれる」との言い伝えもあったらしいのです。おじさまは背に腹は代えられないと、私を殺して心臓を取り出してくるようにお家の方に命じたのでした。修三郎さんは私がそんな目に遭うことをどうしても見過ごせなくて、助けてくれたのです。
出がけに会った女の人が言った「お願いします」の内容もわかりました。
あの看護婦の女性はずっとおじさまのお世話をしていましたが、私が殺されることが決まったとき、反対した修三郎さんにそっと、私を逃がすのを手伝う代わりに頼みたいことがあると持ちかけてきたそうでした。
「人蛇と人間は本来は棲む世界をまったく異にするもの。お前を平川の家から連れ出したらなるべく時を置かず、もともといた湖に戻してやってほしい、と言っていた」
私は首をひねりました。なぜそんなことを頼むのでしょう。彼女と私は面識などありません。そもそも、私が離れに隔離されていたのは近隣の目に触れさせないためということでしたが、そんな私のことをなぜ彼女は知っていたのでしょう。
私は素直に疑問を口にしました。
「俺もわからない。ただ彼女は、このままお前が人間の世界に居続けたら、遅かれ早かれよくないことが起こるだろうと言っていた」
修三郎さんもまた、腑に落ちていない様子でした。
ともあれ私を殺すことが翌日に迫ったその夜、修三郎さんは急がねばなりませんでした。看護婦さんはごく少量の睡眠薬を皆さんの飲み物に入れ、皆さんが眠ってしまったわずかな時間に、修三郎さんは私を連れ出したのでした。
「だけどあの看護婦が何者であれ、俺もお前を元いた場所に戻してやりたいと思っている。俺たちとお前は形(なり)は多少似ていてもまったく違う生き物だ。平川の家はもう十分な富を得たし、兄たちもお前に強く頓着しているわけじゃない」
修三郎さんは、自分の大人の体と、私のほとんど子供のままの体を交互に見比べていました。私はそのとき尾をすっかり脚に変えていましたが、そんなことは関係ないようでした。
「お前がどのあたりで拾われたのかは、昔、親父が酔うたびに話してくれたから大体わかる。近くまでいけば湖も見つかるだろう」
「いやです」
ほとんど反射的に答えました。
「今さら帰りたくありません。いいえ、帰れません。私はもう、湖での暮らしをすっかり忘れてしまいました。きっと向こうには馴染めません。私がいたいのはこちらの世界です」
興奮のあまり、顔が熱くなっていきます。まくしたてるように言ったそれらの言葉は、どれもこれも本当のことでした。
いいえ、じつはひとつだけいちばん大事な本心を晒してはいませんでした。湖に帰ってしまえば、修三郎さんとは今以上に会えなくなるでしょう。もしかしたら二度と姿を見ることもできなくなるかもしれません。私はそれがいやで......怖くてたまらなかったのです。
結局修三郎さんは、私を無理に帰すようなことはしませんでした。私がこちらにいたがるのは、元はといえば無理に連れてきた平川の家に責任があると考えたようです。もしくは、おいおい説得していけばいいとしたのかもしません。
それに修三郎さんは学生でありながら、家族の援助のおかげで小さくも独立した一軒家に住んでいました。私と暮らすのに何の不都合もなかったのです。とはいえ、ご実家のお兄さまたちには私をどうにかして山に帰した、と話していたようですが......。
翌年、修三郎さんは大学を卒業し、新聞社に勤めるようになりました。
修三郎さんは毎日忙しく働きました。半年後には何か思うところがあったのか、お給料でやりくりできるアパートに住居を変えました。その年、天皇陛下がお亡くなりになり、新しい昭和の時代が始まりました。
そのうち、お家にはある女の方が出入りするようになりました。修三郎さんよりも一つ年下で、女性雑誌の編集をしているというその女性は、たえ子さんといいました。私はたえ子さんに、家族を亡くしたために一時的に預かっている親戚の子供だと紹介され、その通りに振る舞いました。二人に嫌われたくなかったからです。私はたえ子さんが家に来たときは少女雑誌を何冊か渡されて、すぐに迎えに行くから家の近くで大人しくしているように言われました。
やがて、修三郎さんとたえ子さんは結婚することになりました。話があっという間に決まったのは、たえ子さんのお腹に赤ちゃんがいるとわかったからでした。修三郎さんがたえ子さんの紹介のために平川のお家に戻られたとき、私は東京のお家で一人でお留守番をしていました。
たえ子さんは男の子を生みました。修三郎さんにもたえ子さんにも似た、目鼻だちのしっかりした子で、実と名付けられました。昭和四年のことです。
実は、生まれてから三カ月足らずで母親を失いました。出産のときに体を壊したたえ子さんは、結局その後回復せずに世を去りました。修三郎さんは考えに考えた末、母のない子を多忙な父のもとで育てるのは不憫だからと、実を実家に頭を下げて預けると決めました。頭を下げるというところに、修三郎さんの複雑な思いと立場がありました。私を逃がしたことで家主をいわば見殺しにし、婚前交渉で妊娠した女性と結婚した修三郎さんは、古い因習に則って暮らす田舎の家からしてみれば異端児でしたから。
私は止めました。そうして自分が母代わりになって実を育てたいと懇願しました。
私には罪悪感と恐怖がありました。正直に言うと、私はずっとたえ子さんを邪魔だと感じていました。いなくなってしまえばいいとひそかに願っていました。予知夢を見、心臓が人を不老にするといわれた私です。強い思いが現実に影響を及ぼしたとしても不思議ではありません。たえ子さんが死んだのは私のせいかもしれない。私がたえ子さんを殺したのかもしれない。もしもそうだとして、たえ子さんに罪滅ぼしができるとしたら、実を修三郎さんのもとで、たえ子さんがそう育てるはずだった立派な男の子に育て上げること以外にないと思いました。
予想していましたが、修三郎さんは反対しました。まだほんの娘の、少なくとも娘にしか見えない私に育てられるわけがないというのです。このとき私はやっと14、5歳に見える程度でした。
土下座をしました。畳に額をすりつけました。罪悪感が大きかったのもありますが、かたわらで眠る実を見ていると、この子と離れることがつらくてたまらなくなりました。まるで本当に私が産んだ子のような気がしてきました。
実を抱いて出て行こうとする修三郎さんの足にしがみついたまま玄関まで運ばれたところで、やっと修三郎さんは許してくれました。こうして私と実は、母と子というよりは、年の離れた姉と弟のような親子になりました。私たちは修三郎さんが通勤しやすい都心に引っ越し、私は小さな弟を母代わりに気丈に育てる姉として周囲に見られるようになりました。実もまた、私のことを姉だと思って育ちました。
ですが、いずれ本当のことを話さないといけなくなったときのことを考えると、不安に駆られました。実はすぐに私の見た目の年齢に追いつくでしょう。私が人間とは違う生物だと知ったとき、実はどう受け止めるでしょうか。
とはいっても、その不安にそんなに強く支配されたわけでもありません。それよりもどんどん不穏になる雰囲気と、その行く末を示すような不気味な夢をたびたび見るようになっていたことのほうが、ずっと気になっていました。
中でも怖かったのは、十一年の二月に起こった昭和維新未遂事件(※1)です。陸軍の内乱で政治家や軍人がたくさん襲われて、一時東京は騒然となりました。民衆に直接の被害はなかったのですが、修三郎さんの勤めていた新聞社に兵隊さんがやって来て、彼らの志を示す文章を掲載するよう迫られたと聞いたときには、そこまでは夢で見ていなかっただけにぞっとしました。
十四年になると第二次世界大戦が始まり、国力増強のためにとさんざん節制生活を強いられた後、十六年の年末には太平洋戦争の火蓋が切って落とされました。実は十二歳になっていました。
戦争が進むにつれ、男の人たちが次々と兵隊に取られて行きました。実は規定年齢に達していなかったため、修三郎さんは新聞記者だったために徴兵されることはありませんでしたが、それを幸いと思うことはできませんでした。昭和二十年が明けてすぐに、東京が焼き尽くされる空襲の夢を見たからです。続いて、どこかはわからないけれど東京ではないところに、見たこともないような巨大な爆弾が落とされる夢を見ました。
それらがいつ起こるかはわかりません。しかし必ず起きることは間違いありません。私は東京から逃げようと訴えました。ですが、たとえ起こるとしても、今、仕事を失ったら、生き残ったときに死ぬよりみじめな人生を送ることになると、修三郎さんは聞く耳を持ってくれませんでした。
私はこのとき初めて、生まれ育った湖に帰ることを考えました。修三郎さんはあきらめるとしても、実だけは守りたい。頼れる場所があるとしたら、あの湖だけでした。
ですが、結局はあきらめるより他ありませんでした。平和なときでさえ行くのに手間と時間がかかる山中のその場所に、戦乱期の真っ只中に誰の助けもなく、十六歳ほどにしか見えない私と実際に十六歳の実が行くのは至難のわざでしたし、さらにあろうことか実が志願兵に名乗りを上げたいと言い出したのです。実はすでに私が人蛇であることを知っていましたが、自分だけ逃げ出そうとするなんてやはり私は人間とは違って卑怯だと罵りました。
私たちの間に滞った気まずい空気が払拭されないうちに、その日はやってきました。三月十日、東京は大空襲に見舞われました。が、この空襲は少なくとも私にとっては吉と出ました。家族の中で怪我をしたのは実だけでしたが、おかげで軍隊に入ることができなくなりました。太腿を骨折した実は、修三郎さんが出社し、私が隣組に参加して消火訓練や防空訓練の練習をしている間、布団の上で空しく祖国の勝利を祈っていました。
その後も何度か空襲があり、夏になって広島と長崎に原子爆弾が落とされて、やっと戦争は終わりました。修三郎さんや実は玉音放送を聞きながら泣いていましたが、私は内心せいせいしていました。たとえアメリカの植民地にされるとしても、こんなことはもう本当にごめんでした。なぜもっと早く終わらせられなかったのかと、言葉にはしないながらも憤慨しました。それから、これもまた誰にも言えませんでしたが、これからは戦時中には想像さえうまくできなかったバナナをきっとたくさん食べられるようになると思うと、とても楽しみでした。私があまりにも好むものだから、実もバナナが好きでした。実にもたくさん食べさせてあげることができるでしょう。
新しい時代が始まると、修三郎さんも実も意外なほどあっさり立ち直りました。GHQが軍部の横暴を明るみに出したせいもあったでしょう。修三郎さんは手のひらを返したように日本軍を批判し、アメリカ軍を褒め称える記事を作り始めました。実も早々に英語の勉強を始めて、進駐軍に用もないのに話しかけるような有様でした。
食糧のない時代ではありましたが、修三郎さんのおかげで私や実はそれほど飢えずに済みました。あのとき修三郎さんが私の誘いのまま、記者の仕事を捨てて逃げ出していたらと思うと、感謝せざるを得ません。
配給の品を取りに行き、闇市でお芋を買い、道端の傷痍軍人に怯え、日々をとにかく生き抜くうちに憲法ができ、建物や交通網が整備され、時は1950年、昭和二十五年になりました。
この年に修三郎さんは亡くなりました。享年は四十七歳でした。平川のおじさまと同じ胸の疾患でしたが、十歳以上早い旅立ちでした。戦争が終わって気が抜けたのが悪かったのかもしれません。
修三郎さんが助からないと知ったとき、私はひどくうろたえました。みっともないぐらいうろたえにうろたえて、最後に、このまま生きているよりは自分の心臓を修三郎さんに食べてもらおうと決めました。そのためにはどうしたらいいか。実の力を借りなければいけないでしょうが、何を、どう頼んだらいいのか。実を帰して修三郎さんと二人になった夕暮の病室で、私はじっと考えていました。
そのときです。あの夜、平川の家の裏門から私たちを見送った看護婦さんが、ふいに病室に現われたのです。
最初は病院勤めの看護婦さんが入ってきたのかと思いました。ですが、何だか様子がおかしい。何よりも違和感があったのは、着ているものです。白衣なのですが、少し時代がかっていました。
記憶を取り戻した途端、茫然としました。その人は二十五年以上経ったと言うのに、あのとき、あの夜のままの姿でした。私でさえ多少は年をとったのに、その人はまったく何も変わっていませんでした。
修三郎さんは眠ったまま、目を覚ましませんでした。
「湖に帰らなかったんですね」
看護婦さんは言いました。凍った夜の空気の中で聞こえたのと、確かに同じ声でした。
「そんなことをしたら彼、死にますよ。もっとも放っておいても死にますが」
「そんなことって、あなたに何がわかると......」
「あなた、自分の心臓を食べさせようとしていますよね」
看護婦さんの回答に、体から血が引くのがわかりました。どうやらこの人は私がやろうとしていることをわかっているらしい。誰にも話していないのに、どうしてそんなことができるでしょう。
もしくは......この人は私の作りあげた幻なのかもしれない。
だとしたら、これは予知夢の一種と考えることもできます。心臓を食べさせることに、もしかしたら何かとんでもない危険が潜んでいるのかもしれません。
決してそんなことをしてはいけないと釘を刺し、看護婦さんは病室を出ていきました。
湖に一度帰ろう、と思いました。私の知識はあまりにも不十分です。人蛇たちが詳しいことを知っているかどうかわかりませんが、そこしか頼れそうなところはありません。
実に修三郎さんを助ける手立てを探すとだけ伝え、私は平川のお家のある山間の村に一人で戻りました。平川のお家には、もちろん立ち寄りませんでした。
山の場所も湖のある場所もすぐにわかりました。帰巣本能というのでしょうか、帰ろうと強く念じると、そこに至る道が頭の中に浮かび上がるのです。山中だというのに迷うこともなければ動物に襲われることもなく、私はじつにあっさりと生まれ故郷に戻りました。
脚を尾に戻し、服を脱いで水に飛びこみました。深く、深く潜っていきます。その感覚はとても懐かしいものでしたが、ずっと浸っていたいとは思いませんでした。
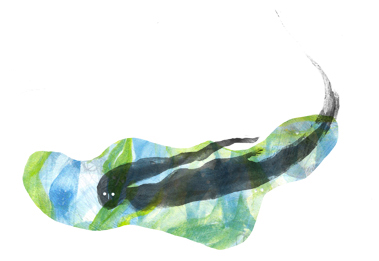
水の底では見覚えのある仲間たちが、今までいたところとは比べものにならないゆったりとした穏やかな生活を、巨大な水草の影で営んでいました。小さな頃に一緒に遊んだ友達が、今の私と同じ、人間でいえば17、8歳ぐらいに成長しています。彼らは驚きながらも、すぐに暖かく迎え入れてくれました。小さい頃に覚えたことは忘れないものなのか、言葉もたどたどしくはありましたが問題なく喋れました。
三日ほど留め置かれ、人の世界で生きるようになった経緯を説明させられ、戻って来いと繰り返し説得されてから、私はやっと人蛇の心臓の秘密について、あるおばあさんから聞き出すことができました。いわく、人蛇の心臓は人間にとって、決して不老の妙薬になどならない。ごくわずかな確率でそうなる者もいるが、ほとんどの場合は毒として作用し、苦しみぬいて死ぬ。それよりは生き血のほうがまだましだが、それも同様に毒として作用する可能性のほうが高い。
「昔は人間に子供が攫われたものだけど、それがわかってからはむしろ恐れられるようになってねぇ」
おばあさんは本当に知っているのか、誰かから聞いたことを話しただけなのかわかりませんが、目をしきりに細めながら教えてくれました。
翌日、こっそり逃げ出すように湖を出ました。仲間には申し訳なかったけれど、修三郎さんの命には替えられません。急いで山を下り、駅に着いて、東京行きの切符を求めました。
一瞬、自分の目を疑いました。駅に掛かっていた日付が、出てきた日から3カ月近く過ぎているのです。その日付のほうが間違っているのだと思って新聞も確認しましたが、やはり同じでした。
いやな予感がして、すぐに家に電話をしました。
修三郎さんは、一月以上前に亡くなっていました。
湖の中と人間の世界とでは、時間の進む速さが違っていたのでした。
昭和が終わって平成になり、世紀が変わってから、もう三十年になります。最近は、時間が経つのをとても速く感じます。修三郎さんが亡くなったのも、ついこの間のことのようです。
私もさすがに年をとり、今は人間でいえば三十歳をいくつか超えたほどの見た目になりました。もう若いとは言われません。
実は修三郎さんが死んだ翌日に大学を卒業し、商社に就職にしました。それから数年後には、修三郎さんの同僚の方が紹介してくれたお見合いで結婚しました。ですが、その生活は長くは続きませんでした。修三郎さんのときと同様に、お嫁に来てくれた方が若いうちに亡くなってしまったのです。やはり私は、そういう点に対してもとても特別な......とてもいやらしい力を持っているのでしょう。
それからも恋愛らしいことはしたようですが、結局再婚はしませんでした。私は実のことを考えれば実のもとを離れるべきだったのでしょうが、どうしてもできませんでした。言い訳をするつもりはありませんが、実に止められたのです。私はいつしか実の妻のような存在になっていました。
母から始まり、姉を経て妻になった私は、やがて妹や年の離れた妻として、それから娘として振る舞うようになり、とうとう孫になりました。でも実は、外に見える立場はどうであれ、生きている限りは私にとってはやはり息子です。
今、実はこの時代最先端の延命治療を受けています。私の能力のおかげで、私たちは今もお金には困っていません。ですがそんな機械も、実には本当は必要ありません。私が毎日、自分の体から絞った血を飲ませていますから。実は最初こそ少し苦しんだけれど、そのうち素直に飲み下ろしてくれるようになりました。
病室のテーブルに置いたバナナが甘く匂っています。今、ここでベッドに横たわっている実がまた元気になったら、きっとまた食べたがるでしょう。
「それにしても看護婦さん、あなたは全然、お変わりにならないのですね」
私は先ほど病室に入ってきて、実の運命とやらを告げた看護婦さんに話しかけました。それは大正時代、修三郎さんに連れられて逃げた夜に会った、あの看護婦さんでした。服装も肌も顔だちも、やはりそのままでした。
ふいに実の手がぴくりと動き、続いて唇が震えるようにわずかに開きました。何か言いたいことがあるのでしょうか。私は皺を描いた自分の手で、すかさず実の手を取りました。私は少し前から顔や手に、実と同じような皺を化粧品を使って描いていました。腰や背も、実のように曲げて歩きました。
お母さんもね、お前と同じように年をとったのよ。ほら見て、この皺を。ね、お前と一緒でしょう。一緒に生きて、一緒に死にましょう。
「何? 聞こえない。もう一度言って、ねぇ、実......」
空気だけがこぼれ落ちていく萎んだ唇に、私は耳を近づけました。
「お母さん」
実は、言いました。はっきりと、お母さん、と言いました。
「......苦しいよ......死なせて」
今、何と言ったのでしょう。何度か聞いた覚えもあるような気もしますが、意味がよくわかりません。きっと夢うつつで、うわごとを呟いているのでしょう。
看護婦さんが近づいてきて、私の肩をそっと抱きました。そして、ポケットに用意していた何か柔らかくて温かいものをそっと取り出すように、こう言いました。
「もう、同じ時間を生きる仲間たちのところへ戻りましょう」
意識がすぅっと遠ざかっていきます。完全に気を失う直前に、私は水の底の、陽の光を受けて音もなく揺らめく水草を見ました。
「百年の孤独」了
異色ファンタジー小説連載 毎週火曜日更新
Abnormal Fantasy Novel 2013 [god of the end]
Abnormal Fantasy Novel 2013 [god of the end]
作=Kamisuwa Jun
絵=Inoue Chihiro
絵=Inoue Chihiro
※1 二二六事件
関連記事
終わりの神様
【1】 私が見つめた水
【2】 8月5509日の邂逅
【3】 猫屋敷の住人たち
【4】 不機嫌な座敷童
【5】 曼珠沙華が咲くまでに
【6】 15年目のスーパーヒーロー
【7】 夜と呼ばれたもの
底本・今昔物語集
口中の獄
稲荷山デイドリーム
百鬼女衒とお化け医師
朱の風吹く

上諏訪純 フェティシズムと日本史と妖怪・人外と幻想文学をこよなく愛しすぎて、
全部足さずにはいられなくなった水瓶座・A型。
好きな歴史上の人物は世阿弥。

井上千裕 絵本とイラストレーションを中心に、物語の表現を研究、制作しています。映画とマンガ、お酒が好きな乙女座A型です。うどん県と納豆県のサラブレッド。






















